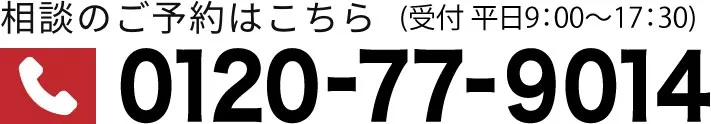企業法務コラム
熊本で懲戒解雇・退職勧奨を検討中の企業様へやってはいけない対応と適切な進め方について弁護士が解説
更新日:2025/11/25
熊本で企業を経営する中で、従業員の労務問題について、以下のようなお悩みをお持ちではありませんか。
- ・問題行動を繰り返す従業員に、どう対応すればいいかわからない。
- ・不正行為が発覚し厳正な処分を下したいが、手順が不安だ。
- ・会社の将来を考え、円満に従業員に退職してもらいたい。
このような問題で最も重要な結論は、感情的に判断せず、弁護士へ相談して、法的に正しい手順を踏んで対応することです。なぜなら、懲戒解雇や退職勧奨は手順を間違えると「不当解雇」として訴訟に発展し、賃金の支払命令や企業イメージの低下など、会社が大きなダメージを負うリスクがあるからです。
この記事では、熊本の経営者様が従業員の問題を解決するための具体的な道筋を、法的な観点からわかりやすく解説します。
- この記事でわかること
-
- 懲戒解雇・退職勧奨で絶対にやってはいけないこと
- 懲戒解雇と退職勧奨の違い
- 状況に応じた「懲戒解雇」と「退職勧奨」の使い分け
- 法的に有効な手続きの具体的なステップ
- 懲戒解雇・退職勧奨を熊本の弁護士に相談するメリット
目次
懲戒解雇・退職勧奨を考える前に!経営者が絶対にやってはいけない3つのこと
従業員による重大な問題が発覚したとき、経営者として憤りや失望を感じるのは当然のことです。しかし、その感情に任せて行動すると、事態をさらに悪化させる危険性があります。懲戒解雇や退職勧奨を具体的に進める前に、まずは以下の3つの行動を絶対に避けてください。
- 感情的に解雇を告げる
「もう顔も見たくない」「明日から来なくていい」といった感情的な言葉で解雇を告げるのは、最も危険な対応です。たとえ従業員に明らかな非があったとしても、感情的な解雇通告は、後の裁判で「冷静な経営判断を欠いた、違法な解雇」と判断される大きな要因となります。従業員とのやり取りは、ICレコーダーなどで録音されている可能性も常に念頭におくべきです。冷静さを欠いた言動は、会社にとって不利な証拠となりえます。 - 十分な証拠なしに手続きを進める
「あの従業員がやったに違いない」という確信や状況証拠だけでは、法的に有効な解雇はできません。懲戒解雇を行うには、その原因となった不正行為や規律違反を客観的に証明する証拠が不可欠です。- 不正行為の例: 経費の不正請求書、横領を裏付ける会計記録、防犯カメラの映像
- 勤務態度の例: タイムカード、注意指導を行った記録(メールや書面)
証拠が不十分なまま手続きを進めると、たとえ事実であったとしても、裁判では「証拠がない」ことを理由に不当解雇と判断されてしまいます。
- 退職届の提出を強要する
穏便に済ませたいと考えるあまり、従業員に対して執拗に退職を迫ったり、「退職届を出さないと懲戒解雇にする」などと脅迫的な言動で退職届の提出を強要したりすることは、違法な「退職強要」にあたります。たとえその場で退職届に署名・捺印させたとしても、後から「強要されて書いたものだ」と主張されれば、その退職届は無効と判断される可能性が高いです。
懲戒解雇と退職勧奨、どちらを選ぶべきか?違いと判断基準を弁護士が解説
従業員に会社を辞めてもらうための手続きには、大きく「懲戒解雇」と「退職勧奨」の2つがあります。両者は性質が全く異なるため、状況に応じて適切に使い分ける必要があります。
懲戒解雇とは?企業の最も重い罰則
懲戒解雇とは、従業員が企業の秩序を著しく乱す重大な規律違反や不正行為を行った場合に、会社が一方的に労働契約を終了させる「罰則」です。懲戒処分の中では最も重い処分であり、いわば「企業の死刑宣告」ともいえます。そのため、法的に有効と認められるためのハードルは非常に高く、慎重な手続きが求められます。
退職勧奨とは?あくまで合意を目指す話し合い
退職勧奨とは、会社が従業員に対して「会社を辞めてもらえないか」と退職を促し、従業員との合意によって労働契約を終了させる方法です。あくまで「お願い」であり、従業員には退職勧奨を拒否する自由があります。
懲戒解雇とは異なり、双方の合意に基づいて退職を目指すため、紛争化するリスクを比較的低く抑えられるのが特徴です。
【比較表】懲戒解雇と退職勧奨の違い
| 比較項目 | 懲戒解雇 | 退職勧奨 |
|---|---|---|
| 性質 | ||
| 従業員の同意 | 不要 | 必須 |
| 法的リスク | 非常に高い(不当解雇訴訟) | 比較的低い(ただし退職強要に注意) |
| 解決スピード | 遅い(裁判に発展する可能性) | 早い(合意すれば即解決) |
| 退職金 | 不支給とできる場合がある(要規定) | 通常通り、または上乗せして支給 |
懲戒解雇が適しているケース
- 業務上横領や重大なハラスメントなど、極めて悪質な不正行為があった
- 会社の秩序を著しく乱している
- 客観的で明白な証拠が揃っている
退職勧奨が適しているケース
- 能力不足や勤務態度不良など、解雇理由としては弱いが改善も見込めない
- 協調性がなく、他の従業員とのトラブルが絶えない
- 紛争を避け、できるだけ円満に解決したい
判断に迷ったら「退職勧奨」から検討するのが原則
どちらの手段をとるべきか判断に迷う場合は、まずリスクの低い「退職勧奨」から検討するのが賢明です。退職勧奨で従業員の合意が得られなかった場合に、次の手段として普通解雇や懲戒解雇が可能かどうかを弁護士と相談しながら進めていくのが、安全な手順といえるでしょう。
【懲戒解雇】法的に有効と認められる3つの要件と具体的な進め方
懲戒解雇が法的に有効と認められるには、労働契約法第15条の趣旨に照らし、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
労働契約法 第15条
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
要件1:懲戒解雇の根拠が就業規則に明記されているか
大前提として、どのような場合に懲戒解雇となるのか、その理由(懲戒事由)と内容が就業規則に具体的に記載され、その就業規則が従業員に周知されている必要があります。懲戒解雇の理由は、必ず就業規則に明記されていなければなりません。就業規則にない行為を理由に懲戒解雇を行うことは、原則として無効です。
要件2:懲戒事由に「客観的に合理的な理由」があるか
就業規則に定められた懲戒事由に、従業員の行為が客観的に見て該当する必要があります。経営者の主観的な判断ではなく、誰が見ても「それは解雇されても仕方がない」と思えるだけの合理的な理由が求められます。
- 横領・業務上横領・重大なハラスメント: 会社の財産を盗んだり、立場を利用して取引先から不正な利益を得たりする行為。また、従業員の心身に重大な影響を及ぼす悪質なハラスメントも含まれます。
- 重要な経歴の詐称: 会社の採用判断に重大な影響を与えるような学歴や職歴、資格などを偽っていた場合です。
- 長期間の無断欠勤や悪質な業務命令違反: 正当な理由なく長期間無断で欠勤を続け、出勤の督促にも応じないケースなどが該当します。
要件3:処分内容が「社会通念上相当」であるか
問題となった行為の悪質性に対して、「懲戒解雇」という処分が重すぎないか、というバランスが問われます。例えば、一度の遅刻や軽微なミスでいきなり懲戒解雇にすることは、社会通念上相当とは認められず、無効となる可能性が極めて高いです。これまでに注意や指導を繰り返してきたか、他の従業員との処分の公平性は保たれているか、といった点も総合的に考慮されます。
懲戒解雇を断行するための4ステップ
- 客観的な証拠を確保する
何よりも先に、懲戒事由を裏付ける客観的な証拠を確保します。関係者へのヒアリング内容をまとめた陳述書、メールの履歴、業務記録、映像データなどを集め、紛失しないように保全してください。 - 弁明の機会を設ける
懲戒処分を下す前に、必ず対象となる従業員本人から言い分を聞く機会(弁明の機会)を設けなければなりません。一方的に処分を決定すると、手続きの妥当性が欠けていると判断されるリスクがあります。 - 妥当性を審議し、議事録を作成・保管する
就業規則に定めがある場合は、懲戒委員会などを開催し、処分の妥当性について慎重に審議します。議事録は必ず作成し、保管しておきましょう。 - 懲戒解雇通知書を交付する
最終的に懲戒解雇を決定したら、「懲戒解雇通知書」を作成し、従業員本人に交付します。通知書には、どの就業規則の条文に基づく処分なのか、解雇の理由を具体的に記載する必要があります。
【退職勧奨】円満解決に導くための5つのステップと「退職強要」にならないための注意点
退職勧奨は、あくまで従業員の自由な意思による退職を目指すものです。以下のステップに沿って、丁寧に進めることが円満解決の鍵となります。
- STEP1:事前準備(問題点の整理と証拠の収集)
なぜ退職を勧奨するのか、その理由を客観的な事実に基づいて整理します。能力不足であれば、具体的な業務上のミスや成績評価の記録。勤務態度であれば、注意指導の履歴などを準備します。 - STEP2:退職勧奨の実施(日時・場所・同席者の選定)
従業員のプライバシーに配慮し、他の従業員のいない静かな会議室などで面談を設定します。時間は30分~1時間程度を目安とし、長時間に及ばないようにしましょう。同席者は、経営者と直属の上司など、2名程度が望ましいです。 - STEP3:適切な「伝え方」と退職条件の提示
感情的にならず、準備した客観的な事実を基に、会社として期待するパフォーマンスに至っていないこと、改善が難しいと考えていることを冷静に伝えます。その上で、退職を考えてもらえないかと打診します。
「あなたの能力が低い」といった人格を否定するような表現は避け、「会社の求める水準と、あなたのスキルにミスマッチがある」など、客観的な表現を心がけます。。従業員が合意しやすくするために、退職金の増額や、有給休暇の買い取り、再就職支援などの優遇措置を提示することも有効な手段です。。 - STEP4:退職合意書の作成と締結
従業員が退職に同意したら、必ず「退職合意書」を作成し、双方で署名・捺印します。合意書には、退職日、退職理由(会社都合または自己都合)、退職金の金額、守秘義務などを明記し、後日のトラブルを防ぎます。 - STEP5:退職後の手続き
合意内容に基づき、離職票の発行や社会保険の手続きなどを速やかに行います。
【注意】このラインを超えたら「違法な退職強要」
以下の行為は、従業員の自由な意思決定を妨げる「退職強要」とみなされ、違法となる可能性が非常に高いです。
- 執拗な退職勧奨: 従業員が明確に拒否しているにもかかわらず、何度も面談を強要する。
- 名誉感情を害する言動: 「お前は会社のお荷物だ」など、侮辱的な言葉を浴びせる。
- 多数での取り囲み: 複数人で従業員を取り囲み、威圧的な雰囲気で退職を迫る。
【熊本での解決事例】弁護士への相談が企業を守る
当事務所で実際に取り扱った解決事例を2つご紹介します。
事例1:【在庫転売】証拠不十分から裁判手続きで逆転し、懲戒解雇の正当性が認められたケース
会社の在庫商品をフリマサイトで転売していた疑いのある従業員を懲戒解雇したところ、不当解雇であるとして訴訟を起こされた事案です。
相談当初は、転売を裏付ける決定的な証拠がありませんでした。しかし、弁護士が介入し、裁判上の手続きを利用してフリマサイトの出品者情報を調査した結果、当該従業員による転売の蓋然性が極めて高いことを立証。
最終的に、相手方(元従業員)が請求を放棄する形で、実質的に当社の主張が認められる形で解決しました。
ポイント:初期段階で証拠が不十分でも、弁護士による法的な手続きを通じて、解決の糸口が見つかる場合があります。
事例2:【試用期間中の問題社員】解雇無効を主張されたが、交渉により自己都合退職で解決したケース
試用期間中に入社直後から問題行動を繰り返す従業員を解雇したところ、代理人弁護士を通じて解雇無効と未払賃金の支払いを請求された事案です。
試用期間中の解雇は本採用後より広く認められますが、本件では裁判で争った場合に解雇が無効と判断されるリスクも否定できませんでした。
そこで、弁護士が代理人として交渉を行い、会社側の「従業員に戻ってきてほしくない」という最大の希望を叶えるため、解決金として要求された給与6ヶ月分から2ヶ月分に減額して支払うことを条件に「自己都合退職」としてもらう合意を取り付け、円満に解決しました。
ポイント:裁判で白黒つけることだけが解決策ではありません。交渉によって、リスクを抑えつつ、企業の希望に沿った現実的な解決を目指すことも重要です。
懲戒解雇・退職勧奨を熊本の弁護士に相談する3つのメリット
従業員との労務問題は、経営者様だけで抱え込まず、早い段階で弁護士にご相談いただくことで、より良い解決に繋がります。
メリット1:法的リスクを正確に診断し、最適な解決策を提示できる
ご相談いただいた内容に基づき、「そのケースで懲戒解雇は可能か」「退職勧奨を進めるべきか」といった法的なリスクを正確に診断します。そして、会社の状況やご希望に合わせた、最善の解決策をご提案します。
メリット2:経営者に代わり従業員と交渉し、精神的・時間的負担を大幅に軽減する
弁護士が会社の代理人として、従業員本人や相手方の弁護士との交渉窓口となります。これにより、経営者様が直接対峙することによる精神的なご負担や、交渉に割かれる貴重な時間を大幅に軽減できます。
メリット3:就業規則の見直しなど、将来の労務トラブルを防ぐ「予防法務」までサポートできる
今回の問題を解決するだけでなく、将来同様のトラブルが再発しないよう、就業規則の不備の見直しや、雇用契約書の整備といった「予防法務」の観点からもアドバイスが可能です。強い組織作りのパートナーとして、継続的にサポートいたします。
熊本で弁護士に相談する流れと費用の目安
相談から解決までのステップ
- お問い合わせ: まずはお電話またはウェブサイトのフォームからご予約ください。
- 初回相談: 弁護士が直接お会いし、詳しい状況をヒアリングします。
- 方針のご提案・お見積り: 最適な解決方針と弁護士費用についてご説明します。
- ご契約: ご納得いただけましたら、契約を締結します。
- 業務開始: 弁護士が代理人として、交渉や法的手続きに着手します。
費用感とオンライン対応
弁護士費用は、大きく分けて以下の3つで構成されます。
- 法律相談料: 弁護士に相談する際にかかる費用。
- 着手金: 弁護士に依頼する際に、最初にお支払いいただく費用。
- 報酬金: 事件が解決した際に、成功の度合いに応じてお支払いいただく費用。
具体的な費用は事案の複雑さによって異なりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
当事務所は、初回の法律相談を無料で承っております。熊本県内全域の企業様からのご相談に対応しており、Google MeetやZoomなどを利用したオンライン相談も積極的に活用しています。
また、顧問契約を締結いただくことによって、日頃の問題に対するアドバイスのみではなく長期的な体制構築のサポートが可能です。
懲戒解雇・退職勧奨に関するよくあるご質問
懲戒解雇の場合、退職金は支払わなくてよいのでしょうか?
退職金規程に「懲戒解雇の場合は退職金を支給しない、または減額する」という定めがあれば、不支給とすることも可能です。ただし、規程があっても、裁判所が「労働者のこれまでの功労を全て抹消するほど悪質ではない」と判断した場合は、一部の支払いを命じることがあります。自己判断で不支給とせず、弁護士にご相談ください。
退職勧奨を従業員に拒否されたら、どうすればよいですか?
退職勧奨は、あくまで従業員の合意があって成立するものです。従業員が明確に拒否の意思を示した場合は、それ以上勧奨を続けると「退職強要」とみなされる恐れがあるため、一度打ち切るべきです。その後の対応としては、配置転換や、客観的・合理的な理由があれば普通解雇を検討することになりますが、いずれも慎重な判断が必要です。
パワハラを理由に従業員を懲戒解雇することはできますか?
パワハラの事実が客観的な証拠(被害者や第三者の証言、メールなど)によって証明され、その行為が極めて悪質で、会社の秩序を著しく乱すものであると評価される場合には、懲戒解雇が有効となる可能性があります。しかし、パワハラの認定は非常に難しく、慎重な事実認定が求められるため、処分を決定する前に必ず弁護士にご相談ください。
熊本で従業員の問題にお悩みの経営者様へ。一人で決断する前に、まず弁護士にご相談ください
従業員の懲戒解雇や退職勧奨は、企業の将来を左右しかねない重大な経営判断です。正しい知識と手順で進めなければ、不当解雇として訴訟を起こされ、多額の金銭支払いを命じられるだけでなく、会社の評判にも傷がつくことになりかねません。
経営者様が一人で孤独な決断を下す前に、ぜひ一度、労働問題の専門家である弁護士にご相談ください。私たちは、熊本の経営者様の最も身近なパートナーとして、法的なリスクから会社を守り、問題を最善の形で解決するため、全力でサポートいたします。
監修者
弁護士法人グレイス企業法務部
- 本店所在地
- 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
- 連絡先
- [代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129 - WEBサイト
- https://www.kotegawa-law.com/
お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら
電話で問い合わせる
0120-77-9014
受付時間:平日9:00-17:30
メールで問い合わせる
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!
メールでのお問い合わせは24時間受付中!