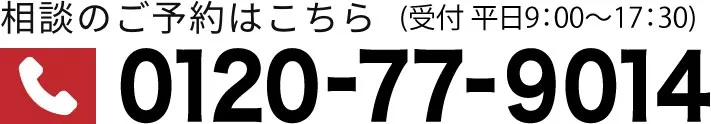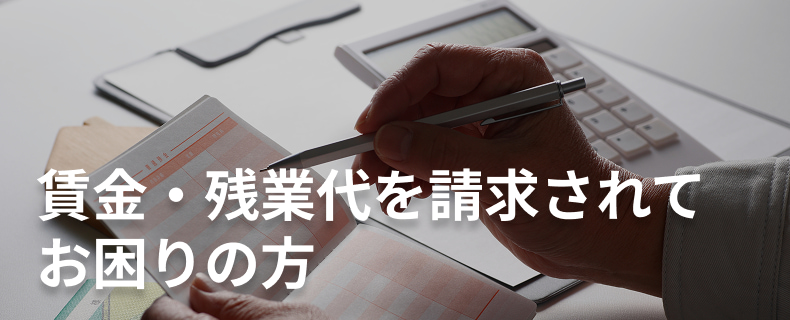企業法務コラム
団体交渉は拒否できる?よくある誤解と注意点を弁護士が解説
更新日:2025/11/25
東京・神戸・福岡・熊本・長崎・鹿児島を拠点に活動を行う弁護士法人グレイスです。
今回は、「団体交渉は拒否できる?よくある誤解と注意点」について解説いたします。
- この記事でわかること
-
- 会社が団体交渉を拒否できるケース
- 拒否できる正当な理由が認められる具体例
- 団体交渉を拒否した場合のリスク
- 団体交渉の対応を弁護士に相談するメリット
目次
団体交渉は会社側が拒否できるのか?
結論:基本的には拒否できません。
労働組合(ユニオン)から団体交渉の申入れがあった場合、会社は原則としてこれを拒否・無視することはできないと考えてください。団体交渉は労働組合の基本的権利であり、日本国憲法28条で保障された団体交渉権に基づくものです。

そのため、会社側には団体交渉に誠実に対応する義務(誠実交渉義務)が課されています。労働組合法7条2号でも「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なくて拒むこと」を禁止しており、正当な理由のない団交拒否は不当労働行為に該当します。
もっとも、「基本的に応じる義務がある」とはいえ、労働組合からのあらゆる要求をそのまま受け入れなければならないわけではありません。会社には団体交渉に応じて真摯に話し合う義務がありますが、後述するように正当な理由があれば団体交渉を拒否できる場合もあります。
団体交渉権とは?労働組合の基本的な権利
団体交渉権とは、労働者が労働条件や職場環境について使用者(会社)と集団で交渉する権利を指します。この団体交渉を行う権利は、労働者の団結権・団体行動権と並ぶ基本的な労働三権の一つとして憲法で保障されています。労働組合を結成した労働者たちは、団結して会社に対し賃金や労働時間その他の労働条件の改善を求めることができます。そして会社は、従業員が求める団体交渉のテーブルに着かなければなりません。会社側担当者が交渉の場に着席しないと、憲法上保障された団体交渉権が実現できないため、法律(労組法)によって会社の一方的な拒否が禁じられているのです。
使用者に課される「誠実交渉義務」とは
会社側には、労働組合から団体交渉を求められたときに誠実に交渉へ対応する義務があります。これを一般に「誠実交渉義務」といい、単に形式的に団体交渉の席に着くだけではなく、実質的にも真摯な姿勢で話し合いに臨む義務を意味します。
誠実交渉義務を果たすためには、組合側の主張をきちんと聞き、会社の考えも根拠を示して丁寧に説明し、可能な限りの提案や妥協点を模索する姿勢が重要です。形ばかりの対応や、先延ばし・一方的な打ち切りは厳禁です。「交渉するフリ」をして時間稼ぎをしたり、相手を萎縮させるような対応を取ったりすると、法律上の義務違反として後で大きな問題になりますので注意しましょう。
団体交渉を拒否すると不当労働行為になる?
**正当な理由なく団体交渉を拒否することは、不当労働行為に該当し違法となります。**先述のとおり労組法7条2号で禁止された行為であり、労働組合の団体交渉権を侵害するものだからです。労働組合側から見れば、話し合いを求めているのに会社が取り合わないのは権利の妨害に他なりません。そのため労働組合は、会社が団交拒否という不当労働行為を行ったとして、公的機関に救済を求めることができます。
具体的には、会社が正当な理由なく交渉を拒否した場合、労働組合は都道府県労働委員会などの労働委員会に対して「不当労働行為救済申立て」を行うことが可能です。労働委員会は会社と組合双方の主張や証拠を精査し、本当に不当労働行為があったかどうか審査します。その結果、会社に非があると判断されれば、労働委員会から会社に対し団体交渉に応じるよう救済命令が発出されます。この救済命令に会社が従わない場合、後述するような罰則(過料等)の対象ともなります。
また、不当労働行為は労働組合や労働者に対する民事上の不法行為にも該当し得ます。団交拒否によって組合が何らかの不利益を被った場合、組合は民法709条に基づき損害賠償請求を行うことも可能です。
このように、安易な団交拒否は法律違反となり得て、会社にとって大きなリスクとなるのです。
団体交渉を拒否することはできないのですね。
原則として拒否はできません。誠実に交渉に応じる法的義務があり、正当な理由がない限り拒否すると不当労働行為に該当します。
労働組合からの団体交渉を拒否したときの罰則・リスク
労働組合からの団体交渉申入れを正当な理由なく拒否した場合、会社側には様々なペナルティやリスクが生じます。ここでは、主な法的措置や不利益について確認します。

労働委員会からの救済命令・制裁措置
会社による不当な団交拒否があった場合、公的機関である労働委員会が介入します。労働組合から救済申立てを受けた労働委員会は、先述したように審査のうえ会社に団体交渉に応じるよう救済命令を発出します。この救済命令は法的拘束力を持つもので、会社は真摯に従わなければなりません。
もし会社が救済命令に背いて団体交渉に応じない場合、労働組合法に定める罰則が科される可能性があります。具体的には、確定した救済命令に違反した使用者には50万円以下の過料が科せられます(労組法第32条)。さらに、会社が不服として命令の取消訴訟を提起し最終的に命令が確定した後も従わないような場合には、**「1年以下の禁錮」または「100万円以下の罰金」(労組法第28条)**というより重い刑事罰の対象ともなり得ます。つまり、労働委員会の命令を無視し続ければ、最終的には刑事処分を受けるリスクさえあるのです。
行政指導・評判リスク・訴訟リスク
労働委員会による法的救済以外にも、団交拒否は様々な面で会社に悪影響を及ぼします。
まず、労働組合とのトラブルが表面化すれば、所轄の労働局や労基署などから行政指導を受ける可能性もあります。正式な救済申立てに至らずとも、労働組合が労働行政に相談すれば、行政担当者から「誠実に団交に応じてください」という注意喚起や助言が会社に入る場合があります。これ自体法的強制力はないものの、行政からマークされることで会社の信用に影響することも考えられます。
次に、社外的な評判リスクも無視できません。労働組合との交渉拒否がこじれると、「従業員の声を聞かない会社」「組合いじめをするブラック企業」といったレッテルを貼られ、企業イメージが損なわれる恐れもあります。特に外部ユニオンは他企業の事例も含め発信力を持つ場合があり、自社の顧客や取引先の耳にも入るリスクがあります。評判の低下は人材採用面や営業面にも影響しかねず、長期的な損失となり得ます。
さらに、先述の通り団交拒否は損害賠償訴訟に発展する可能性もあります。労働組合は不当労働行為として労働委員会に訴えるだけでなく、民事裁判で会社の違法行為による損害を問うことができます。裁判となれば弁護士費用や対応時間の負担が増えるだけでなく、判決によって賠償金支払いが命じられれば金銭的損失も被ります。
拒否を理由にトラブルが激化するケースも
団体交渉の申入れを拒絶することは、労使間の紛争を一層激化させる火種にもなります。労働組合としては、会社に無視・拒否されればされるほど反発心を強め、より強硬な手段に訴えてくる可能性が高いからです。
また、団交拒否という会社の姿勢自体が組合側の不信感を大きくし、「相手(会社)は敵対的だ」という認識を強めます。その結果、労使の溝が深まり問題がこじれてしまうケースが多いのです。
以上のような理由から、団体交渉は原則拒否すべきでないことがお分かりいただけたかと思います。しかし一方で、法律上「正当な理由」があれば団交を拒否できる場合も存在するのも事実です。
罰金や評判リスク、訴訟まであると知り驚きました。拒否は避けるべきですね。
はい、原則として団交には応じるべきです。拒否は不当労働行為となるので、リスクが大きいです。
団体交渉の申入れを拒否できる理由とは?
前提として、労働組合法は「正当な理由なく」団体交渉を拒むことを禁じています。裏を返せば、正当な理由がある場合には団体交渉を拒否できる可能性があります。もっとも、そのハードルは非常に高く、会社側に主張できる余地があるケースは限られています。ここでは判例や労働委員会命令の蓄積から、一般に会社側が拒否し得るとされる典型的な理由をいくつか紹介します。

なお、これから述べる状況に該当すれば必ず団交拒否が認められるというものではありません。あくまで「正当な理由」と評価される可能性がある事情に過ぎず、実際に拒否が適法と判断されるかは個別具体的な事情を総合考慮して決まります。その点を踏まえ、どのような場合に正当な理由が成り立ち得るか見ていきましょう。
会社側が拒否できる「正当な理由」とは
一般に会社が団体交渉を拒否し得る正当な理由としては、以下のような場合が挙げられます。
交渉事項が組合員の労働条件に関係しない場合
労働組合から要求された交渉議題が、組合員(従業員)の労働条件や労使関係と無関係の場合、会社はその団体交渉申入れを拒否できる可能性があります。法律上、会社に団交に応じる義務があるのは「労働者の労働条件その他待遇や労使関係の運営に関する事項で、会社(使用者)に決定権限があるもの」に限られると解釈されます。こうしたテーマは**「義務的団交事項」**と呼ばれ、賃金・労働時間・休日・安全衛生・人事異動・解雇など従業員の待遇に直接関わる事項が典型例です。
一方、それ以外の議題は「任意的団交事項」とされます。例えば、設備投資や生産方式・経営方針の決定、他社との業務提携や会社組織の変更など、経営そのものに関する事項が代表例です。これらは会社が広範な裁量権を持つ領域であり、直接に従業員の個々の待遇を変更するものではないため、法律上は団交に応じる義務までは課されないとされています。
ただし注意すべきは、一見経営事項に思えるテーマでも、それが従業員の雇用や労働条件に影響を及ぼす場合です。判断に迷う場合は専門家に相談すると良いでしょう。
交渉の態様が社会通念に照らして不相当な場合
労働組合側の交渉のやり方が常識的な範囲を逸脱し、社会通念上受け入れ難いような場合、会社は団体交渉に応じない正当な理由を主張できることがあります。具体的には、組合の交渉態度が過度に威圧的・暴力的で、冷静な話し合いができない場合です。
組合側に明らかな暴力・威嚇行為がある場合には、まず会社として毅然と抗議し謝罪と再発防止を求めるべきです。その上で「安全に話し合いができない状況では応じられない」として、一時交渉を中断したり、問題行為を行った人物の出席を拒むなどの対応も考えられます。会社が「暴力行為をした人物は交渉に出さないこと」を条件に交渉再開に応じるという姿勢を示すことも考えられるでしょう。
過去には以下のようなケースで「正当な理由あり」とされた例があります
- ・過度に多人数の組合員が交渉に押しかけ、使用者側交渉員を罵倒するなど正常な話し合いを期待できない場合
- ・肉体的限界を超える長時間の団交を組合が強要しようとする場合
- ・組合側が交渉参加者の人数に固執し過剰な大人数を要求したため、会社が適正人数を超える出席には応じないとした場合
以上のような場合、まずは会社として事態の改善を求め、それでも改善されないときに「正常な協議ができない以上、応じられない」と対応することになります。
団体交渉申入れの形式・方法に不備がある場合
労働組合からの団体交渉申入れ自体に形式上の不備がある場合も、会社が即座に交渉に応じなくても許されることがあります。考えられるケースとしては次のようなものです。
申入書の内容や手続に問題がある場合
通常、団交申入れは書面で行われ、交渉事項や希望日時、組合側出席者などが記載されます。これらが全く明らかにされていない場合、会社は「内容が不明確なため対応しかねる」として調整を保留することが考えられます。
労働組合側に交渉当事者能力がない場合
団交の相手方はあくまで法的な労働組合ですので、労働組合法上の「労働組合」に該当しない団体(例えば単なる親睦団体や任意の従業員グループ)から交渉を求められた場合、会社はそれを拒否できます。
交渉方法・条件に無理がある場合
組合から提示された交渉日時や場所、人選などが、会社にとって著しく受け入れ困難な場合も考慮すべき点です。組合が会社に無断で第三者(関連団体や支援者等)を交渉に同席させようとしたり、交渉の場として会社に不利益を及ぼしかねない場所(公開の場など)を一方的に指定してきた場合も、会社は合理的な範囲で修正を求めることができます。
以上のように、「交渉に応じないこと自体」に正当理由があるというより、「適切な形での交渉申入れが行われていないので一旦拒んだ」というイメージです。申入れ内容の確認や調整は決して不誠実対応ではなく、正当な理由になり得ることを覚えておいてください。
ユニオン・合同労組からの申入れへの対応ポイント
近年では、会社内に労組がなくても従業員が社外のユニオン(合同労組)に加入して団体交渉を求めてくるケースが増えています。ここでは、ユニオンからの団交申入れに会社がどう対応すべきかポイントを解説します。
まず大前提として、ユニオンであっても一人でも貴社従業員が組合員として在籍していれば、労組法上の「労働者の代表者」にあたります。したがって、社外の合同労組だからといって交渉を拒否することはできません。自社の従業員が加入している以上、その組合は貴社に対して団交権を有します。「うちは社内労組しか認めない」という態度をとれば、正当な理由のない団交拒否として違法となりますので注意してください。
次に、ユニオンから申入れがあった場合の具体的な初動対応です。多くの場合、団交申入れは書面(郵送やFAX)で届きます。これを決して無視してはいけません。申入書には要求事項や希望日時が書かれているのが一般的ですので、まずは内容をよく読み、会社として窓口担当者(通常は人事部長や労務責任者)を決めて対応しましょう。申入れを受け取ったら、できるだけ早めに組合宛に回答することが大切です。回答といっても、要求に即答する必要はありません。「団体交渉の日程調整を行いたい」「御社のご要望について社内検討の上、追って回答します」など、まずは受領連絡と今後の対応方針(検討・調整中である旨)を伝えるようにします。
ユニオンとの団交では、交渉の場に組合の専従スタッフや弁護士が同席してくることも多いです。相手は労使交渉のプロですから、会社側も可能であれば労務に強い弁護士や社会保険労務士にサポートを依頼した方が安心です。自社だけで対応する場合でも、事前準備を入念に行いましょう。想定される要求内容について自社の見解やデータを整理し、対応可能な譲歩ラインと絶対譲れないラインを明確にしておきます。初回交渉では相手の主張をしっかり聞きつつ、自社の事情も冷静に説明するよう努めます。
また、ユニオンは複数企業の案件を抱えており、要求や交渉スタイルにも一定のパターンがあります。過去の類似ケースを調べたり、専門家から情報を得たりして、ユニオン側の出方を想定しておくことも有益です。場合によっては、労働委員会のあっせん制度など第三者の力を借りて解決を図る選択肢もあります。いずれにせよ、「外部の組合だからうちは関係ない」と放置するのは最悪の対応です。社外ユニオンであっても、誠実交渉義務は社内組合と変わりません。適切に向き合えば円満に解決する問題も多いので、冷静かつ丁寧な対応を心がけてください。
態度が威圧的だったり内容が労働条件と無関係な場合は断れるのですね。
はい、そのような場合は「正当な理由」として拒否できる可能性がありますが、判断は慎重に。証拠確保と専門家の助言が重要です。
団体交渉の拒否に関するよくある誤解と注意点
最後に、企業の人事担当者や経営者が陥りがちな団体交渉拒否に関する誤解と、その注意点について整理します。「うっかり誤った対応をして不当労働行為に問われてしまった」という事態を避けるためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。
組合の主張をすべて受け入れる必要はない
「団体交渉に応じたら、組合の要求通りに全部飲まないといけないのでは?」と心配される方もいます。しかし、決してそんなことはありません。団体交渉とはあくまで「労使が誠実に話し合うプロセス」であって、その結果として合意に至るかどうかは双方の努力次第です。会社には交渉の席につく義務はありますが、提示された要求を100%受諾する義務まではないのです。
実際、団交の場では会社側が組合の要望に反対意見を述べたり、一部のみ受け入れて他は断ったりすることも当然あります。重要なのは、きちんと理由を説明しつつ検討・協議した結果として結論を出すことです。誠実に交渉を重ねた結果、会社としてどうしても譲れない点については「それには応じられない」と最終的に回答すること自体は法的に問題ありません。また、組合から指定された日程が都合悪ければ代替日程を提案するなど、相手の要求に一定の調整を求めることも許容されています。
要は、団交において会社側も自社の方針や事情をしっかり主張し、合意可能なラインを模索すれば良いのです。「交渉=譲歩の場」と身構えすぎる必要はありません。もちろん最初から全部突っぱねるのでは交渉になりませんが、かといって要求を鵜呑みにしてしまうと会社経営に支障が出ることもあります。法は話し合いの場を保障するものの、最終的な合意内容までは強制しません。たとえ交渉が決裂して組合要求を一部しか認めなかったとしても、それまでに誠意ある協議を尽くしていれば不当労働行為には当たりません。
したがって、「要求をのまないと違法になるのでは」と萎縮する必要はありません。重要なのはプロセス(過程)です。会社の判断に正当な根拠があり、その説明責任を果たしていれば、結果として組合の希望通りでなくても構わないのです。交渉のゴールは双方が納得できる落とし所を探ることであり、決して会社が一方的に譲歩し続けることではない点を誤解しないようにしましょう。
拒否と交渉打ち切りは別問題
「一度団体交渉に応じたから、もう途中で打ち切るのはダメなのか?」という疑問もよくあります。ここで「拒否」と「交渉の打ち切り」を区別して考える必要があります。法律上問題となる「団交拒否」は、最初から話し合いに応じなかったり、正当な理由なく交渉の場から一方的に逃げ出したりする行為を指します。それに対し「交渉打ち切り」とは、ある程度話し合いを重ねた後で「これ以上交渉を続けても進展が見込めない」として協議を終了することを指します。
交渉打ち切りが許されるかどうかは、それまでに誠実な交渉を尽くしたかがポイントです。例えば数回にわたり真剣に協議を行い、お互いに主張・提案を出し尽くしたものの意見が平行線のまま……という状況であれば、会社が「残念ながらこれ以上交渉しても結論は変わらないでしょう」と打ち切りを宣言することは許容され得ます。
ただし注意すべきは、打ち切りのタイミングです。例えば最初の一回目の交渉から会社が強硬な姿勢で「当社の立場は不変です。これで終わりです」と短時間で切り上げてしまった場合、組合から「不誠実だ」と非難されるでしょう。交渉回数や時間があまりに不足していれば、「事実上の拒否」とみなされ不当労働行為になるリスクがあります。
また、一度交渉を打ち切っても、状況が変われば組合から再度交渉申入れが来ることもあります。その際は改めて応じる義務が生じる可能性もあります。打ち切ったからといって未来永劫拒否できるわけではない点も認識しておきましょう。
交渉へ対応すれば打ち切りも可能なんですね。
はい、誠実な交渉を尽くせば一部拒否や打ち切りも可能です。ただしタイミングと説明が重要です。
団体交渉の対応でお困りなら弁護士に相談を
団体交渉の申し入れ対応は、法的知識と実務経験が求められる難しい分野です。もし貴社で対応にお困りの場合は、早めに労働問題に詳しい弁護士に相談することを強くお勧めします。

交渉拒否の判断は法的知見が不可欠
団体交渉を「正当な理由」で拒否できるかどうかの判断は、非常に専門的です。労働法の条文だけでなく、過去の判例や労働委員会の判断例を踏まえて総合的に考える必要があります。例えば、先述したように何が「正当な理由」に当たるかはケースバイケースで微妙なことも多く、法律の素人判断で「これは正当な理由になるだろう」と踏んで拒否したら実は不当労働行為だった…というリスクがあります。
弁護士に相談すれば、最新の判例動向や労働委員会の運用を踏まえて適法・違法のボーダーラインを教えてもらえます。例えば「この程度交渉したら打ち切っても大丈夫か」「組合のこの要求にはどこまで応じる義務があるのか」といった判断は、経験豊富な弁護士の助言なしに進めるのは危険です。交渉拒否が適法かどうかは会社単独ではなかなか判断がつきませんから、法的知見を持つ専門家のサポートが不可欠と言えるでしょう。
また、弁護士であれば労働組合法や労働関係調整法など関連法規を踏まえた戦略的なアドバイスも可能です。下手に拒否するくらいなら初めから応じて穏便に解決した方が良い場合や、逆に強い姿勢を見せるべき場合など、状況に応じた適切な対応策を提案してもらえます。「どのラインまで妥協すべきか」「どの主張は通せるか」といった交渉上の駆け引きも含め、法的な裏付けのある判断を示してくれるでしょう。
初動対応の誤りが後のトラブルを招く
団体交渉問題では最初の対応が極めて重要です。初動で間違った対応をすると、その後の展開が不利になったり、トラブルが拡大してしまうことが多々あります。例えば、申入れを受け取った際に感情的になって「うちには関係ない!」と突っぱねる返信をしてしまったり、何も返答せず放置してしまったりすると、後からいくら軌道修正しようとしても組合との信頼関係は損なわれたままになります。最悪の場合、その初動の一言・一手が不当労働行為の証拠として残ってしまうこともあります。
また、「とりあえず一度適当に話し合ってお茶を濁そう」と安易に考えて臨んだ結果、組合側をさらに怒らせてしまったり、逆に会社側の主張が曖昧で弱みを握られたりするケースもあります。初回交渉での会社発言は議事録に残り、後の法的争いで引用される可能性もあります。初動対応を誤ると、紛争が長期化・泥沼化しやすいのです。
そこで、弁護士に相談して適切な初動対応を取ることが肝心です。弁護士であれば、受領通知の文面ひとつ取っても法に触れず角が立たない表現を考えてくれますし、交渉の場に臨む前の準備も万全にサポートしてくれます。最初の一歩を間違えないことが、後々のトラブル防止につながるのは言うまでもありません。不安な場合は、ぜひ交渉が始まる前に専門家のチェックを受けてください。
実績ある弁護士による対応で企業リスクを軽減
団体交渉への対応に長けた弁護士に依頼すれば、会社のリスクを大幅に軽減できます。まず、弁護士がいれば交渉の場で法的にNGな発言や対応をする心配が減ります。先方の主張に対してどこまで回答すべきか、その場で判断に迷うような点も、弁護士がいれば適宜耳打ちや代理発言でフォローしてくれるでしょう。会社単独ではつい感情的になってしまう局面でも、冷静に法的観点から対処できます。
また、弁護士が代理人として交渉に同席すれば、組合側も不用意な違法要求は控えるものです。お互い専門家が入ることで、交渉がより建設的かつスムーズに進む効果も期待できます。仮に交渉が決裂して労働委員会や裁判に発展した場合でも、最初から関与している弁護士であれば事情を把握していますから迅速に対応できます。証拠書類の整備や主張の組み立ても一貫して任せられ、会社側の防御体制が盤石になります。
さらに、弁護士は第三者の視点から状況を判断してくれます。経営者や人事担当者はどうしても社内事情に引きずられがちですが、弁護士は客観的に「ここは譲歩すべき」「ここは主張すべき」といったメリハリをつけてくれます。それにより、無用な争点で争ったり、逆に譲れない点をうっかり譲ってしまったりするリスクも減らせます。
最後に何より、団体交渉問題で悩み続ける精神的負担が大きく軽減されます。プロに任せることで経営者・人事担当者は本来の業務に専念できますし、安心感も違います。「備えあれば憂いなし」です。団体交渉の対応に不安があるときは、一人で抱え込まずにぜひ経験豊富な弁護士にご相談ください。専門家の力を借りて適切に対処すれば、企業としてのリスクを最小限に抑えつつ円満な問題解決を図ることができるでしょう。
監修者
弁護士法人グレイス企業法務部
- 本店所在地
- 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
- 連絡先
- [代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129 - WEBサイト
- https://www.kotegawa-law.com/
「労働組合対応」の関連記事はこちら
お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら
電話で問い合わせる
0120-77-9014
受付時間:平日9:00-17:30
メールで問い合わせる
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!
メールでのお問い合わせは24時間受付中!