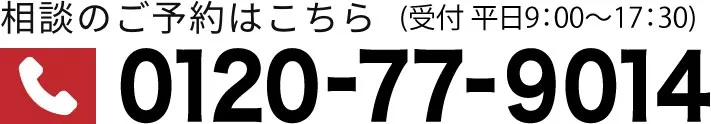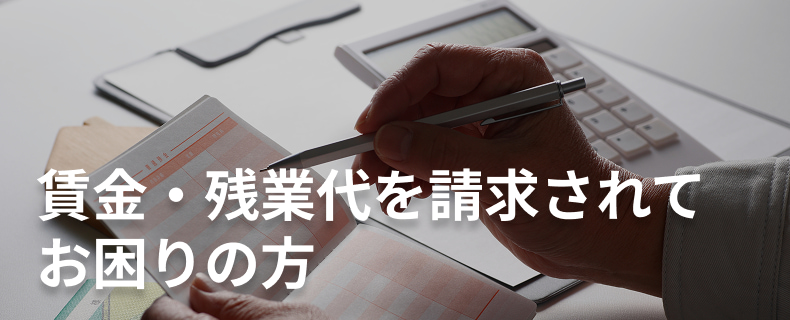企業法務コラム
人材派遣業でよくあるトラブルとは?トラブルが起きた時の対応と事前にできる対策を弁護士が解説
更新日:2025/12/23
人材派遣業は、労務トラブルの宝庫です。
人材派遣業におけるトラブルは多岐にわたりますが、特に多いのは派遣可能期間の超過、不当解雇・契約終了、契約と異なる業務内容、ハラスメント、労働条件通知書作成・就業条件明示義務の未対応です。
これらのトラブルは、派遣社員、派遣元、派遣先の三者関係に起因することが多く、それぞれが異なる立場や利害を持っているために発生しやすいと言えます。このため、実際にトラブルが発生した場合には、三者間で揉めることとなってしまいます。
この記事では、このような複雑なトラブルが起きた時の対応方法と、事前対策についてご説明します。
目次
人材派遣業でトラブルが起きやすい理由
それでは、なぜ人材派遣業でトラブルが起こりやすいのでしょうか?
人材派遣業では、派遣元企業が雇用主として派遣社員と労働契約を結び、派遣社員は派遣先の指揮命令のもとで業務を行います。この複雑な三者関係が以下のように、トラブルの温床となる要因を生むことがあります。
①三者の利害関係の不一致
派遣社員は安定した雇用と適切な労働条件を求め、派遣先は必要な人材を必要な期間だけ確保したいと考え、派遣元は事業の継続性を確保しつつ、派遣社員と派遣先の双方に配慮する必要があります。
自分勝手といえばそうですが、どうしてもこういった利害関係は生じてしまいます。これらの利害が必ずしも一致しないため、問題が発生しやすくなります。
②契約内容の不明確さ
また、人材派遣においては、契約書がちゃんと作成されていないことが多いです。具体的な業務内容や責任範囲、労働条件などが曖昧なまま契約が進むと、後になって認識のずれが生じ、トラブルに発展するケースが生じてしまいます。
③法令遵守の難しさ
労働者派遣法をはじめとする関連法規は複雑であり、頻繁に改正されるため、すべての企業が完璧に遵守することは容易ではありません。特に中小企業では、専門知識が不足しているために意図せず法令違反を犯してしまうこともあります。
④コミュニケーション不足
派遣社員、派遣元、派遣先の間のコミュニケーションが不足していると、問題が発生しても早期に発見・解決ができず、事態が悪化する可能性があります。普段のコミュニケーションができていれば、大きな問題になる前に相談等をもらい、紛争の芽を摘めるはずなのです。
人材派遣業でよくあるトラブルとは?
人材派遣業では、以下のようなトラブルが労務トラブルとして起こりがちです。
派遣可能期間の超過
労働者派遣法では、同一の派遣社員を同一の組織単位で派遣できる期間には制限があります(原則3年)。この期間を超えて派遣を継続した場合、違法派遣となります。
不当解雇・契約終了
派遣期間中の解雇や契約終了は、労働契約法や労働者派遣法に則って慎重に行う必要があります。派遣先の都合による一方的な契約終了や、合理的な理由のない解雇は、不当解雇として争われる可能性がありますから注意しなければなりません。
業務内容が契約と異なる
派遣契約で定められた業務内容と、実際に派遣社員が行う業務内容が異なる場合、トラブルになります。これにより、派遣社員のモチベーション低下や、ミスマッチによる業務効率の低下を招くこともあります。
ハラスメント(パワハラ・セクハラ)
派遣先での各種ハラスメントは、派遣社員の心身の健康を損なうだけでなく、派遣元・派遣先双方の企業イメージを著しく損ないます。ハラスメントがあった場合、派遣先は適切な対応を取る義務がありますが、問題化してから対応をとっても、後の祭りになってしまうのです。
就業条件明示義務の未対応(2020年の派遣法改正)
2020年の労働者派遣法改正により、派遣元から派遣労働者への待遇等の説明義務が強化されました。これらの説明が適切になされていない場合、後から派遣労働者の不満を招きやすくなります。
派遣先でトラブルが起きた場合の対応
それでは、派遣先で労務トラブルが発生した場合には、どうしたら良いのでしょうか?まずは、以下のような対応をとることをお勧めします。
事実確認と証拠の確保
トラブル発生時は、まず冷静に状況を把握し、事実関係を確認することが最重要です。関係者からの聞き取りや、メール、チャット履歴、業務日報など、客観的な証拠を可能な限り集めましょう。その上で、各種関係者や労働者から話を聞いて録音するなどすると良いです。
証拠は、後の交渉や、訴訟等の法的手続において非常に重要になります。派遣労働者から訴えられる事態まで想定して準備しなければなりません。
契約書・労働条件通知書の確認
トラブルの内容が契約条項や労働条件に関わるものであれば、派遣契約書や労働条件通知書の内容を改めて確認しましょう。何が約束され、何が守られていないのかを明確にすることで、今後の対応方針を定める上で不可欠な情報を得られます。
また、契約書等の各種書面を確認することで、企業に有利な条項を再発見することができる場合もあります。
弁護士へ相談
トラブルの内容が複雑であったり、法的な問題が絡んだりする場合はもちろんのこと、トラブル発生後、早急に弁護士に相談することを強くお勧めします。
弁護士は、法的な観点から状況・証拠を整理し、適切な対応策や交渉方法についてアドバイスすることができます。特に労働者派遣法を含む労務トラブルへの対応に詳しい弁護士を選ぶとよいでしょう。
ちなみに、万が一派遣労働者から訴訟などを提起されてしまった場合には、派遣労働者側が収集した証拠が裁判に提出されます。企業経営者の不用意な発言が録音されて証拠になることも稀ではありません。不利益なことを認めたり話したりする前に、弁護士にご相談ください。
派遣先とのトラブルを未然に防ぐ対策
また、派遣先とのトラブルを未然に防ぐために、以下のような対策をとることもお勧めです。これらの対策を講じることで、人材派遣業におけるトラブルのリスクを大幅に軽減し、健全な事業運営につなげることができます。いずれも、弁護士による支援を得ながら行うことで、充分に対策として機能するでしょう。
契約書類の整備と法令遵守
派遣契約書や労働条件通知書などの書面が、トラブルを未然に防ぐための最も重要なツールです。業務内容、指揮命令者、労働時間、賃金、休日、契約期間、解雇事由、懲戒事由などを明確に記載し、双方が納得した上で締結することが重要です。
また、労働者派遣法をはじめとする関連法令を常に把握し、法令遵守を徹底することが必要です。このためには、法律専門家である弁護士と顧問契約を締結し、平時からの情報収集に努めることが必要です。
労働時間と給与管理の徹底
また、派遣労働者の労働時間は正確に把握し、サービス残業などが発生しないよう、勤怠管理システムを導入するなどの対策が必要です。当然ながら、タイムカード・勤怠管理システム上の記録などの客観証拠は、のちに企業を守るためには必須です。
また、給与計算も適切に行い、給与明細を正確に交付することで、金銭トラブルを未然に防ぎましょう。勤怠管理・給与計算については、社会保険労務士への依頼も検討するべきです。
ハラスメント・苦情対応窓口の設置
更に、ハラスメントやその他の苦情について、相談しやすい窓口を設置し、迅速かつ適切に対応する体制を整えることが重要です。
昨今は、いわゆるハラスメントに対して厳しい取扱いがされるようになってきました。企業のレピュテーションリスクにも繋がります。
相談窓口は複数設け、匿名での相談も可能にするなど、派遣労働者が安心して相談できる環境を整備しましょう。もちろん、公益通報者保護法などを参考に、相談者を守る体制を構築する・相談者への不利益がないように注意するといったことも必要となります。また、相談があった場合には、秘密厳守で対応し、再発防止策を講じることも不可欠です。
まとめ
以上のとおり、人材派遣業でよくあるトラブルと、これに対する対応・予防策を解説しました。人材派遣業ではどうしてもこれらのトラブルが起こりやすいので、ぜひ弁護士にご相談いただき、顧問弁護士のご依頼をご検討ください。平時から契約書等の整備や、法令遵守をする体制構築のために法務相談をすることで、上記トラブルが劇的に減少するでしょう。
当事務所では、多くの企業顧問を抱えておりますので、人材派遣業のトラブル対応・トラブル予防も熟知しています。ぜひ、当事務所にご相談いただき、我々を顧問弁護士として選んでいただけますと幸いです。
監修者
弁護士法人グレイス企業法務部
- 本店所在地
- 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
- 連絡先
- [代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129 - WEBサイト
- https://www.kotegawa-law.com/
「クレーム対応」の関連記事はこちら
お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら
電話で問い合わせる
0120-77-9014
受付時間:平日9:00-17:30
メールで問い合わせる
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!
メールでのお問い合わせは24時間受付中!