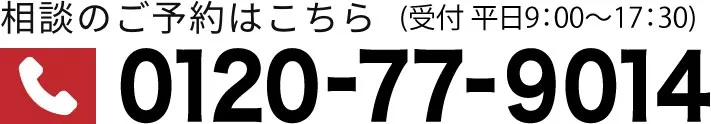企業法務コラム
問題社員の諭旨解雇を検討中の方へ|手続きやよくあるトラブルを弁護士が解説
更新日:2025/11/26
問題社員への対応は、企業の経営者や人事担当者にとって、非常に繊細かつ重要な課題です。中でも「諭旨解雇」(ゆしかいこ)は、懲戒処分の一種でありながら、その性質上、通常の解雇とは異なる手続や法的リスクが伴いますので注意が必要です。
この記事では、諭旨解雇のメリットや特徴と、諭旨解雇から発生しうるトラブルとそれに伴う法的リスクについて、解説していきます。これらのリスクを回避し、円滑に諭旨解雇を進めるために、弁護士をどのように活用すべきかについても詳しくご紹介しますので、問題社員への対応で悩んでいらっしゃる方は、ぜひ参考にしてください。
目次
諭旨解雇を選ぶメリット
諭旨解雇には、企業が一方的に雇用契約を終了させる「懲戒解雇」と比較して、以下のようなメリットがあります。問題社員に対する適切な処分を選択する上では、これらのメリットを理解することが必要となります。
大きなトラブルを回避できる
諭旨解雇の最大のメリットは、解雇を巡る大きな法的トラブルへの発展を回避できる可能性が高い点にあります。通常の懲戒解雇ですと、会社が一方的に社員を解雇することになり、かつ、退職金を支払わないことが多いです。このため、社員が解雇の有効性を争い、労働審判や訴訟に発展するケースが少なくありません。これらの手続は、企業にとって時間、費用、労力の大きな負担となるだけでなく、企業のブランドイメージにも悪影響を及ぼす可能性があります。
一方、諭旨解雇では、社員に退職を促し、社員の同意を得て雇用契約を終了させる形態を取ります。社員が自らの意思で退職に同意することで、解雇の有効性を後から争われるリスクを大幅に低減することができます。これは、企業が予期せぬ法的紛争に巻き込まれることを避ける上で非常に有効な手段といえるでしょう。
就業規則に基づく正当な懲戒処分として記録できる
また、諭旨解雇は、一般的に企業の就業規則に定められた懲戒処分の一つです。このため、社員の問題行為に対して、就業規則に基づき正式な懲戒処分として記録を残せることは、企業の秩序維持にとって重要です。曖昧に自主退職を促すことと比較して、他の社員にも、示しが付くでしょう。
将来的に同様の問題が発生した場合、過去の諭旨解雇の事例が、その後の対応の根拠となり得ます。企業として、問題行為に対して毅然とした態度で臨む姿勢を示すことで、他の社員への抑止力としても機能します。これにより、社内の規律が保たれ、健全な職場環境の維持を図ることができます。
社員の同意を得た「合意退職」に近い形を取れる
諭旨解雇は、社員に退職を勧告し、最終的に社員の同意を得るという点で、「合意退職」に近い性質を持ちます。これは、特に社員のその後の人生、特に転職活動への影響を考慮する上で重要な意味を持ちます。
懲戒解雇の場合、その事実自体が次の就職活動に大きな負の影響を与えることがあります。しかし、諭旨解雇であれば、退職理由を「自己都合退職」に近い形で処理することも可能です。社員が納得して退職に同意することで、不必要な摩擦を避け、比較的円満な形で関係を解消できる可能性があります。社員の心情に配慮しつつ、会社の目的を達成できるという点で、企業にとって柔軟な選択肢となるでしょう。
諭旨解雇とは?
ここで、諭旨解雇の内容自体についてもご説明いたします。
諭旨解雇の定義
諭旨解雇とは、会社が社員に対して、懲戒解雇に相当するほどの重大な問題行為があったにもかかわらず、社員に反省の態度が見られる場合や、情状酌量の余地がある場合に、自主的な退職を促し、社員の同意を得て雇用契約を終了させる懲戒処分の一種です。通常、社員がこの勧告に応じない場合は、懲戒解雇に切り替えて対応することになります。
諭旨解雇は、会社が一方的に雇用契約を打ち切る「懲戒解雇」と、社員が自らの意思で退職する「自己都合退職」の中間的な位置づけにあるといえるでしょう。このため、会社としては、懲戒解雇の有効性を争われるリスクを避けつつ、問題社員を会社から排除したい場合に選択されることが多い処分です。
懲戒解雇・普通解雇との違い
ちなみに、解雇には、大きく分けて「懲戒解雇」「諭旨解雇」「普通解雇」の種類があります。
懲戒解雇は、上記のとおり、会社が一気に雇用関係を終了させるとともに、通常は退職金も支払わないという対応を取ることとなります。また、離職票等に退職理由が懲戒解雇などと書かれることとなりますので、再就職が非常にしにくくなります。
他方で、普通解雇は、懲戒処分ではなく、社員の能力不足、勤務態度不良などを理由に解雇する手続となります。退職金の給付はありますし、場合によっては解雇予告手当の給付もありますが、会社からの一方的な通知によって雇用契約が終了することは懲戒解雇と同じです。
諭旨退職は、懲戒処分ではあるものの、これらの解雇と比較して、対象者自身の意思による退職を促す点に特徴があります。
どのようなケースで使われるのか
諭旨解雇は、懲戒解雇に値するほどの問題行為があったものの、社員が反省の態度を示している場合や、会社と社員の間で円満な解決を望む場合に選択されることがあります。例えば、会社の秩序を乱す行為があったが、再犯の可能性が低いと判断されるケースなどが挙げられます。
諭旨解雇の手続
ここで、諭旨解雇に必要な手続をご説明します。
就業規則の整備が必要
諭旨解雇を行うためには、そもそも、会社の就業規則に諭旨解雇に関する規定(諭旨退職の対象となる事由と、会社が諭旨退職できること)が明確に定められている必要があります。どのような行為が諭旨解雇の対象となるのか、手続の流れなども明記しておくことが重要です。
本人への事前説明・弁明の機会
諭旨解雇を検討する際は、処分を行う前に、対象社員に対して事前に問題行為の内容を具体的に説明し、弁明の機会を与える必要があります。社員の言い分を十分に聞き、公平な判断を下すことがトラブル防止に繋がります。
この手続なしでいきなり諭旨解雇処分を下すと、のちに諭旨解雇が無効となるおそれがありますので、ご注意ください。
退職届の取得と記録の残し方
諭旨解雇では、社員から退職届を提出してもらうのが一般的です。退職届には、諭旨解雇の勧告を受けて合意の上で退職すること、退職理由などを、対象社員の手で明記してもらいましょう。
また、話し合いの経緯や合意内容を記録に残しておくことも重要です。弁明の機会を付与した場合の会社側への弁明内容を録音しておくなど、直接的な記録を残すことも有益です。
諭旨解雇のよくあるトラブルと法的リスク
上記のとおり、諭旨解雇はトラブルを回避しやすい側面もありますが、適切な手続を踏まないと予期せぬ問題に発展する可能性がありますので、油断はできません。
諭旨解雇なのに「自主退職ではない」と争われるケース
例えば、諭旨解雇なのに「自主退職ではない」と争われるケースがあります。社員が退職に同意したにもかかわらず、後になって「会社から強制されたもので、自主退職ではない」と主張し、退職の無効を争うケースになります。
手続に不備があった場合や、そもそも社員への説明不足などがあった場合に、これらが原因で起こりやすいトラブルとなります。このようなケースでは、諭旨解雇が無効となることのないよう注意が必要です。
無効主張された場合の企業リスク
また、社員から諭旨解雇の無効を主張された場合には、会社側が、解雇が有効であることを証明する必要があります。万が一裁判等で解雇が無効と判断されれば、解雇期間中の賃金の支払や、職場復帰を命じられる可能性がありますから、そのリスクは甚大です。
少しでもリスクを軽減できるように、適切な手続を履践したことの証拠を残しておきましょう。ご不安な場合には、実際に諭旨解雇を下す前に、弁護士にご相談をいただいておくべきです。
労働審判・訴訟への発展リスク
また、従業員とのトラブルが解決しない場合、労働審判や訴訟へと発展する可能性が残るということそれ自体も企業のリスクとなります。これらの手続は、会社にとって時間的・金銭的負担が大きく、企業の評判にも影響を与える可能性があります。
諭旨解雇時に、従業員の納得を得られるようにしておくことで、少しでもリスクを低減しましょう。
顧問弁護士の活用が有効な場面
ここで、諭旨解雇をする際に、顧問弁護士の活用が有効な場面についてご紹介します。やはり、諭旨解雇を万全の体制で行うためには、平時から会社の状況を知っている顧問弁護士の助力が必要です。
手続の適法性の確認
弁護士は、諭旨解雇の手続が法的に適切であるか、就業規則の規定と照らし合わせて確認してくれます。これにより、後々のトラブル発生リスクを大幅に低減できます。特に弁護士であれば訴訟等に発展した際にリスクが大きくならないように配慮・手当てすることができるでしょう。
社員への対応・交渉
また、問題社員本人への説明や交渉は、どうしても感情的になりやすく、慎重な対応が求められます。例えば説明・交渉の場に弁護士が立ち会うことで、冷静かつ法的な根拠に基づいた交渉が可能となりますから、円満な解決に繋がりやすくなります。
事前相談で会社を守る
上記のとおり、諭旨解雇を検討する段階で弁護士に事前に相談することで、想定されるリスクを洗い出し、適切な対応策を講じることができます。これにより、会社が法的なトラブルに巻き込まれることを未然に防ぎ、会社の利益を守ることができます。
5.まとめ
以上のとおり、諭旨解雇の制度と手続、そして諭旨解雇のメリットとリスクをご紹介しました。諭旨解雇等の懲戒処分を下す前には、顧問弁護士を付けておくことをお勧めします。当事務所では、多くの企業の顧問を担当しておりますので、問題社員への対応に自信をもってアドバイスできます。実際にお悩みになる前に、ぜひ、当事務所に一度ご相談ください。
監修者
弁護士法人グレイス企業法務部
- 本店所在地
- 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
- 連絡先
- [代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129 - WEBサイト
- https://www.kotegawa-law.com/
「問題社員対応(解雇・退職勧奨等)」の関連記事はこちら
お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら
電話で問い合わせる
0120-77-9014
受付時間:平日9:00-17:30
メールで問い合わせる
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!
メールでのお問い合わせは24時間受付中!