企業法務コラム
懲戒解雇が有効となるためには
更新日:2023/12/22
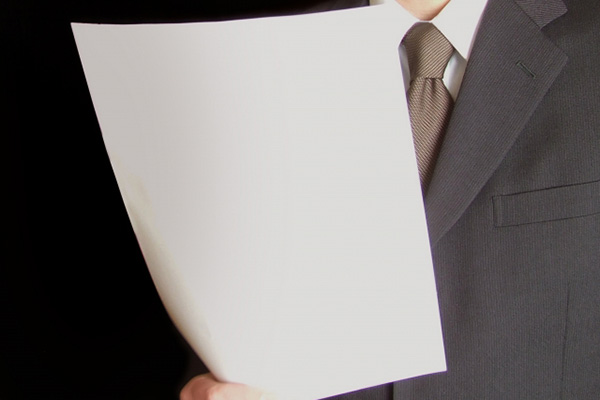
1. 解雇にはどのような種類があるか
解雇にも普通解雇、懲戒解雇、整理解雇等、いくつかの種類がありますが、そのうちの懲戒解雇は、あくまで懲戒処分としての解雇ですので、そもそも懲戒処分ができるのかという点が問題となります。
2. 懲戒処分としての解雇をする上で必要な手続は?
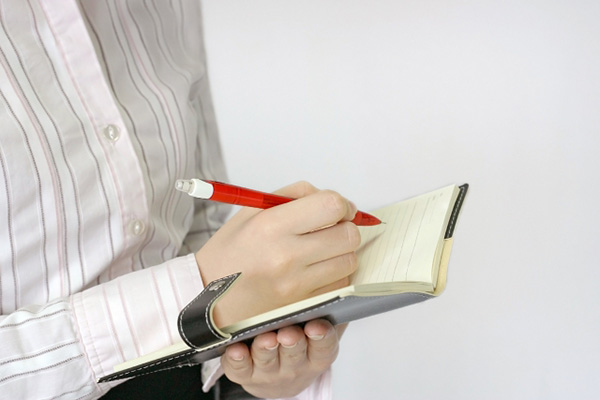
使用者が労働者に対して懲戒処分をする場合、まず、あらかじめ就業規則において懲戒の種類、及び懲戒事由を定めておくことが必要です。
ここにいう懲戒の種類とは、例えば、戒告や減給、出勤停止といったものです。また、懲戒事由とは、例えば「会社の名誉・信用を毀損し、又は会社に損害を及ぼした場合」や、「経費の不正な処理をした場合」というものです。
就業規則に定められている懲戒事由に該当し、その懲戒事由に相当する懲戒処分の内容が就業規則に明示されていることによってはじめて、懲戒処分をなすことができるのです。
次に、当該労働者に解雇理由を告知したり、弁明の機会を与えたりする手続が必要になります。何ら解雇の理由を示すことなく、または一切の弁明の機会を与えないまま懲戒解雇とした場合には、必要な手続きを欠いたものとして、その解雇が無効となる可能性があります。
3. 解雇権濫用法理とは?

以上は、懲戒解雇を有効とするための形式的な要件に過ぎず、これらを充たしていれば直ちに懲戒解雇が有効となるものではありません。
労働契約法15条は、「当該懲戒が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定しております。これは解雇権濫用法理といわれております。
ここにいう「客観的に合理的な理由」とは、解雇理由とされている事実が真に存在し、解雇を正当化するものであるということが、外部から検証できる程度に裏付けられるかという要件です。
これは解雇の有効性を争うことになった場合には、「信用力のある証拠が存在するのか」という問題として先鋭化します。当事務所が顧問弁護士として、どういう証拠を整えておくべきなのか普段からお客様にアドバイスを差し上げているのも、この要件をクリアするために必要であるからに他なりません。
また、「社会通念上相当である」とは、懲戒処分としての解雇を行おうと判断するに至った問題が、解雇という究極の方法で労働者を企業から排除する程度のものであるか否かという問題です。
すなわち、解雇という処分の重さが解雇の理由となった事実の重さとバランスが保てているのかというチェック項目といえます。例えば、仮に労働者が一度遅刻したからといって、即刻出勤停止や解雇といった処分をとることは行き過ぎであるという判断です。重い処分をとる前にまずは事案に即した軽い処分を選択すべきです。当該処分を複数回行ったにもかかわらず、労働者に改善が認められない場合に、初めて出勤停止、更には解雇というより重い処分の選択を考えるという、段階的な対応が必要になります。
4. 解雇が無効となった場合のリスク
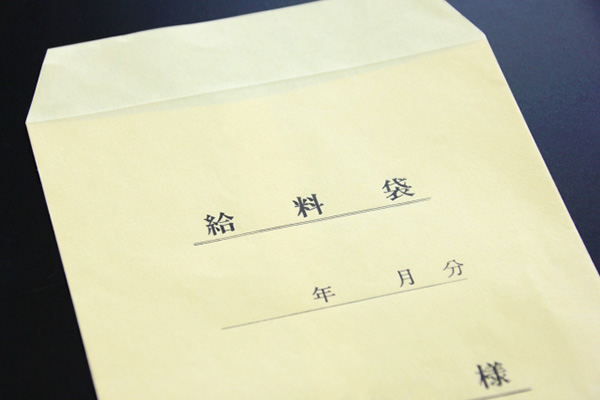
使用者としては解雇をしたつもりが、後になって労働者が以上の各要件のうちどれかを欠くとして、解雇が無効である旨争うケースが非常に多いです。
そして、仮に解雇が無効であるとの判断が裁判所からなされると、使用者は、解雇した日から裁判が確定した日までの間に発生したはずの賃金を、労働者の勤務実態がないにもかかわらず、支払わなければなりません。
使用者にとって、この経済的負担は決して軽視できないリスクであるため、懲戒解雇をする場合には、その法的判断を非常に慎重に行わなければなりません。
監修者
弁護士法人グレイス企業法務部
- 本店所在地
- 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
- 連絡先
- [代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129 - WEBサイト
- https://www.kotegawa-law.com/
「問題社員対応(解雇・退職勧奨等)」の関連記事はこちら
お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら
電話で問い合わせる
0120-77-9014
受付時間:平日9:00-18:00
メールで問い合わせる
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!
メールでのお問い合わせは24時間受付中!














