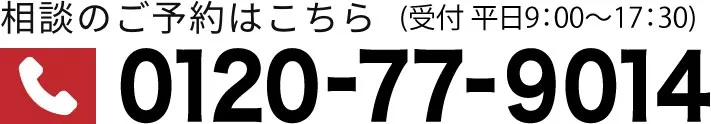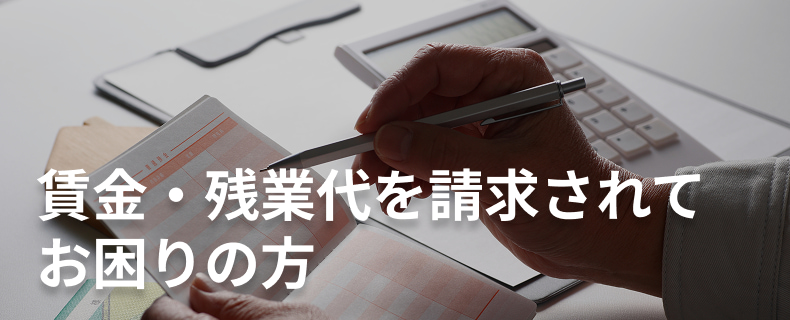企業法務コラム
福岡で懲戒解雇・退職勧奨を検討中の企業様へ適切な進め方について事例を交えて弁護士が解説
更新日:2025/11/25
企業の経営者様や人事担当者様で、問題社員への対応や、やむを得ない人員整理について、頭を悩ませてはいないでしょうか。
特に懲戒解雇や退職勧奨を検討する際には、以下のようなお悩みをお持ちの方が多くいらっしゃいます。
- ・問題行動が目立つ従業員への対応に困っている
- ・懲戒解雇を検討しているが、法的なリスクがわからず踏み切れない
- ・退職勧奨をしたいが、どのように進めればよいか手順を知りたい
- ・退職後に従業員から訴えられないか不安を感じる
結論から申しますと、懲戒解雇や退職勧奨で最も大切なことは、感情的に判断せず、法的に正しい手順を踏むことです。なぜなら、初動対応や手続きを一つでも誤ると、後から解雇が無効となり、多額の金銭支払いを命じられるなど、企業の存続に関わる重大なリスクに発展するおそれがあるからです。
この記事では、福岡の企業様が従業員とのトラブルで失敗しないために、懲戒解雇と退職勧奨の基礎知識から、具体的な進め方、弁護士による解決事例までをわかりやすく解説します。
- この記事でわかること
-
- 懲戒解雇と退職勧奨の違い
- 懲戒解雇と退職勧奨の優先すべき対応
- 懲戒解雇が無効となるリスク
- 懲戒解雇と退職勧奨の基礎と手続きの流れ
- 懲戒解雇・退職勧奨を弁護士に依頼するメリット
目次
福岡の企業様がまず押さえるべき懲戒解雇と退職勧奨の対応
従業員との雇用関係を終了させる手段として、懲戒解雇と退職勧奨は性質が全く異なります。福岡で事業を営む企業様が、これらの対応を検討するにあたり、まず最初に押さえるべき初動対応と両者の分岐基準について解説します。
初動で優先すべき対応(証拠保全・ヒアリング)
問題が発覚した際、感情的な対応は禁物です。
まず優先すべきは、客観的な事実を証明するための「証拠保全」と、関係者からの「ヒアリング」です。
証拠保全の具体例
懲戒処分や解雇の妥当性を証明するために、以下のような証拠を確保します。
- メールやチャットの履歴: 問題行動に関するやり取り
- 業務日報や勤怠記録: 勤務態度の問題を示す記録
- パソコンのログデータ: 不正な情報アクセスや私的利用の履歴
- 防犯カメラの映像: 横領や暴力行為などの記録
- 関係者の陳述書: 同僚や取引先からの具体的な証言
- 始末書や注意指導の記録: 過去の指導履歴
これらの証拠は、後に従業員と争いになった際、会社の正当性を主張するための生命線となります。
ヒアリングの注意点
関係者から話を聞くときは、以下の点に注意してください。
- 複数名で実施: 担当者一人ではなく、必ず複数名で対応する
- 事実確認に徹する: 感情的な詰問や誘導尋問は避ける
- 記録の作成: 「いつ、どこで、誰が、何をしたか」を時系列で記録する
- 秘密の厳守: 関係者のプライバシーに配念慮する
正確な事実確認が、適切な判断の第一歩です。
懲戒解雇と退職勧奨の分岐基準
懲戒解雇と退職勧奨は、どちらも雇用契約を終了させる可能性がありますが、その性質は大きく異なります。
| 項目 | 懲戒解雇 | 退職勧奨 |
|---|---|---|
| 性質 | 罰則(ペナルティ) | 合意に向けた交渉(お願い) |
| 主導権 | 会社の一方的な意思表示 | 従業員の自由な意思 |
| 退職理由 | 会社都合(重責解雇) | 自己都合または会社都合 |
| 退職金 | 不支給・減額の可能性あり | 通常どおり支給 |
| 法的リスク | 高い(無効リスク) | 低い(退職強要リスク) |
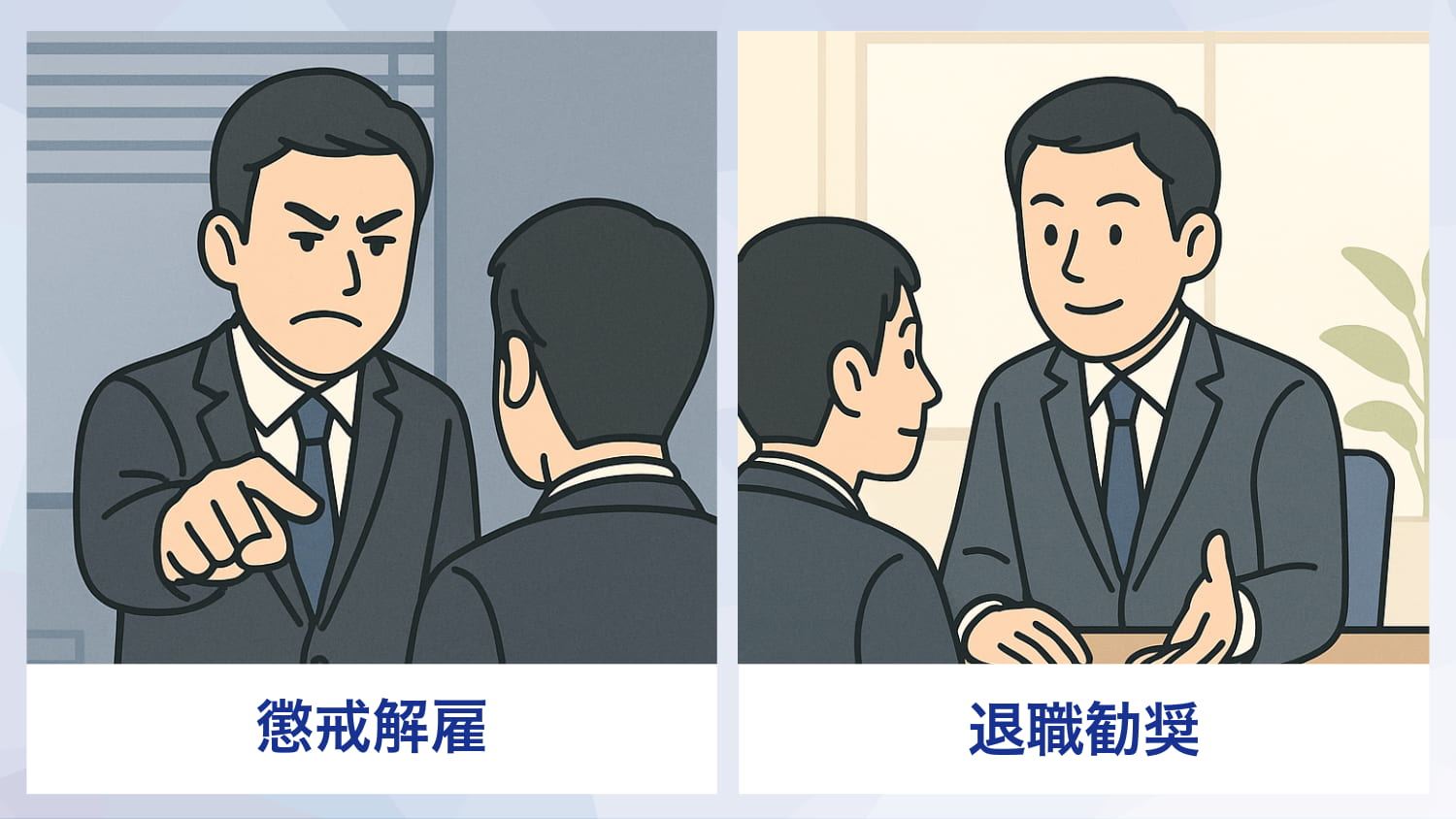
どちらを選択すべきか
選択の基準は、「従業員の行為の悪質性」と「証拠の明白性」です。
- 懲戒解雇を検討するケース:
業務上横領、重大な経歴詐称、悪質なハラスメントなど、極めて悪質な規律違反が明白な証拠とともにある場合。 - 退職勧奨を検討するケース:
能力不足、勤務態度不良、協調性の欠如など、懲戒解雇とするには証拠が弱い、または行為が悪質とはいえない場合。
紛争の長期化を避け、穏便な解決を望む場合。
福岡県内の多くの企業様は、リスク管理の観点から、まず退職勧奨による合意退職を目指すのが一般的です。安易な懲戒解雇は、会社の存続を揺るがしかねないリスクをはらんでいることを認識しましょう。
懲戒解雇の基礎と手順
懲戒解雇は、会社が従業員に科すことのできる最も重い処分です。そのため、裁判所は有効性を厳しく判断します。ここでは、懲戒解雇を法的に有効とさせるための基礎知識と、踏むべき手順を解説します。
有効性判断のポイント(要件・相当性・退職金)
懲戒解雇が有効と認められるためには、法律上の要件を満たす必要があります。
労働契約法第15条
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
この条文から、以下の3つのポイントが重要になります。
- 就業規則上の明記: 懲戒解雇の理由となる事由が、あらかじめ就業規則に具体的に記載されていることが大前提です。
- 客観的に合理的な理由: 従業員の行為が、就業規則の懲戒事由に該当するという客観的な証拠が必要です。
- 社会通念上の相当性:従業員の行為の悪質性と、懲戒解雇という処分の重さのバランスが取れていることが求められます。例えば、一度の遅刻で懲戒解雇にすることは、相当性を欠き無効と判断される可能性が極めて高いです。
退職金について
多くの会社では、就業規則に「懲戒解雇の場合、退職金を不支給または減額する」という規定があります。この規定自体は有効ですが、懲戒解雇自体が無効と判断されれば、当然退職金も支払う義務が生じます。
手続きの流れと注意点(調査・弁明・通知文)
懲戒解雇を行うには、適正な手続きを踏むことが不可欠です。
- 事実関係の調査: 先述した証拠保全とヒアリングを徹底し、客観的な事実を固めます。
- 弁明の機会の付与:
本人に懲戒処分の対象となっている事実を伝え、言い分を聞く機会を必ず設けてください。これを「弁明の機会の付与」といいます。従業員の言い分を一切聞かずに処分を決定すると、手続きの不備として解雇が無効になるリスクがあります。 - 懲戒委員会の開催(任意): 社内に規定があれば、懲戒委員会を開き、処分の妥当性を審議します。
- 懲戒解雇の決定と通知:最終的に懲戒解雇を決定した場合、「懲戒解雇通知書」を作成し、本人に交付します。通知書には、解雇日と、就業規則のどの条項に基づく解雇なのかを明確に記載する必要があります。
無効リスクと典型的な失敗例
懲戒解雇が無効と判断された場合、会社は深刻なダメージを受けます。
- バックペイの発生: 解雇期間中の給与を、さかのぼって全額支払う義務が生じます。
- 慰謝料の支払い: 不当解雇と認定され、慰謝料の支払いを命じられることがあります。
- 企業イメージの低下: 「ブラック企業」という評判が広がり、採用活動や取引に悪影響を及ぼすおそれがあります。
典型的な失敗例
- 証拠が不十分: 社長の思い込みや、噂レベルの話で解雇してしまう。
- 処分のバランスを欠く: 軽微なミスに対して、最も重い懲戒解雇を選択する。
- 手続きの不備: 弁明の機会を与えずに、一方的に解雇を通知する。
これらの失敗を避けるためにも、処分の決定前に必ず専門家である弁護士に相談することが重要です。
退職勧奨の基礎と進め方
退職勧奨は、会社から従業員に対して退職を「お願い」し、双方の合意によって雇用契約を終了させる方法です。あくまで任意であるため、進め方を間違えると「退職強要」という違法行為になりかねません。
違法とならないための面談ルール
適法な退職勧奨と、違法な退職強要の境界線は非常に曖昧です。以下のルールを守り、従業員の自由な意思決定を尊重する姿勢を保ってください。
- 面談の時間と頻度:
1回の面談は30分〜1時間程度、何度も執拗に繰り返さない。 - 面談の場所:
会議室など、プライバシーが確保された静かな場所を選ぶ。 - 面談の人数:
従業員1名に対し、会社側は2名程度が望ましい。大人数で囲むのは威圧的です。 - 発言内容:
「辞めてほしい」という会社の意思は明確に伝える。
大声を出したり、机を叩いたりするなどの威圧的な言動は厳禁。
「解雇する」「あなたの将来はない」といった脅迫的な発言はしない。
「退職届を出すまで部屋から出さない」といった監禁行為は論外です。 - 考える時間を与える:
その場での決断を強要せず、「一度持ち帰って考えてください」と伝える。
合意書に盛り込むべき項目と解決金の目安
従業員が退職に合意した場合、必ず「退職合意書」を2部作成し、双方が署名・押印のうえ、1部ずつ保管します。
合意書に盛り込むべき主な項目
- ・退職日
- ・退職理由(「会社都合」か「自己都合」か)
- ・解決金の金額と支払日
- ・守秘義務条項
- ・会社への誹謗中傷を行わない旨の条項
- ・清算条項(本書に定めるほか、債権債務がないことを確認する)
解決金の目安
法的な支払い義務はありませんが、従業員に合意してもらうインセンティブとして、解決金を提示することが一般的です。金額の目安は、賃金の3ヶ月〜6ヶ月分がひとつの相場となります。ただし、事案の性質や交渉次第で変動します。
応じない場合の選択肢
従業員が退職勧奨に明確に応じない場合、会社側は以下の選択肢を検討することになります。
- 退職勧奨を打ち切る:
これ以上続けても合意の見込みがないと判断し、現状のまま雇用を継続する。 - 配置転換や役割変更を検討する:
本人の適性に合わせて、別の部署への異動を打診する。 - 普通解雇を検討する:
退職勧奨の理由が、普通解雇の要件(著しい能力不足など)を満たすか慎重に検討する。ただし、普通解雇も懲戒解雇と同様に、有効性のハードルは非常に高いです。
従業員が応じないからといって、嫌がらせをしたり、仕事を取り上げたりすることは、パワーハラスメントにあたり、新たなトラブルの原因となりますので絶対にやめてください。
弁護士法人グレイスの解決事例の一例
在庫転売疑いで懲戒解雇訴訟に対応したケース
ご相談内容:
会社の倉庫にあった商品をフリマサイトで転売した疑いがある従業員を懲戒解雇したところ、その従業員から「解雇は無効だ」として訴訟を起こされた。
弁護士の対応と解決:
ご相談の段階では、転売をしていたという直接的な証拠は弱い状況でした。しかし、当事務所の弁護士が、訴訟手続きの中で法的な手段を用いて調査を進めた結果、その従業員が転売を行っていた蓋然性が極めて高いことを示す証拠を複数発見しました。最終的に、相手方である元従業員の請求の放棄という形で、全面的に当社の主張が認められる形で解決しました。
ポイント:
懲戒解雇の有効性は、いかに客観的な証拠を揃えられるかにかかっています。当初は不利に見える状況でも、弁護士が介入し、法的な手続きを利用することで、形勢を逆転できる場合があります。
試用期間中の問題社員を合意退職で解決したケース
ご相談内容:
中途採用した従業員が、入社直後から業務への不満を述べたり、他の従業員の前で経営方針を批判したりするなどの問題行動を繰り返したため、試用期間中に解雇した。すると、相手方の弁護士から解雇無効を前提とした未払い賃金の支払いを求める通知が届いた。
弁護士の対応と解決:
試用期間中の解雇は、本採用後よりも広く認められる傾向にありますが、無制限ではありません。本件も、裁判になれば解雇が無効と判断されるリスクがありました。ご依頼主である会社様の最大の希望は「その従業員に戻ってきてほしくない」という点にありましたので、当事務所は交渉による解決を目指しました。
相手方からは当初、給与6ヶ月分の解決金を要求されましたが、粘り強く交渉した結果、給与2ヶ月分を支払うことで自己都合退職とするという内容で合意に至りました。
ポイント:
「試用期間だから」と安易に解雇すると、かえって大きな紛争に発展することがあります。裁判で争うだけでなく、交渉によって早期に、かつ経済的損失を最小限に抑えて解決するという選択肢もあります。
福岡で懲戒解雇・退職勧奨を弁護士に依頼するメリット
労働問題は、初期対応を誤ると紛争が複雑化・長期化しがちです。早い段階で弁護士に依頼することで、企業は多くのメリットを得られます。

違法リスクを回避し、適法な手続きを実現できる
弁護士は、懲戒解雇や退職勧奨が法的に有効となるための要件や、踏むべき手続きを熟知しています。専門家の助言に基づき対応することで、「手続きの不備」や「権利濫用」といった致命的なミスを防ぎ、違法な解雇と判断されるリスクを大幅に低減できます。
交渉力と抑止力でトラブルを早期に収束できる
弁護士が代理人として交渉の窓口に立つことで、感情的になりがちな従業員とのやり取りを、冷静かつ法的な土俵で行うことができます。また、「弁護士がついている」という事実が相手方への抑止力となり、無理な要求を抑制し、トラブルの早期収束につながります。
労働局・労働審判・訴訟への備えが整う
万が一、あっせんや労働審判、訴訟といった法的な紛争に発展した場合でも、顧問弁護士がいれば、事実関係を迅速に把握し、一貫した方針で的確な対応をとることが可能です。いざというときに慌てることなく、万全の体制で臨めます。
規程整備や研修で再発防止と社内体制を強化できる
弁護士の関与は、目の前のトラブル解決だけにとどまりません。今回の事案を教訓に、就業規則や懲戒規程の不備を見直したり、管理職向けのハラスメント研修を実施したりするなど、将来の労務リスクを予防し、健全な社内体制を構築するためのサポートも可能です。
福岡で弁護士に相談する流れと費用の目安
当事務所にご相談いただくさいの、一般的な流れと費用の目安についてご説明します。
相談から解決までのステップ
- お問い合わせ: まずは、お電話またはウェブサイトのフォームから、お気軽にご連絡ください。
- 初回相談: 弁護士が直接お話を伺い、問題の法的整理と、今後の見通しをご説明します。(オンラインでのご相談も可能です)
- ご依頼・委任契約: 方針にご納得いただけましたら、委任契約を締結します。
- 方針の実行: 弁護士が代理人として、相手方との交渉や書面作成、法的手続きなどを進めます。
- 解決: 合意書の締結や、訴訟の終結などをもって、問題解決となります。
費用感とオンライン対応
弁護士費用は、大きく分けて以下の3つで構成されることが一般的です。
- 法律相談料: 弁護士に相談する際にかかる費用。
- 着手金: 弁護士に依頼する際に、最初にお支払いいただく費用。
- 報酬金: 事件が解決した際に、成功の度合いに応じてお支払いいただく費用。
具体的な金額は、事案の複雑さや、予想される業務量によって異なります。初回相談のさいに、詳細な御見積りを提示いたしますので、ご安心ください。
当事務所は、初回の法律相談を無料で承っております。福岡市内はもちろん、福岡県内全域の企業様からのご相談に対応しており、Zoomなどを利用したオンライン相談も積極的に活用しています。
また、顧問契約を締結いただくことによって、日頃の問題に対するアドバイスのみではなく長期的な体制構築のサポートが可能です。
懲戒解雇・退職勧奨に関するよくあるご質問
どのような場合に懲戒解雇が認められますか?
懲戒解雇が有効と判断されやすいのは、従業員の行為が会社の秩序を著しく乱し、信頼関係を完全に破壊したといえる重大なケースです。具体的には、業務上横領、重要な経歴の詐称、長期間の無断欠勤、悪質なハラスメント行為などが挙げられます。
懲戒解雇を行うことで、会社にどのようなリスクやデメリットがありますか?
最大のデメリットは、解雇が無効と判断されるリスクです。無効となった場合、解雇期間中の給与(バックペイ)の支払いや、慰謝料の支払い義務が生じる可能性があります。また、訴訟に発展すれば、時間的・金銭的コストがかかるほか、企業の社会的信用が低下するおそれもあります。
退職勧奨を行うときは、どのようなことに注意したらいいですか?
従業員の自由な意思を侵害する「退職強要」と受け取られないように注意が必要です。具体的には、大声や威圧的な言動を避ける、長時間・多数回にわたる面談は行わない、その場での決断を強要しない、といった点に配慮してください。
従業員が退職勧奨に応じない場合、どのようなことに対処したらいいですか?
従業員には退職勧奨に応じる義務はないため、拒否された場合は、一旦その勧奨を打ち切るのが基本です。その上で、配置転換など他の選択肢を検討します。安易に普通解雇に切り替えることは、解雇権の濫用と判断されるリスクが高いため、極めて慎重な判断が求められます。
まとめ(判断を誤らないための要点整理)
この記事では、懲戒解雇と退職勧奨について、その違いから法的なリスク、具体的な進め方までを解説しました。
- ・懲戒解雇は、リスクの高い最終手段。客観的な証拠と適正な手続きが不可欠。
- ・退職勧奨は、あくまで任意。退職強要とならないよう、進め方には細心の注意が必要。
- ・どちらを選択するにせよ、初動対応としての「証拠保全」が極めて重要。
従業員との労務トラブルは、一つ対応を誤るだけで、会社の経営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。判断に迷ったとき、対応に不安を感じたときは、決して自己判断で進めず、できるだけ早い段階で、労働問題に精通した弁護士にご相談ください。
福岡で企業の労務問題にお悩みの経営者様・人事担当者様は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
監修者
弁護士法人グレイス企業法務部
- 本店所在地
- 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
- 連絡先
- [代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129 - WEBサイト
- https://www.kotegawa-law.com/
「問題社員対応(解雇・退職勧奨等)」の関連記事はこちら
お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら
電話で問い合わせる
0120-77-9014
受付時間:平日9:00-17:30
メールで問い合わせる
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!
メールでのお問い合わせは24時間受付中!