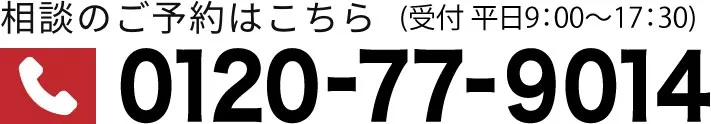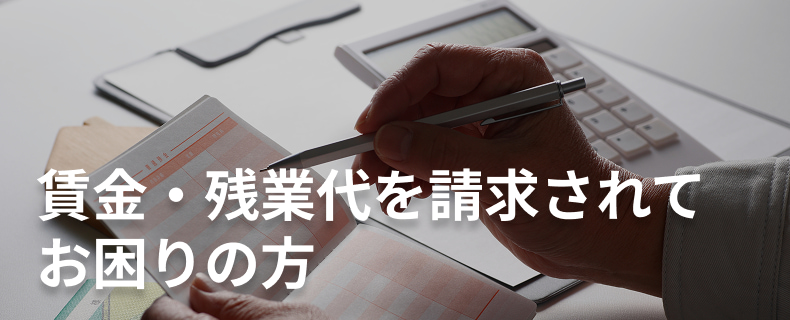企業法務コラム
退職後の競業避止義務とは?誓約書の必要性と元従業員の引き抜きに対する企業の対策を弁護士が解説
更新日:2025/10/28
「中核を担う従業員の突然の退職。もし競合他社に転職し、顧客を引き抜かれたら…」
経営者として、このような不安をもつのは当然のことです。
貴社では、以下のようなお悩みはありませんでしょうか。
- 退職する社員に「競業避止義務」を課したいが、どんな誓約書なら有効かわからない。
- 元従業員が同業他社に就職した。自社の顧客に接触しているようで、やめさせたい。
- 入社時に交わした誓約書が、法的にどこまで効力をもつのか知りたい。
結論からいうと、法的なポイントを押さえた競業避止義務の誓約書は、会社の資産を守る強力な武器になります。なぜなら、裁判所も企業の「守るべき正当な利益」は保護する一方で、従業員の「職業選択の自由」を不当に侵害する内容は無効と判断するからです。つまり、有効な対策には法律上のバランス感覚が不可欠です。
本記事では、競業トラブルに悩む経営者様に向けて、弁護士が実践的な知識をわかりやすく解説します。
退職者による競業や顧客の引き抜きは、企業の存続を揺るがしかねない重大なリスクです。競業避止義務を定めた誓約書は、会社の技術や顧客リストといった無形の資産を守る強力な武器となりますが、法的な要件を満たさなければ無効と判断される可能性があります。
誓約書が有効と認められるには、制限する期間・場所・職種の範囲が合理的で、従業員の不利益に見合う代償措置が講じられていることなどが重要です。
誓約書の作成、トラブルが発生してしまってお困りの方は弁護士法人グレイスへご相談ください。企業向けに誓約書の作成・見直しのサポートを行っております。初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
- この記事でわかること
-
- 競業避止義務の基本と法的リスク
- 誓約書が「有効」と判断される6つの基準
- トラブルを防ぐ誓約書の作り方と例文
- 違反された場合の具体的な対処法3ステップ
目次
競業避止義務とは?経営者が押さえるべき競業避止義務の目的と法的根拠
競業避止義務とは、従業員が退職後、在職中に得た知識や経験、人脈などを利用して、所属していた企業と競合する事業や会社に就職したり、自ら開業したりすることを禁止する義務のことです。
中小企業にとって、独自の技術情報、顧客リスト、営業ノウハウは事業の生命線といえます。これらが退職した従業員によって安易にライバル社に渡ってしまえば、会社の競争力が著しく低下し、経営に深刻なダメージを与えかねません。
このような事態を防ぎ、企業の「守るべき正当な利益」を保護することが、競業避止義務の主な目的です。この義務は、企業と従業員との間の契約(合意)に基づいて発生するのが一般的です。
「職業選択の自由」との関係で無効になることも
一方で、日本国憲法第22条第1項では「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」と定められています。
従業員にも、退職後にどのような職業に就くかを自由に決める権利があります。そのため、企業が従業員のキャリアを過度に制約するような競業避止義務を課すことは、この「職業選択の自由」を不当に侵害するものとして、裁判所で無効と判断されることがあります。
したがって、競業避止義務に関する取り決めは、企業の利益保護と、従業員の職業選択の自由とのバランスを適切にとることが極めて重要になるのです。
誓約書や就業規則の定めがなくても義務は発生する?
「うちの会社は、競業避止義務について誓約書も交わしていないし、就業規則にも書いていない。だから何も請求できないのでは?」とご不安になる経営者の方もいらっしゃるでしょうか。
結論からいうと、原則として、個別の合意(誓約書など)や就業規則上の根拠がなければ、従業員は退職後に競業避止義務を負いません。
ただし、例外もあります。例えば、企業の機密情報(営業秘密)を不正に持ち出して使用するようなケースでは、不正競争防止法に基づき差止請求や損害賠償請求が可能な場合があります。また、役員など特に重要な地位にあった従業員の場合、信義則上の付随義務として、一定の競業避止義務が認められる可能性もゼロではありませんが、極めて限定的です。
トラブルを未然に防ぎ、会社の権利を確実に守るためには、書面による明確な合意が不可欠といえるでしょう。
競業避止義務に関する誓約書が「有効」になるかの判断基準
競業避止義務を定めた誓約書や就業規則が法的に有効と認められるためには、いくつかの要素を総合的に考慮して判断されます。ここでは、過去の裁判例で重視される6つの判断基準を解説します。
① 目的の合理性-守るべき企業の利益は明確か-
競業避止義務によって守ろうとしている利益が、企業にとって本当に「守る価値のある正当な利益」といえるかどうかが問われます。
認められやすい例:
- 他社が容易に模倣できない独自の製造技術
- 長年の営業努力で築き上げた顧客リストや緊密な関係性
- 社外秘の営業戦略や開発情報
認められにくい例:
- 一般的に公開されている情報や知識
- 誰が担当しても同様の結果が出せるような定型的な業務ノウハウ
② 従業員の地位・職務内容
競業避止義務を課される従業員が、在職中にどのような地位や職務内容にあったかも重要なポイントです。
企業の重要な情報にアクセスできる立場にあった従業員ほど、義務の必要性が認められやすくなります。一般的に、取締役などの役員や管理職は、一般社員よりも重い義務が認められる傾向にあります。
③ 地域的範囲の合理性
競業行為を禁止する地理的な範囲が、企業の事業内容に照らして妥当な範囲に限定されている必要があります。
例えば、顧客が関東一円にしかいない企業が、誓約書で「日本全国における競業行為を禁止する」と定めた場合、その範囲は広すぎると判断され、無効になる可能性が高いでしょう。旧担当エリアや、事業所が所在する都道府県など、合理的な範囲に絞ることが求められます。
④ 制限期間の合理性
退職後、競業を禁止する期間が不当に長すぎないかも判断基準となります。
企業のノウハウや顧客情報も時間とともに陳腐化するため、永久に禁止することは認められません。過去の裁判例をみると、おおむね「6ヶ月〜2年」の範囲内であれば有効と判断されることが多いようです。これを大幅に超える3年や5年といった長期間の定めは、無効と判断されるリスクが高まります。
⑤ 職種・業務範囲の限定
禁止される競業行為の範囲が、具体的かつ明確に定められている必要があります。
「一切の同業他社への就職を禁ずる」といった包括的で曖昧な規定は、従業員の職業選択の自由を過度に制限するものとして無効になりやすいです。「〇〇製品を取り扱う事業部門での業務」「〇〇に関するコンサルティング業務」のように、企業の守るべき利益と関連する範囲に限定することが重要です。
⑥ 代償措置(補償)の有無
競業避止義務という制約を課す見返りとして、企業が従業員に対して何らかの経済的な利益(代償措置)を提供しているかは、有効性を判断する上で非常に重視されます。
代償措置がない、あるいは不十分な場合、誓約書が無効と判断される可能性が高まります。
代償措置の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 退職金の増額
- 競業避止義務手当などの支給(在職中または退職後)
- 相応の地位や高い給与の支払い
競業避止義務って、ただ誓約書に書くだけじゃ駄目なんですね。特に補償については初めて知り驚きました。
代償措置の有無も重要な判断基準になります。退職金の上乗せや特別手当など、義務の重さに見合う補償を設定することで、有効性が高まります。
トラブルを未然に防ぐ!有効な競業避止義務の誓約書・就業規則の作り方
ここまで解説した判断基準を踏まえ、実際にトラブルを防ぐための具体的な方法を見ていきましょう。
誓約書を交わすベストなタイミングは「入社時」
競業避止義務に関する誓約書は、原則として「入社時」に署名・捺印をもらうのが最も効果的です。雇用契約を結ぶタイミングで、労働条件の一つとして従業員に説明し、納得のうえで合意を得ることで、その後のトラブルを大きく減らすことができます。
なぜ退職時ではリスクがあるのか
退職を申し出た従業員に対して、退職日直前に競業避止義務の誓約書への署名を求める企業もありますが、これはいくつかのリスクを伴います。
- 署名を拒否される可能性が高い:退職を決めた従業員にとって、新たな制約を受け入れるメリットはありません。
- 合意の任意性が疑われる:「退職金を受け取るために、仕方なく署名した」などと主張され、誓約書の効力が裁判で争われる可能性があります。
どうしても退職時に署名を求める場合の注意点
やむを得ない事情で退職時に誓約書を求める場合は、一方的に署名を強要するのではなく、以下の点に注意してください。
- 誓約書の内容(義務の範囲、期間など)を丁寧に説明し、従業員の理解を得る。
- 誓約に同意することへの見返りとして、解決金の支払いや退職金の増額といった明確な代償措置を提示する。
- 従業員に考える時間を与え、自由な意思で署名したことがわかるようにする。
就業規則への規定方法と周知の重要性
誓約書とあわせて、就業規則にも競業避止義務に関する根拠規定を設けておくことが望ましいです。就業規則に定めることで、会社としての統一的なルールであることを明確に示すことができます。
規定を設ける際は、「従業員は、退職後、会社の承認なく競合する企業に就職してはならない。詳細については、個別に従業員と締結する誓約書によるものとする」といった内容を記載します。
そして最も重要なのは、就業規則を従業員に周知することです。内容をいつでも閲覧できる状態にしておかなければ、就業規則自体の効力が認められない可能性があります。
競業避止義務の誓約書に盛り込むべき内容
有効な誓約書を作成するためには、前述した「6つの判断基準」を満たす内容を盛り込む必要があります。
また、競業避止義務は、秘密保持義務と1つの誓約書にまとめて記載することが多いです。
退職時の秘密保持誓約書はなぜ必要?効力が認められないケースや記載すべき項目について解説
秘密保持と競業避止義務を一緒に記載することが多い理由
1.目的の関連性が非常に高いから
企業が従業員に競業避止義務を課したいと考える最大の理由は、「自社の重要な秘密情報(技術、顧客リスト、ノウハウなど)を、競合他社で利用されることを防ぎたい」からです。
つまり、「競業避止」は「秘密保持」をより確実にするための強力な手段という位置づけになります。このように目的が密接に関連しているため、1つの書面で一体的に定めるのが自然で、合理的です。
2.管理の効率が良いから
経営者や人事担当者の視点から見ると、従業員一人ひとりに対して交わす誓約書は、できるだけシンプルに管理したいものです。入社時に「秘密保持及び競業避止義務に関する誓約書」といったタイトルの書面を1通取り交わすだけで済むため、管理が非常に楽になります。
3.従業員にも分かりやすいから
従業員にとっても、「退職後にしてはいけないこと」が1枚の書面にまとまっている方が、義務の内容を理解しやすくなります。
あえて分けて作成する場合
数は少ないですが、戦略的にあえて「秘密保持誓約書」と「競業避止義務に関する誓約書」を分けるケースもあります。
対象とする従業員を分けたい場合
秘密保持義務は、正社員、契約社員、アルバイトを含め、原則として全従業員に課すべき義務です。
一方で、競業避止義務は、企業の重要な情報にアクセスできる一部の役職者や特定の職種の社員(役員、管理職、研究開発職、トップ営業など)に限定して課すのが一般的です。
このように対象者を明確に分けたい場合、
- 全従業員向け:「秘密保持誓約書」
- 特定の従業員向け:「競業避止義務に関する誓約書」(秘密保持義務も再度記載することが多い)
と、分けて運用することがあります。
退職時に競業避止義務の合意を新たに取り付けたい場合
入社時には秘密保持誓約書しか取っていなかったものの、退職時に特に競業を制限する必要性が生じた場合などです。この場合、退職金の増額などの「代償措置」と引き換えに、退職時用の「競業避止義務に関する合意書」を別途作成することがあります。
元従業員が競業避止義務に違反した場合の対処法を3ステップで解説
予防策を講じていても、残念ながらトラブルが発生してしまうこともあります。元従業員の違反が疑われる場合に、会社がとるべき具体的な対処法を3つのステップで解説します。
ステップ1:まずは証拠の収集を
感情的になってすぐに元従業員本人に連絡をとるのではなく、まずは客観的な証拠を集めることが最優先です。証拠がなければ、その後の交渉や法的手続きを有利に進めることはできません。
競業行為の証拠:
- 競合他社のウェブサイトやパンフレット(元従業員が役員や従業員として掲載されている)
- 元従業員が使用している名刺
- 業界紙やSNSの情報
顧客や従業員の引き抜き行為の証拠:
- 顧客から「元従業員の〇〇さんから連絡があった」という情報提供(メールや書面で残してもらうのが望ましい)
- 在職中の従業員からの「〇〇さんから転職の誘いを受けた」という証言
- 元従業員が送付した挨拶状やメール
ステップ2:内容証明郵便で警告(通知)する
十分な証拠が集まったら、次は弁護士に相談のうえ、内容証明郵便で警告書(通知書)を送付します。
警告書には、①競業避止義務の根拠(誓約書など)、②現在確認できている違反行為の事実、③違反行為を即時に停止するよう求める要求、④要求に応じない場合は法的措置を講じること、などを記載します。
弁護士名義で送付することで、会社の断固たる姿勢を示すことができ、相手に強い心理的プレッシャーを与える効果が期待できます。この段階で、違反行為が停止され、交渉による解決に至るケースも少なくありません。
ステップ3:法的措置を検討する
警告しても違反行為がやまない場合は、裁判所を通じた法的手続きを検討します。
競業行為をやめさせる「差止請求(仮処分)」
これ以上、競業行為を続けられると会社に回復しがたい損害が生じる恐れがある場合に、その行為を暫定的に禁止するよう裁判所に求める手続きです。通常の訴訟よりも迅速に判断が下されるため、緊急性が高い場合に有効な手段となります。
被った損害を請求する「損害賠償請求」
元従業員の競業避止義務違反によって、顧客を奪われるなどして会社が被った損害について、金銭的な賠償を求める訴訟です。ただし、会社側は違反行為と損害発生との間の因果関係や、損害額を具体的に立証する必要があります。
退職金の減額・不支給は可能か
就業規則や退職金規程に、「競業避止義務に違反した場合は、退職金を減額または不支給とする」という明確な定めがある場合に限り、その有効性が認められる可能性があります。ただし、その場合でも、違反の程度に照らして退職金の全額を不支給とすることは、権利の濫用として認められないケースが多いです。
もし元社員が競合に移っていたら、すぐ連絡したくなりますが、まずは証拠集めが大事なんですね。どの段階で弁護士に相談すべきでしょうか。
はい、感情的な対応は避け、証拠を揃えた段階で早めに弁護士へご相談ください。内容証明での警告や法的手続きの可否を、状況に応じて判断いたします。
【解決事例】従業員の引き抜きと未払い家賃トラブルを交渉で解決
当事務所で実際に取り扱い、解決した事例をご紹介します。
ご相談内容:競合店への転職と従業員・顧客の引き抜き
飲食業を営む経営者様からのご相談でした。店の中心的な従業員が突然退職し、近隣の競合店で働き始めたことが判明しました。さらに、その元従業員は、元の店の常連客や他の従業員にまで連絡を取り、引き抜き行為を行っているとのことでした。
加えて、会社が提供していた住居の家賃も支払わないまま退去し、連絡先もわからない状況で、大変お困りでした。
弁護士の対応と解決結果:証拠を基に交渉し、引き抜き行為の停止と未払い賃料の回収に成功
まず、ご依頼者様にご協力いただき、引き抜き行為に関する証拠(他の従業員の証言や顧客からの情報など)を迅速に収集しました。
交渉の糸口が見つからない状況でしたが、幸いにも元従業員の方から未払い賃金の請求があり、それを機に直接交渉の場を設けることができました。
交渉の場で、当職から収集した証拠を提示し、引き抜き行為が競業避止義務に違反するものであることを冷静に指摘しました。その結果、元従業員は引き抜き行為の事実を認め、謝罪。今後一切の引き抜き行為を行わないことを誓約させました。また、問題となっていた未払いの家賃についても、分割で支払うことに合意させることができ、1回の交渉で紛争を早期に解決することができました。
競業避止義務に関するよくあるご質問(Q&A)
パートやアルバイトにも競業避止義務を課せますか?
可能です。ただし、正社員に比べて重要な情報にアクセスする機会が少ないため、義務の必要性や合理性がより厳しく判断される傾向にあります。店長クラスのアルバイトなど、その職務内容によっては有効と認められる可能性はあります。
代償措置は必ず必要ですか?相場はいくらくらいですか?
法律で必須と定められているわけではありませんが、裁判例では代償措置の有無が有効性を判断する上で極めて重視されています。事実上、有効な誓約書とするためには必要不可欠に近い要素といえるでしょう。金額に明確な相場はありませんが、在職中の地位や給与、制限される期間や内容などを総合的に考慮して、従業員の不利益を補うに足りる合理的な額を検討する必要があります。
従業員が誓約書への署名を拒否した場合、どうすればよいですか?
入社時に署名を拒否された場合、それを理由に採用を拒否することは、直ちに違法とはなりません。在職中の従業員や退職時の従業員に拒否された場合、署名を強制することはできません。なぜ誓約書が必要なのか、会社が守りたい利益は何かを丁寧に説明し、理解を求めることが重要です。
公務員にも競業避止義務はありますか?
国家公務員法や地方公務員法には、在職中の守秘義務や信用失墜行為の禁止などが定められていますが、退職後の競業避止義務について直接的な規定はありません。ただし、特定の機密を扱う職種などでは、個別の法令で規制されている場合があります。
違反した場合の違約金や損害賠償を定めることはできますか?
労働基準法第16条は「賠償予定の禁止」を定めており、競業避止義務違反に対して高額な違約金をあらかじめ定める契約は、無効となる可能性が非常に高いです。損害が発生した場合は、違約金としてではなく、実際に生じた損害額を立証して賠償請求することになります。
競業避止義務に関して弁護士に相談したい方
今回は、退職者の競業避止義務について、誓約書の有効性の判断基準から、トラブルの予防策、発生後の対処法までを解説しました。
競業避止義務に関する取り決めは、会社の貴重な資産を守るために不可欠ですが、その設定や運用を誤ると「無効」と判断され、いざという時に全く役に立たないリスクもはらんでいます。
- 自社の誓約書や就業規則が法的に有効か不安だ
- これから従業員と誓約書を交わしたいが、作り方がわからない
- すでに元従業員との間でトラブルが発生してしまっている
このようなお悩みをお持ちの経営者様は、初回相談を無料で受け付けておりますので、弁護士法人グレイスへお気軽にご相談ください。
監修者
弁護士法人グレイス企業法務部
- 本店所在地
- 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
- 連絡先
- [代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129 - WEBサイト
- https://www.kotegawa-law.com/
「問題社員対応(解雇・退職勧奨等)」の関連記事はこちら
お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら
電話で問い合わせる
0120-77-9014
受付時間:平日9:00-17:30
メールで問い合わせる
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!
メールでのお問い合わせは24時間受付中!