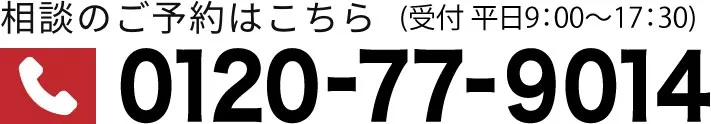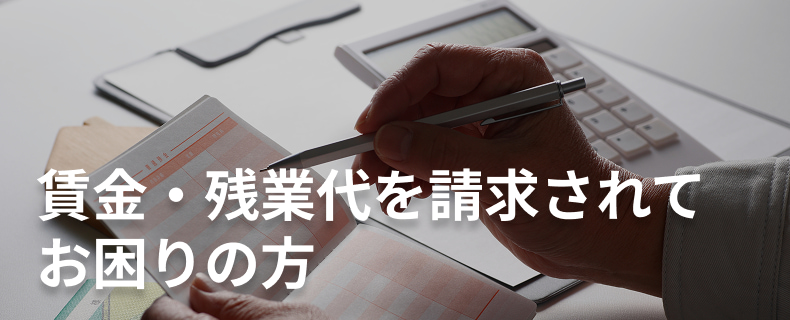企業法務コラム
従業員等による会社従業員の引き抜き行為をめぐる問題について
更新日:2025/09/16
中心となって活躍していた従業員が、ある日突然競合他社へ転職してしまった。さらに、その元従業員が主導して、他の従業員まで次々と引き抜かれていく…。経営者として、これほどの裏切り行為はないと感じるのではないでしょうか。
しかし、このような悪質な引き抜きに対して「転職は自由だから」と泣き寝入りする必要はありません。
悪質な引き抜き行為は違法と判断され、損害賠償請求が認められる可能性があります。実際に当法人の弁護士が担当した事案では、勝訴し300万円の損害賠償を獲得した例もございます。
①社会的相当性の逸脱、②加害側の故意・過失、③引き抜きと会社の損害(因果関係)などの証拠がそろえば、不法行為(民法709条)や債務不履行、役員の忠実義務違反、退職時の誓約書違反を根拠に請求できます。
この記事を読んでいる経営者様は、以下のようなお悩みを抱えているのではないでしょうか。
- ・そもそも、従業員の引き抜きで損害賠償を請求できるのか?
- ・どのようなケースが「違法な引き抜き」になるのか、具体的な基準を知りたい。
- ・損害賠償を請求するための手続きや、必要な証拠がわからない。
- ・実際に裁判で認められた場合、いくらくらいの賠償額になるのか相場を知りたい。
- ・今後、二度とこのような事態が起きないように対策を講じたい。
本記事では、従業員の引き抜き問題に直面している経営者様に向けて、損害賠償請求が認められる法的要件から、当法人が対応した事例、具体的な請求ステップ、そして将来の予防策まで、企業法務に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。
まずは、なぜ従業員の引き抜きが単なる転職問題ではなく、会社全体を揺るがす「経営問題」なのか、その理由から見ていきましょう。
- この記事でわかること
-
- 違法な引き抜きの3つの要件
- 認められた/棄却された裁判例と見るべきポイント
- 逸失利益・採用育成コストなどの損害算定の考え方
- 引き抜きで損害賠償をする基本ステップ
- 在職中/退職後それぞれの法的根拠と実務対応
- 引き抜きトラブルを防ぐ3つの再発防止策
目次
「ただの転職」ではない。悪質な引き抜きが会社に与える甚大な損害
従業員が単に他社へ転職するだけであれば一般的な人材の流動といえます。しかし、計画的かつ組織的に複数の重要社員を一斉に引き抜く行為は「ただの転職」ではなく、会社に甚大なダメージを与えかねません。
たとえば、主要プロジェクトを担うチームのメンバーがまとめて退職して競合に移れば、その部門の業務が回らなくなり、取引先からの信頼低下や売上減少など深刻な影響が生じます。
実際に幹部社員が在職中から同僚44名を新会社へ引き抜き、一度に大量退職者が出た結果、約1,500万円の損害賠償が命じられた判例もあります。このように、悪質な引き抜きは企業の存続を揺るがす経営問題となり得るのです。
一方で、すべての転職勧誘が違法となるわけではありません。個々の従業員が自発的に転職先を選ぶ行為自体は「職業選択の自由」(憲法22条)によって保障されています。
そのため、単なる1名の勧誘や円満な退職で会社に大きな支障がない場合には、会社側が泣き寝入りせざるを得ないケースもあります。しかし、明らかに背信的で会社経営に重大な支障を及ぼす「悪質な引き抜き」については違法と判断され、損害賠償が認められる可能性があるのです。
その引き抜きは違法です!?損害賠償請求が認められる3つの要件
「引き抜き被害で損害賠償を請求したい」と考える場合、まずその引き抜き行為が法的に“違法”と評価される必要があります。裁判で違法と判断されるためには、大きく以下の3つの要件を満たすことが必要です。
- ・引き抜き行為が社会的に許容される範囲を超えた悪質なもの(違法性)であること
- ・引き抜きを実行した側に故意または過失(違法な引き抜きを行った落ち度)があること
- ・その引き抜き行為によって会社に実際に損害が生じ、引き抜きと損害との間に因果関係があること
まず最も重要なのが要件1の「引き抜き行為自体の違法性」です。単なる転職の範囲を超え、「社会的相当性を逸脱した極めて背信的な方法」で行われた引き抜きであれば違法と認定されます。違法か否かの判断にあたって裁判所は、以下で述べるような様々な事情を総合考慮して判断を下しています。
要件1:【最重要】「社会的相当性」を逸脱した悪質な引き抜きか
違法と評価される引き抜きかどうかは、その行為が一般的な社会通念上許される範囲を超えているかで判断されます。具体的には、以下のようなポイントが総合的に考慮されます。
判断基準① 人数と地位:中心的な従業員が、複数名まとめて引き抜かれたか
引き抜きの対象となった従業員の社内での地位や役割の重要性、そして一度に何人が引き抜かれたか(人数の多さ)は重要な判断材料です。たとえば会社の中核メンバーやエース級の社員が引き抜かれた場合、会社への打撃が大きいため違法と認められやすくなります。
特に、責任あるポジションの人材が複数人同時に退職するようなケースでは、業務運営に重大な支障を来たす可能性が高く、社会的相当性を逸脱すると判断されやすいでしょう。
例:
実際の判例でも、会社売上の8割を占める部署の部長が、自らの部下多数と一斉退職して競合会社に移籍したケースでは、「単なる転職の勧誘の域を超え社会的相当性を逸脱した引き抜き」と認定されています。このように、会社の事業継続が困難になるほど重要人材がまとめて抜ける状況は、違法な引き抜きと判断される大きな要素となります。
判断基準② 計画性と背信性:在職中から計画され、秘密情報を利用したか
引き抜き行為が周到に計画されたものかどうか、そしてそのやり方が会社に対して背信的か(裏切り行為と言えるか)も判断基準になります。具体的には、次のような事情があると違法性が強まります。
在職中から秘密裏に引き抜き計画を進めていた:
退職前の在職期間中に水面下で同僚に声をかけ、転職を持ちかけていた場合は背信性が高いと評価されます。在職中の従業員には会社への誠実義務がありますから、在職中に裏で会社の人材を引き抜く行為は明らかに義務違反となり得ます。
会社の内部情報を悪用した:
引き抜きの際に、元の会社の経営上の弱みを誇張したり、社内の機密情報(人事情報や顧客情報)を利用した場合も悪質です。たとえば「会社の将来が不安だ」と同僚に吹聴して退職を煽ったり、社内データを持ち出して取引先に働きかけたよう。
引き抜きの手段が悪質:
勧誘時に元の会社の信用を傷つけるデマを流したり、引き抜かれる側に金銭的インセンティブ(報奨金等)を与えるなど、不当な手段が用いられた場合も違法と判断されやすいです。
以上のように、事前に綿密な謀議があり背信行為を伴う引き抜きは「極めて背信的な方法」に当たります。判例でも「在職中に共謀して組織の中枢メンバーを大量引き抜きし、在職中に知り得た情報を使って顧客を奪うなど悪質な場合に初めて、債務不履行または不法行為責任が問える」とされています。
判断基準③ 影響の大きさ:事業の継続が困難になるほどの損害を受けたか
引き抜きによって会社に生じた損害の大きさも考慮されます。たとえ複数人の退職があっても、会社の業績や事業にさほど影響がなければ違法とまでは言えない場合もあります。逆に、引き抜き後に売上や利益が急減し、事業縮小や停止に追い込まれるほどの打撃を受ければ、社会的相当性を欠く行為と認定される可能性が高まります。
実例として、ある判例では引き抜き直後に売上高・粗利益が著しく落ち込んだことを重視し、「引き抜きがなければ得られたはずの利益」と実際の利益との差額が損害として認められました。このように、引き抜き行為と時を同じくして経営に深刻な悪影響が現れている場合には、引き抜きとの因果関係が推認され違法性が認められやすいのです。
逆に言えば、会社側が「引き抜きによる損害」を立証できない場合には損害賠償は認められません。後述するように、引き抜きと損害との因果関係の立証は重要ポイントとなります。
要件2:引き抜いた側に「故意・過失」があったこと
次に、違法な引き抜きを行った加害者側の主観的な非(責任)が問われます。民法上の不法行為で損害賠償責任を追及するには、加害者に故意または過失があることが必要です。一般に、計画的に同僚を誘い出す引き抜き行為は意図的(故意)に行われるものなので、この点はさほど問題にならないケースが多いでしょう。
ポイントは、誰が引き抜きの主体となって故意・過失を持っていたかです。たとえば在職中の社員Aが中心となって引き抜きを画策したならA本人が責任を負いますし、競合他社B社が裏で糸を引いていたならB社も故意による不法行為責任を問われ得ます。
元社員や元役員が黒幕となり複数の関係者を使って裏で引き抜きを計画したケースでは、関与した者全員が連帯して損害賠償責任を負うこともあり得ます。
一方、単に誘われて転職しただけの社員については、故意・過失がない限り責任を問われません。引き抜きに応じて転職した社員自身は「職業選択の自由」に基づき動いただけで、違法とされる行為をしていない可能性が高いためです。したがって、責任追及の相手は主に引き抜きを実行・主導した人物や企業となります。
要件3:引き抜き行為と会社の「損害」に因果関係があること
最後に、引き抜き行為によって会社に生じた損害と、その行為との間に因果関係があることを証明する必要があります。これは損害賠償請求において極めて重要なポイントです。
例えば、引き抜きによって売上が減少したとしても、その売上減少が純粋に人材流出のせいなのか、それとも景気悪化や他社台頭など別の要因が影響しているのかは慎重に見極められます。
裁判では、被告側から「業績悪化は引き抜きとは無関係な要因によるものだ」という反論がなされることもあります。そのため、引き抜きさえなければ生じなかった損害であることを客観的資料で立証することが欠かせません。
具体的には、以下のような損害項目と因果関係を主張・立証するケースがあります。
- 売上・利益の減少分:
中核社員を失った結果、業務効率や営業成績が落ちて売上が減少した場合、その減少額を損害として請求できます。特に、引き抜き直後に顕著な売上落ち込みがあれば、因果関係が認められやすいでしょう。 - 顧客流出による損失:
引き抜かれた社員が担当していた優良顧客が競合に移ってしまった場合、その顧客から得られていた利益相当分も損害になります。これは営業秘密や顧客リストの不正利用にも絡む部分です。 - 逸失利益:
引き抜かれた社員が今後も在職していれば将来得られるであろう利益、いわゆる逸失利益も請求可能な場合があります。例えば、引き抜きがなければ達成できたはずの売上目標との差額などです。 - 採用・育成コスト:
引き抜かれた社員をこれまで教育し戦力化するのに費やしたコストも損害として主張し得ます。具体的には研修費用や資格取得補助などの投資分です。 - 代替要員の確保費用:
抜けた人材を補充するために要した求人広告費、人材紹介料、引き継ぎの残業代なども、違法な引き抜きが原因で発生した追加コストとして請求が認められる場合があります。
注意すべきは、こうした各損害が引き抜き行為によって生じたと因果関係を証明することです。例えば売上減少を損害とするなら、「引き抜かれたAさんがいれば受注できていたはずの案件を失った」等の具体的因果関係を示す必要があります。不十分な立証だと損害賠償請求が認められないリスクが高くなります。
読んで少し胸が軽くなりましたが、因果関係の立証が不安です。何かできることはありますか?
まずは因果関係を集めるために証拠を集めることが重要です。因果関係の証明には法的知識も必要となるため、専門家への相談も検討が必要です。
【裁判例】引き抜きの損害賠償額はいくら?認められた判例・棄却された判例
実際に、引き抜きトラブルで損害賠償請求が争われた裁判では、認められたケースと棄却されたケースがあります。過去の判例から、どのような事情が勝敗を分け、いくら程度の賠償額が命じられているのかを見てみましょう。
損害賠償が認められた裁判例と勝訴のポイント
【当法人対応実績】在職中に派遣スタッフを引き抜き約300万円の賠償が認められた事例
この事例は当法人の弁護士が担当した事例です。
X社は人材派遣会社で、就業規則において従業員の在職中および退職後の競業行為を禁止していました。しかし、宮崎市内の営業所に勤務していた課長職の従業員Y1は、在職中の平成30年5月に同業の派遣会社Y2社を密かに設立し、同年6月にX社へ退職届を提出、8月に退職しました。
Y1は退職届提出後、X社の派遣スタッフ数名に対し「X社には内緒で動いてくれ」「全て話を付けているので安心してきてほしい」と誘いかけてY2社への転職を勧誘し、派遣先企業にも「スタッフの移籍はX社も了承済み」であるかのように説明していました。
その結果、派遣スタッフらは派遣先企業は変えずに派遣元のみX社からY2社へ移籍し、X社は当該スタッフの派遣料収入を失うなど大きな影響を受けました。実際、引き抜き前後でX社の売上も減少しており、この引き抜き行為がX社に与えた打撃は非常に大きいと認められています。
他方、X社は上記Y1の行為に対する措置として、派遣先企業や派遣スタッフに対し「Y1らが重大な非違行為(違法な引き抜き行為)を行った」「Y1を懲戒解雇した」「顧客情報や個人情報を無断で持ち出して利用した」などと記載した書面を配布しました。
その後、X社はY1およびY2社に対し「在職中の引き抜き行為は違法だ」として損害賠償を本訴提起し、逆にY1らも「X社の書面配布は名誉・信用毀損にあたる」としてX社を相手取り損害賠償請求の反訴を提起しました。
裁判所の判断:
宮崎地方裁判所都城支部(2021年4月)では、Y1による引き抜き行為が「単なる転職の勧誘の範囲を超えた社会的相当性を逸脱する違法な引き抜き」と認定され、因果関係のある損害として約3か月分の派遣料相当額である約300万円の支払いがY1およびY2社に連帯して命じられました。
また同時に、X社が行った書面配布についても違法な名誉毀損行為と判断され、X社に対しY1個人への慰謝料70万円およびY2社の無形損害100万円(計約170万円)の支払いが命じられています。
法的根拠として、Y1については雇用契約上の誠実義務(競業避止義務)違反および民法709条の不法行為責任が問われ、Y2社についても同業他社の従業員引き抜きによる共同不法行為責任が認められました。
さらに、X社の書面配布行為については公共性・公益目的もなく真実性も認められないため違法性阻却事由がなく、名誉毀損による不法行為責任が成立しています。
勝訴のポイントとしては、以下のような物があげられます。
- Y1が在職中に計画的に競合会社を立ち上げて自社の派遣スタッフを引き抜いた
- 派遣先企業を変えず派遣元のみを切り替えることでX社に直接的な損害を与えた
- 「会社公認である」と偽って人材と取引先を欺く悪質な勧誘手段が用いられた
これらの事情が総合考慮され、本件引き抜き行為の違法性と損害との因果関係が明確に認められました。
【ケース】役員による集団引き抜きで約1,000万円の賠償が認められた事例
自社の役員が在職中から部下を誘い、一斉退職して競合他社に移ったというケースです。具体的には、ある営業部門の責任者だった役員Yが在職中に密かに計画を進め、自部署の多数の社員(数十名規模)がYとともに退職して新たな会社に合流しました。
その結果、元の会社X社は主要人材の一挙流出で事業継続が困難となり、売上も急減する事態に陥りました。
裁判所の判断:
東京地方裁判所(1996年12月)では、この引き抜き行為が「社会的相当性を逸脱する違法な引き抜き」と認定され、約1,500万円の損害賠償支払い命令が下されています。法的根拠は、役員Yについては会社法上の忠実義務違反および民法709条の不法行為、引き抜き先の競合会社についても不法行為の共同不法行為責任が問われました。
勝訴のポイントは、上述したように在職中の計画的・大量引き抜きであり、退職前から会社の経営体制を批判して社員の不安を煽るなど悪質な勧誘手段があったことです。これらの事情が総合考慮され、違法性と因果関係が明確に認められました。
引用:https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/06991.html
なぜ?損害賠償請求が棄却された裁判例
一方で、会社側が引き抜き行為だとして損害賠償請求を行っても、違法性が認められず棄却される場合もあります。その典型は、「通常の転職勧誘の範囲内」と判断された事例です。
例えば、元社員が同僚1~2名に「うちの会社に来ないか」と声をかけ、結果的に数名が順次転職したというケースでは、特に秘密裏の計画や悪質な手段もなく、会社への影響も一時的であったとして違法とは認められませんでした。
裁判例でも「単なる転職の勧誘に留まる場合には違法ではない」との立場が取られており、たとえ複数の社員が転職して一時的に会社に損失が出ても、それは企業が甘受すべきものとされています。
棄却例のポイントは、引き抜きと呼べるほどの背信性・計画性が立証できないことにあります。つまり「誘われた社員が自主的に辞めただけ」「勧誘もオープンに行われており不当な手段ではなかった」「会社業績への決定的な打撃とまでは言えない」といった事情が揃うと、社会的相当性を逸脱した違法な引き抜きとは評価されにくくなるのです。
経営者としては悔しい状況ですが、違法と合法のボーダーラインは案外高いハードルにあることを認識しておく必要があります。
損害賠償額の算定方法|逸失利益や採用・育成コストが考慮される
違法な引き抜きに対して損害賠償請求が認められる場合、賠償額はどのように算定されるのでしょうか。基本的には前述のとおり、会社が被った経済的損失がそのまま損害額となります。具体的な算定項目としては以下のようなものが考慮されます。
- 減少した売上高や利益:
引き抜き後に業務効率低下や顧客流出で売上・利益が減少した分は、そのまま損害額となり得ます。判例では「引き抜き後に挙げられたであろう利益」と実際の利益との差額が認定された例があります。ただし、減少分すべてが認められるわけではなく、退職した社員の人件費分など出費が減った分は差し引かれるといった調整も行われます。 - 逸失利益:
引き抜かれた社員が継続勤務していれば得られたはずの将来利益も、立証できれば損害額に含められます。例えば営業社員であれば、引き抜きがなければ今後獲得できたであろう契約分の利益などです。 - 顧客喪失による損害:
引き抜きにより流出した顧客の売上分も損害算定の対象です。その社員が担当していた主要顧客を競合に奪われた場合、その顧客から得ていた利益相当額を請求できます。 - 採用・教育コスト:
該当社員の採用にかかった費用(求人広告、人材紹介料など)や、研修・教育に投下したコストも損害に含められる場合があります。会社が投資した人材育成コストを一瞬で無にされた形になるためです。 - 代替要員の確保費用:
違法な引き抜きで欠員が生じた穴を埋めるために新たに採用活動を行った費用や、派遣社員・アルバイト等で一時的に補った人件費なども、損害として主張し得ます。
これらの算定項目から総損失額を積み上げて請求する形になります。ただし繰り返しになりますが、その損害が引き抜き行為によって発生したことの証明(因果関係の証明)が必要です。例えば不況の影響で売上が落ちていた部分まで引き抜きのせいにして計上してはいないか、慎重な検討がなされます。
裁判官にとっても損害額の判断は難しい部分であり、主張の根拠が不明確だと過大請求とみなされて減額・棄却されることもあります。
参考:
裁判例では、引き抜きによる売上減少を損害と認める一方、「会社側の後任育成不足など会社自身の要因による損失部分は考慮すべき」として会社請求が斥けられた論点も見られます。このように、損害算定では会社側にも落度がなかったか検討され、請求額がそのまま認められるとは限らない点に注意が必要です。
1,000万の賠償が認められた例もあるんですね。ただ、通常勧誘は違法でない点が不安です。
時系列で状況を確認し、事業影響と証拠を整理し、因果関係と損害算定を行う必要があります。専門家に相談して自社の状況が該当するか確認してみましょう。
【弁護士が解説】引き抜きで損害賠償を請求する基本ステップ
違法性の立証ポイントが見えてきたところで、実際に引き抜きが発生した場合に企業が損害賠償請求に踏み切るまでの手順を確認しましょう。弁護士の視点から、スムーズかつ効果的に請求を進めるための基本的なステップを解説します。
ステップ1:何よりもまず「証拠」を確保する
引き抜き被害に気づいたら、最優先すべきは証拠の確保です。引き抜き行為は往々にして水面下で行われるため、後から違法性を主張するには客観的な証拠を押さえておく必要があります。証拠が不十分なままでは、いくら被害を受けても裁判で認められないリスクが高まります。
集めるべき証拠の具体例
- メールやチャットの履歴:
引き抜きの勧誘に関わるメッセージ(社内メールやSNS上のやり取りなど)が残っていれば重要な証拠です。日時や内容から、誰が誰を誘ったか、在職中から計画していたかなどを裏付けることができます。 - PCデータ・書類:
引き抜き実行者が会社の顧客リストや機密情報を持ち出していないか調査しましょう。USBメモリへの不正なデータコピー履歴、印刷物の持ち出し履歴など、社内規程違反や不正競争防止法違反を示す証跡は厳しく追及できます。 - 関係者の証言・ヒアリングメモ:
引き抜かれた従業員や周囲の社員から事情を聴取し、可能であれば陳述書など文書にまとめておきます。第三者の客観証言は裁判でも信用力が高いため、協力を得られるようであれば確保してください。 - 業績や取引先からの反応:
引き抜き後に売上が急減したデータや、取引先から「担当者がいなくなって困る」といったクレーム・連絡の記録も立派な証拠です。損害と因果関係を示す資料として有用です。 - 人材紹介会社等とのやり取り記録:
転職あっせん業者が介在している場合、その業者とのメールや契約書類から競合企業と結託していないか探ることもできます。
これらの証拠は、引き抜き行為の存在自体の立証だけでなく、行為の悪質性(計画性や背信性)、さらに損害との因果関係を証明する上でも重要です。証拠の入手は時間との勝負でもありますから、可能な限り早急に動きましょう。
ワンポイント: 退職者の業務用PCやメールアカウントは、社内規程で適法に調査できるよう整備しておくと安心です。退職直後に証拠データを確保できれば、後から証拠隠滅されるリスクを減らせます。
ステップ2:内容証明郵便で交渉のテーブルにつかせる
証拠が揃い、違法な引き抜きである程度の見通しが立ったら、まずは加害者側に損害賠償に応じるよう促す交渉を試みます。その際に有効なのが内容証明郵便による通知です。
内容証明郵便を送る目的
- 公式な形で違法行為を指摘し、賠償請求の意思を示す:
内容証明郵便は郵便局が「誰が・いつ・どんな内容を相手に送ったか」を証明してくれる制度です。これを利用して、「あなたの行為は○○の理由で違法な引き抜きに当たる。○○万円の損害賠償を請求する。○月○日までに回答せよ」といった通知を送ります。公式文書で通知することで、相手に心理的プレッシャーを与え、安易に無視できない状況を作ります。 - 交渉のテーブルにつかせる:
内容証明を送りつけられると、相手も弁護士に相談せざるを得なくなり、本格的な交渉モードに入ります。以後のやり取りでこちらの被害回復に向けた話し合いが始まるきっかけになります。場合によっては、この段階で示談(金銭解決)が成立することもあります。 - さらなる引き抜きへの牽制:
通知書には「これ以上の違法行為をただちに停止せよ」という要求も盛り込みます。今まさに他の従業員への勧誘工作が続いているような場合、内容証明の送付は強力なけん制になり得ます。
内容証明に記載すべき事項
基本的には「違法行為の指摘」「請求趣旨(根拠法令と賠償額)」「損害発生の経緯と算定内訳」「回答期限」「再発防止要求」といった内容を盛り込みます。法律の専門知識が必要な文面になるため、弁護士に作成を依頼するとよいでしょう。
ステップ3:交渉が不調なら訴訟(裁判)を提起する
内容証明による交渉を行っても、相手が賠償に応じない、話し合いが決裂するといった場合には、最終手段として訴訟提起に踏み切ります。裁判所で正式に違法性と損害を認めてもらい、強制的に賠償金を回収するプロセスです。
訴訟提起のポイント
- 提訴にあたっては、これまで収集した証拠を整理し、違法性(前述の要件1)・故意過失(要件2)・因果関係(要件3)をきちんと主張立証できる内容の訴状を作成します。誰に対してどの法的責任を追及するか(不法行為か債務不履行か、共同不法行為かなど)も法的検討が必要です。
- 訴訟では相手も弁護士を立てて争ってくるため、証拠に基づいた主張の一貫性が重要です。「引き抜きなどしていない」「損害は会社の思い過ごしだ」などと反論される点を予測し、反証も用意しておきます。
- 判決までの期間、和解の機会もあります。裁判上の和解で相手に一定の支払いを約束させ、機密情報の使用禁止や接触禁止の取り決めを結ぶことで早期解決を図ることも可能です。和解が成立しない場合は判決を仰ぎ、最終的な決着をつけることになります。
なお、引き抜き事案の訴訟は事実関係が複雑になりやすく、判決まで時間がかかる傾向があります。証人尋問なども必要となれば1年以上の長期戦も想定されますので、提訴の決断は会社方針として慎重に行いましょう。
もっとも、違法な引き抜きによる深刻な被害を受けた場合、泣き寝入りせず裁判で権利救済を図ることは正当な経営判断です。専門家の助言を受けつつ、然るべき措置を取ることが大切です。
少し見通しが持てました。やはり最初は、証拠を集めることが大切なんですね。
その通りです。まずメール・チャット等の証拠と業績データを時系列で整理して、並行して内容証明の文案を作り、交渉と和解の余地も検討します。
【状況別】在職中・退職後で異なる請求のポイントと実務対応
引き抜き行為への対処や法的請求の考え方は、その引き抜きを行った人物が自社に「在職中」か「退職後」かで若干異なります。労働法制上の義務関係が変わるため、それぞれの状況に応じたポイントと実務対応を押さえておきましょう。
従業員が「在職中」に引き抜きを行っている場合
自社に籍を置いたまま、内部の従業員や顧客を引き抜く行為が発覚した場合です。在職中の従業員は会社との間で雇用契約が存続しており、法律上会社に対する誠実義務(信義則上の義務)を負っています。このため、在職中に会社の利益を損なう引き抜きを行うことは就業規則の有無にかかわらず許されないと解されています。
主な法的根拠は「誠実義務違反」
在職中の従業員による引き抜きに対して会社が損害賠償請求を行う場合、根拠となるのは労働契約上の誠実義務違反です。雇用契約には付随義務として「使用者(会社)の正当な利益を不当に侵害してはならない義務」が含まれると解釈されており、在職中に同僚や顧客を引き抜いて会社に損害を与える行為はこの義務に反します。
平たく言えば「勤めて給料をもらっているうちは、裏切り行為をして会社に損害を与えてはいけない」ということです。
法律上は、民法上の債務不履行(労働契約違反)として追及する形になります。また同時に、引き抜き行為自体を不法行為(民法709条)と位置付けて損害賠償請求することも可能です。判例上も、在職中の引き抜きについては債務不履行責任および不法行為責任の両面が認められるケースがあります。
実務対応:
在職中の従業員が引き抜きに関与している疑いがある場合、まずは就業規則や誓約書で定めた社内ルールに基づいて懲戒処分等を検討します。就業規則に「引き抜き行為の禁止」が明記されていれば、当該社員に対し訓戒・減給・懲戒解雇など適切な処分を科すことも視野に入ります。
社内処分と並行して前述の証拠確保を行い、損害が発生していれば在職中の加害社員本人および加担者に損害賠償請求を行います。
就業規則等の社内規程への記載
在職中の引き抜きトラブルに備えるには、事前の社内規程整備が極めて重要です。【予防策】の項でも述べますが、就業規則に「在職中は同僚や顧客の引き抜きをしてはならない」旨の規定を置いておくことで、社員に対し引き抜き禁止義務を明確に認識させることができます。
また入社時に誓約書(同意書)を取り交わし、「在職中および退職後一定期間は自社の従業員・顧客を勧誘しない」と約束させておくことも有効です。
こうしたルールがない場合、仮に引き抜き行為が発覚しても社内的に懲戒処分ができず、抑止が利かない恐れがあります。逆に規程があれば「あなたは規程○条に反する行為をした」と堂々と主張でき、処分や法的措置に踏み切りやすくなります。就業規則への明記と誓約書の徴収はリスクマネジメントとして是非整えておきましょう。
元従業員が「退職後」に引き抜きを行った場合
既に退職した元社員が古巣の同僚や顧客を引き抜くケースです。退職後の元社員については、在職中とは異なり雇用契約上の誠実義務や競業避止義務といった拘束は基本的にありません。したがって、退職後に同業他社へ転職すること自体は自由ですし、元同僚に声をかけて自社に誘う行為も直ちには禁止されていません。
しかし、退職後であっても社会的相当性を著しく欠く方法で引き抜きを行えば、不法行為として損害賠償責任を問われる可能性があります。前述の要件1の判断基準(人数・地位、方法の悪質性、影響の大きさ)は、実は在職中か退職後かで大きく変わらず適用されます。
裁判例上も、元社員による引き抜きでも在職中とほぼ同様の基準で違法性を判断する傾向にあります。
ただし、実務的な対応としては退職時の取り決めがカギを握ります。つまり、退職に際して元社員とどのような誓約や契約を交わしていたかが重要になるのです。
主な法的根拠は「誓約書違反」
元社員による引き抜きに対抗する法的根拠として有力なのが、退職時の誓約書(同意契約)の違反です。多くの企業では退職時に秘密保持や競業避止、引き抜き禁止に関する誓約書に署名させています。
この中で「退職後○年間は自社の従業員を勧誘しない」といった引き抜き禁止条項を設けておけば、元社員がそれを破って引き抜きを行った際に契約違反(債務不履行)として損害賠償請求が可能となります。
例えば、コンサル会社の引き抜き事件では、退職する役員に「1年以内の引き抜き禁止」を誓約させ、違反時は違約金として引き抜いた社員の前年年収相当額を支払うという条項が設定されていました。
裁判ではこの誓約書が重視され、違反した元役員に対し予定されていた損害額(引き抜かれた社員4名の年収合計約4,200万円)の賠償責任が認定されています。
このように、誓約書で事前に損害額まで取り決めておくと、いざという時に非常に強力な武器になります。一方、誓約書がない場合は、元社員の行為そのものを不法行為として立証する必要がありハードルが上がります。
ただし誓約書がなくても、社会通念上あまりに悪質な引き抜きであれば不法行為責任は追及可能です。つまり、退職後でも要件1~3が揃えば損害賠償請求は可能ですが、誓約書があればより確実・円滑に請求できるというイメージです。
退職時に交わした誓約書の「引き抜き禁止条項」が鍵
実務対応として最も重要なのは、退職時(または入社時)に引き抜き禁止の誓約書を取り交わしておくことです。引き抜き禁止条項では通常、「退職後○年間は在職時の同僚や部下を自社(または関連会社)に勧誘しないこと」「違反した場合は○○万円の違約金を支払うこと」などを定めます。これに元社員が署名すれば契約が成立します。
注意点として、退職時になって急に誓約書を書かせようとしても本人が拒否するケースがあります。理想的には入社時に同様の契約を結んでおく方が確実です。入社段階であれば「御社に尽くします」という意思のもと契約してもらいやすいためです。一方、社員数が多い企業では個別の誓約書管理が大変な場合もあるでしょう。
その場合は就業規則に引き抜き禁止を明記し、社員全員に網をかける方法も有効です。就業規則への明記によって、全従業員に対して包括的に引き抜き禁止の効力を及ぼすことができます。
退職後の引き抜き防止策としては、競業避止義務や秘密保持義務とセットで誓約書を作成するのが一般的です。弁護士に依頼すれば、法改正にも対応した適法な誓約書を準備できます。逆に不備のある誓約書だと無効主張を許しかねませんので、専門家のチェックを受けておくと安心です。
ポイント:
元社員による引き抜きは、在職中と比べて違法と認定されるハードルがやや高いものの、組織的・計画的に行われた場合には違法性が高まると判示されています。特に経営幹部クラスが絡むと元会社への打撃も大きいため、「退職後だからといって安心せず、誓約書などで縛っておく」ことが肝要です。
二度と起こさせない!将来の引き抜きトラブルを防ぐ3つの予防策
最後に、経営者が講じておきたい引き抜きトラブルの予防策を紹介します。一度痛手を被った以上、同じことを繰り返さない備えが必要です。法律面から取れる主な対策は次の3つです。
予防策1:入社・退社時の誓約書で「引き抜き禁止」を明記する
誓約書の活用は最大の予防策です。在職中および退職後の一定期間について、自社の社員や顧客を引き抜かないことを約束させる条項を盛り込みます。入社時にサインさせるのが理想ですが、難しければ退職時でも試みましょう。誓約書により社員一人ひとりと個別の合意を取っておくことで、「引き抜き行為は契約違反になる」との意識付けができます。
誓約書には競業避止義務(退職後に競合他社へ就職しない)や秘密保持義務も合わせて記載し、包括的にリスクをカバーします。違反時のペナルティ(違約金や損害賠償額の予定)も定めておけば抑止力が高まります。これにより、万一引き抜きが発生しても契約違反としてスムーズに責任追及できる土台が築けます。
備えあれば憂いなし:
誓約書作成には法律上の配慮が必要です。契約自由とはいえ、内容が労働者に一方的に不利すぎると公序良俗違反で無効となる恐れもあります(競業避止の期間が長すぎる等)。専門家の助言を得て、法的に有効でバランスの取れた誓約書を用意しましょう。
予防策2:就業規則に「競業避止義務」を具体的に定める
就業規則への明文化も有力な予防策です。就業規則に、「在職中はもちろん退職後も○年間は競業会社への転職や自社社員の引き抜きを禁止する」旨の規定を設けます。就業規則で定めれば、従業員全員に対し一律に効力が及ぶため、個別誓約書より手間がかからず確実です。
ポイントは、その規定を具体的かつ周知徹底することです。「引き抜き禁止」の文言を明示し、新入社員研修や社内研修等でしっかり周知することで、社員の意識づけが図れます。万一違反者が出た場合も、「規則違反」として懲戒処分でき、社内統制上も対処しやすくなります。
もっとも、就業規則の変更には労働者代表への意見聴取など一定の手続きが必要です。労働契約法の就業規則変更ルールに則って進める必要があるため、この点も弁護士等専門家に相談するとよいでしょう。
予防策3:企業秘密の管理と秘密保持契約を徹底する
情報流出を防ぐことも、引き抜き予防の観点で重要です。社員が大量離脱する際、顧客リストやノウハウが持ち出されれば、取引先ごと競合に奪われるリスクが高まります。そこで、平時から秘密情報の持ち出し防止策を講じ、退職時には秘密保持契約を再確認する運用を徹底しましょう。
具体的には、社内システムでUSB等外部媒体へのデータ持ち出しを制限したり、退職者にPCを提出させログを確認するルールを設けます。また、退職手続時に「顧客データ等を使用しない」旨の念書を取ることも有効です。
加えて、不正競争防止法により営業秘密の不正利用は刑事罰を伴う違法行為であることも社員に周知しておきます。法律違反にもなり得ると伝えることで、安易な情報持ち出しや引き抜きの誘発を思いとどまらせる効果が期待できます。
このように人と情報の両面からガードを固めることが、引き抜きトラブルの発生確率を下げるカギとなります。
誓約書と就業規則で再発防止できそうで少し安心です。ただ記載内容や、周知の仕方はどこまでが妥当でしょう?
期間は必要最小限、対象と地域を限定するなど検討も必要です。業種と体制も考慮した上で作成・周知を行っていきましょう。
従業員の引き抜きに関するよくあるご質問
どうやって「違法な引き抜き」と普通の転職勧誘を見分ければいいですか?
以下の要素が複数当てはまる場合、「違法な引き抜き」と判断される可能性が高まります。
人数と地位: 会社の中心的な役割を担う従業員が、複数名まとめて引き抜かれた場合。その結果、事業の継続が困難になるほどの打撃を受けるケース。
計画性と背信性:従業員が在職中から秘密裏に引き抜き計画を進めていた。顧客情報や人事情報といった会社の内部情報を不正に利用して勧誘した。「会社の将来が不安だ」とデマを流すなど、悪質な手段で勧誘した。
影響の大きさ: 引き抜きによって、会社の売上や利益が大幅に減少し、事業の縮小を余儀なくされるなど、経営に深刻な損害が出た場合。
これらの点を総合的に考慮し、単なる転職の範囲を超え、会社の経営に重大な支障を及ぼすような悪質なケースが「違法」と判断されます。
いつ弁護士に相談するべき? 社内調査の前でも大丈夫?
従業員の引き抜きの被害に気づいた、あるいはその疑いが生じた時点で、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
社内調査を始める前や、調査と並行して相談することで、以下のようなメリットがあります。
適切な証拠収集のアドバイスを受けられる: どのような証拠が法的に有効か、どうやって集めればよいかについて専門的な助言を得られます。これにより、後々の交渉や裁判を有利に進めることができます。
初期対応を誤らない: 感情的な対応は、かえって自社が不利になる(名誉毀損で訴えられるなど)リスクもあります。法的な観点から、冷静かつ適切な初動対応が可能になります。
今後の見通しが立てやすくなる: 自社の状況が法的に「違法な引き抜き」に該当する可能性はどの程度か、損害賠償請求は可能かといった見通しを立てることができます。
損害賠償請求の鍵となる「因果関係の証明」には法的な知識が不可欠なため、問題が発覚した初期段階で専門家に相談することが賢明です。
どうやって引き抜きの証拠を集めればいいの?
損害賠償請求を成功させるためには、客観的な証拠を確保することが最も重要です。集めるべき証拠の具体例は以下の通りです。
メールやチャットの履歴:引き抜きを計画・勧誘していることがわかる社内メールやSNS上のやり取り。日時や内容がわかるものが有効です。
PCのデータや書類:引き抜きを行った人物が、退職前に顧客リストや会社の機密情報をUSBメモリにコピーした履歴。会社の内部情報を印刷して持ち出した記録。
関係者の証言:引き抜きの勧誘を受けた他の従業員からのヒアリング内容をまとめたメモや陳述書。第三者の証言は信用性が高いと判断されやすいです。
業績データや取引先からの連絡記録:引き抜きが発生した直後に、売上が急激に減少したことを示す会計データ。「担当者がいなくなって困る」といった取引先からのクレームや連絡の記録。
これらの証拠は、引き抜き行為の悪質性や、それによって会社が受けた損害を具体的に証明するために不可欠です。時間が経つと証拠が失われる可能性もあるため、迅速に確保に動きましょう。
引き抜きによる損害額はどうやって計算するの?
損害額は、違法な引き抜き行為によって会社が被った経済的な損失を積み上げて計算します。主な算定項目は以下の通りです。
売上・利益の減少分:引き抜きによって業務が停滞したり、顧客が流出したりして減少した売上高や利益。引き抜きがなければ得られたはずの利益と、実際の利益との差額などが考慮されます。
逸失利益:引き抜かれた従業員が在籍し続けていれば、将来的に会社にもたらしたであろう利益。
採用・育成コスト:引き抜かれた従業員を採用するためにかかった求人広告費や、研修・教育にかけた費用。
代替要員の確保費用:抜けた穴を埋めるために新たに従業員を採用した際の求人費用や、一時的に派遣社員などを雇った人件費。
ただし、これらの損害がすべて引き抜き行為によって生じたものであるという因果関係を証明する必要があります。例えば、売上減少が景気の悪化など他の要因によるものではないことを示す必要があります。そのため、請求した金額がそのまま認められるとは限りません。
まとめ|悪質な引き抜きには断固たる措置を。まずは企業法務の専門家にご相談ください
悪質な従業員の引き抜き行為に対しては、経営者として毅然とした対応が求められます。社会的相当性を逸脱した背信的な引き抜きであれば、泣き寝入りせず法的措置によって損害回復を図るべきです。
実際に違法な引き抜きが行われると、単に人材を失うだけでなく企業秘密の流出や優良顧客の奪取といった深刻な被害につながりかねません。被害を最小限に留め、引き抜き加害者に責任を負わせるためにも、証拠の確保や法的主張の準備を入念に行うことが重要です。
もっとも、引き抜き行為が違法と評価されるかの判断には専門的な知識が必要であり、損害賠償請求を成功させるには法的戦略が欠かせません。引き抜き被害に直面したら、まずは企業法務に詳しい弁護士に相談し、適切な対応策を検討するのが賢明でしょう。
専門家の助けを借りて断固たる措置を講じれば、会社の大切な人材と利益を守ることができるはずです。引き抜き問題でお悩みの経営者様は、ぜひ早めに信頼できる法律のプロにご相談ください。
監修者
弁護士法人グレイス企業法務部
- 本店所在地
- 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
- 連絡先
- [代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129 - WEBサイト
- https://www.kotegawa-law.com/
「問題社員対応(解雇・退職勧奨等)」の関連記事はこちら
お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら
電話で問い合わせる
0120-77-9014
受付時間:平日9:00-17:30
メールで問い合わせる
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!
メールでのお問い合わせは24時間受付中!