企業法務コラム
雇用契約書にみる雇止め・無期転換権
更新日:2024/08/27
東京・神戸・福岡・熊本・長崎・鹿児島に拠点がある弁護士法人グレイスの労働法コラムです。
今回のテーマは、雇用契約書にみる雇止め・無期転換権についてです。
今回は、雇用契約書の重要性についてお聞きしていきます。
雇用契約書は、雇用形態別に作成することが重要です。
雇用形態というと、正社員や契約社員、パート・アルバイトといった区分けのことですか。そもそも、パートとアルバイトって何が違うんでしょうか。
法律上は、いわゆるパート・アルバイトという区分けはなく、両方とも「短時間労働者」といいます。正社員や契約社員の方に比べて短時間の労働をすることからこう呼ばれます。
また、雇用期間の定めの有無で区分けすれば、正社員は、「無期雇用労働者(期間の定めのない労働者)」といい、契約社員やパート・アルバイトは、「有期雇用労働者(期間の定めのある労働者)」と呼ばれます。
パート・アルバイトの方は、有期雇用労働者のうち、時給制の方を指す場合が多いですね。
なるほど。つまり、パート・アルバイトは、短時間労働者でもあり、有期雇用労働者でもあるのですね。
厳密には、短時間労働ではなかったり、無期雇用のパート・アルバイトもありうるところですが、社会一般にはその認識で大丈夫です。
何故、雇用形態別に雇用契約書を作成することが重要なんでしょうか。あまり意識して作成することはない気がします…
例えば、正社員と契約社員で同じ契約書を使っていたとしましょう。そうすると、契約書から労働者がどちらの区分になるのかはわからないですよね。
そうすると、本当は契約社員なのに、正社員として見えてしまうことがあるということですか。
そのとおりです。そして、正社員は、期間の定めがありませんから、自己都合退職や解雇といった雇用契約の終了がない限り、雇用が継続します。
契約社員は、臨時の人手不足で採用する場合が多いですから、本来は、雇用期間の満了で終了するはずだったのに、意図せずして雇用契約が続いてしまうことになります。
それは困りものですね。
ところで、「雇止め」という言葉を聞いたことがありますか。
有期雇用の契約を更新せず、終了することでしょうか。
そのとおりです。契約社員といった有期雇用労働者だとしても、雇止めに関しては規制があります(労働契約法19条)。
長期にわたって反復して更新された契約で正社員と同視されるような勤務形態であったり、反復がなくとも労働者において契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由がある場合、雇止めは認められないことになります。
正社員と同視されるとか、契約更新の合理的期待がある場合というと、具体的にはどんなことが挙げられるでしょうか。
例えば、普段の業務内容に着目すると、正社員と契約社員の従事している業務が同じであるとか、雇用管理のうえで区別されていないといった側面がある場合は、要注意です。
契約の更新手続から見れば、契約更新手続が行われていない・形骸化している、契約更新が何度も行われて勤続年数が長い、他の労働者が更新されているのにその人だけ雇い止めされている等の状況も、注意が必要です。
あとは、会社側から長期雇用をほのめかす言動があった場合もそうですね。
たしかに、正社員と同じ業務をして、契約更新手続もないまま何年も経過していたら、労働者側からしても、いまさら雇止めするなんてという気持ちになってしまいますよね。
ですから、更新手続をして、雇用契約書を作成することが重要なのです。
更新期間の目安としては、半年~1年くらいの期間と思ってください。
単に「自動的に更新する」といった記載をして更新手続をしなかったり、更新の有無を示さないケースは、使用者にとっても労働者にとっても不測の事態を招きやすいですね。
契約更新の条件も示した方がよいのでしょうか。
さすが、いい着眼点ですね。具体的には、以下の条件で定めるとよいでしょう。
・ 契約期間満了時の業務量
・ 労働者の勤務成績/態度
・ 労働者の能力
・ 会社の経営状況
ちゃんと雇用契約書を作成しておけば、あとは安心ということですね
ちょっと待ってください。雇用契約書を定めるだけで満足してはいけませんよ。定めた基準に従って、きっちり運用しないと、更新手続の形骸化だと言われてしまいます。
おっと、そうでした。他にも注意した方がいいものはありますか。
特に注意した方がいいものとして、有期労働契約は、1回以上更新され、その通算期間が5年を超える場合、有期雇用労働者からの希望があれば、無期雇用になることは覚えておくべきでしょう(労働契約法18条)。
えっ!そうすると、契約社員の人が正社員になっちゃうんですか!
そう思うでしょう。勘違いしがちなのですが、契約社員だった頃と同一の労働条件での無期雇用になるので、すぐさま正社員と同一になるというわけではないのです。
なるほど。正社員と契約社員では、業務内容や配置転換が異なる場合がありますから、無期契約になるだけで条件が変更されるわけではないんですね。
無期転換といえば、定年後再雇用にも適用があることには注意してください。定年後再雇用とは、60歳での定年後、労働者が希望すれば継続して雇用する制度のことです(高年齢者雇用安定法9条1項2号)。
定年後再雇用ですか、意外です。
定年後再雇用は、1年更新の有期雇用社員とされるケースが一般的ですので、無期転換制度に該当しうるのです。
無期転換制度の適用を避けるにはどうしたらよいですか。
方法は2つあります。まず、第二・第三定年を設ける方法です。60歳を超えて無期転換した場合には65歳を定年にし、65歳を超えて無期転換した場合には70歳を定年にすると雇用契約書に記載しておくのです。
これはわかりやすいですね。
次に、雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局(労働基準監督署経由でも可)に提出して、認定を受ける方法があります(有期雇用特別措置法6条)。
しかし、この方法は継続雇用を対象とするものであるため、すり抜けが発生します。
例えば60歳定年の場合、55歳を回ってから有期雇用契約を締結した場合や、60歳を超えて有期雇用をした場合、継続雇用ではないため、適用がありません。
計画の作成も難しいため、あまり一般的な手法ではありません。
うーん、これだと結局のところ、第二定年を併用しなければならないような気がします。
雇用形態に即した雇用契約書を作成することの重要性が伝わりましたでしょうか。
最後に、令和6年に労働基準法が改正されましたので、今回ご説明した点についての影響があります。その点を説明します。まず、有期労働契約については、締結と契約更新のタイミングごとに、例えば「契約期間は通算4年を上限とする」「契約の更新回数は3回まで」といった記載をすることができるようになりました。このような運用をしたい場合には、雇用契約書・労働条件通知書に明確に記 載して事前に従業員に説明しておく必要があります。次に、無期雇用の転換権が発生した場合には、その時点で会社から対象となる従業員にその点を説明することが必要になりました。
有期雇用における雇止めと無期転換には注意して雇用契約書を作成する必要がありますね。法改正もありますので、その点を踏まえてしっかりと行うことも重要だということがよくわかりました。
監修者
弁護士法人グレイス企業法務部
- 本店所在地
- 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
- 連絡先
- [代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129 - WEBサイト
- https://www.kotegawa-law.com/



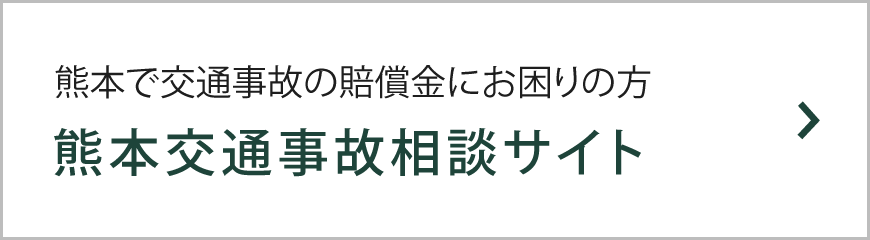


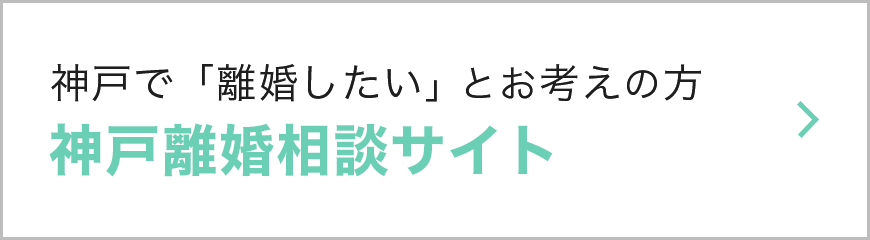
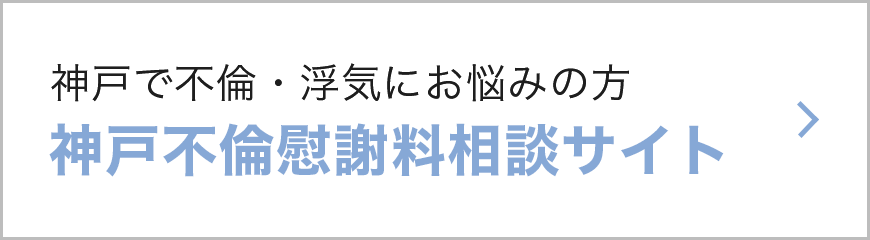



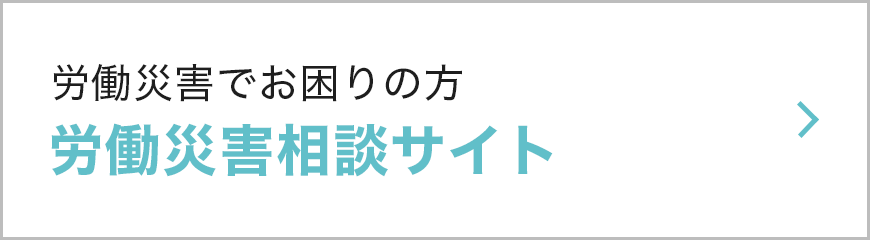
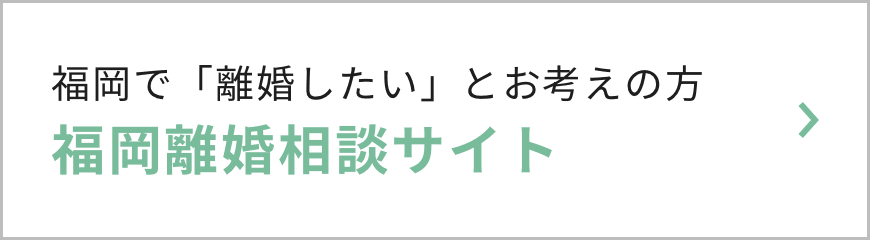
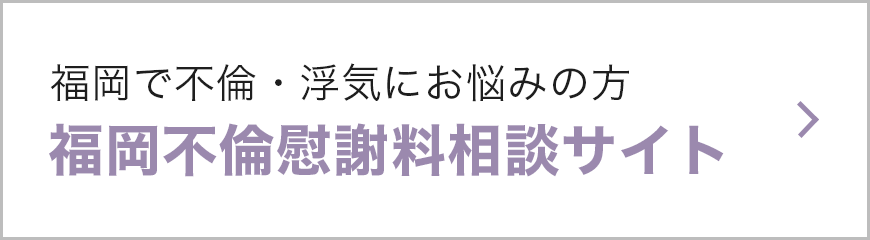
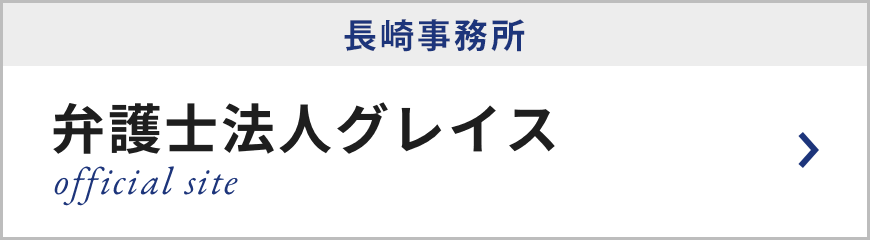

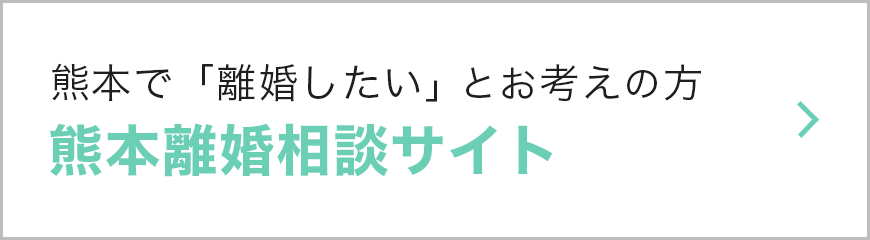
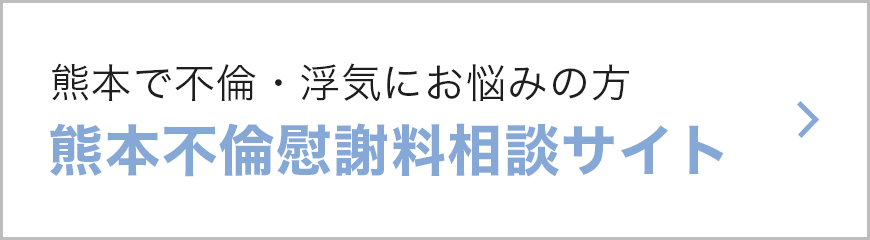






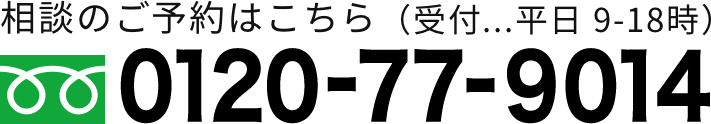
 メールでのお問い合わせはこちら
メールでのお問い合わせはこちら
