企業法務コラム
自筆証書遺言書保管制度について
更新日:2021/08/25

日々相続に関するご相談を多くいただいておりますが、十分に周知されていないなと感じる制度があります。
それは、令和2年7月10日から開始された「自筆証書遺言書保管制度」です。
自筆証書遺言は、自書さえできれば遺言者本人のみで作成することが出来るため、手軽で自由度が高く利便性が高いです。もっとも、遺言者本人が死去した後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされてしまう等といった問題が多くありました。
そこで、このような問題を解決するべく出来た制度がこの「自筆証書遺言書保管制度」になります。この制度は、簡単にいうと、自筆証書遺言書を法務局(遺言書保管所)に保管してもらうというものです。
法務局(遺言書保管所)において保管してもらうことにより、その原本とデータを長期間にわたり適正に管理することが出来るばかりか、相続開始後には、相続人等に遺言書の内容が確実に伝わるように、証明書の交付や遺言書の閲覧等も出来ます。さらに、自筆証書遺言の場合には必要な手続きである「検認」(遺言者の死後に相続人等が家庭裁判所において行わなければならない手続)も不要になります。
この「検認」も意外と知られていない手続なのでご説明すると、遺言書の保管者か遺言書を発見した相続人が、遺言者の死亡を知った後に、遅滞なく行わなければならない手続です。
具体的には、遺言書の保管者か遺言書を発見した相続人がその遺言書を家庭裁判所に提出した上で、後に裁判所から定められた期日(検認期日)において遺言書の形状や、筆跡が相続人のものかどうか、押印が相続人の印鑑によりされたものかどうか等を確認することになります。
この検認手続は、定められた申立書に必要事項を記載したり、遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本等といった必要書類を集めたり、期日に出頭したり(相続人全員が必ず参加しなければならないわけではありませんが、申立人は出席しなければなりません)等となかなかに手のかかる手続です。
そのため、今後はこの自筆証書遺言書保管制度を上手く利用することで、相続人等の手間や、余計な紛争を未然に防ぐことをおすすめいたします。
さらに詳しい制度のご説明や、遺言書の書き方等についてお悩みでしたら気兼ねなく弊所にご相談ください。

【著者情報】
播摩 洋平弁護士
企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)
九州大学大学院法学研究科修士課程 修了
米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業
三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務
プロフィールはこちら>>監修者
弁護士法人グレイス企業法務部
- 本店所在地
- 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
- 連絡先
- [代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129 - WEBサイト
- https://www.kotegawa-law.com/



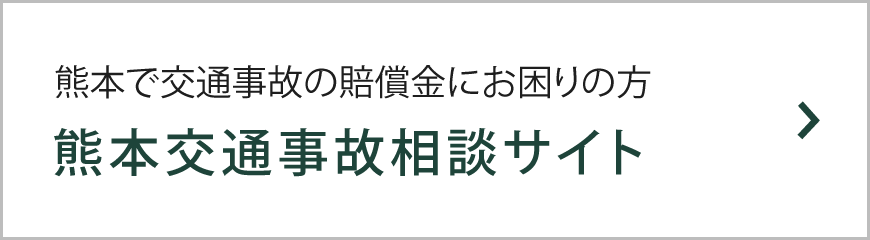


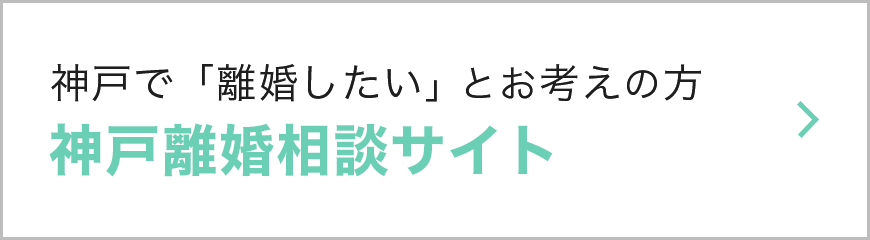
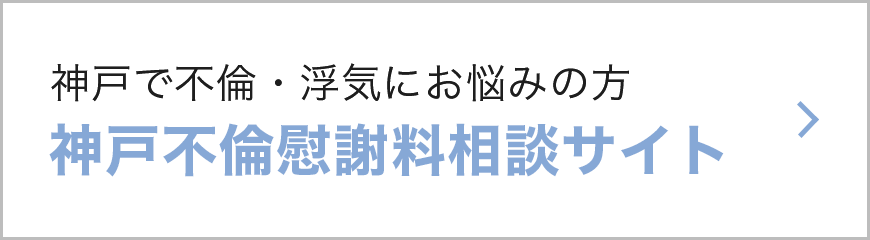



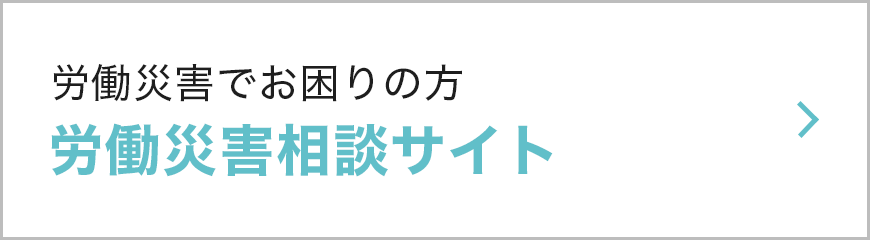
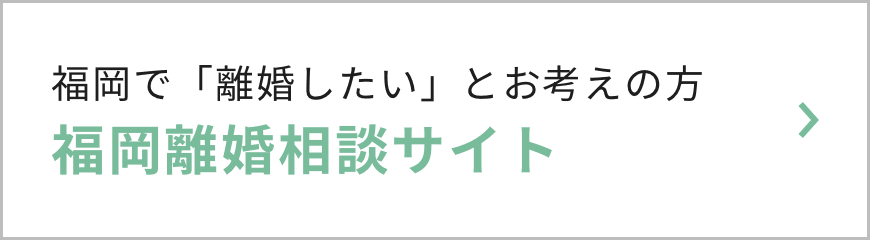
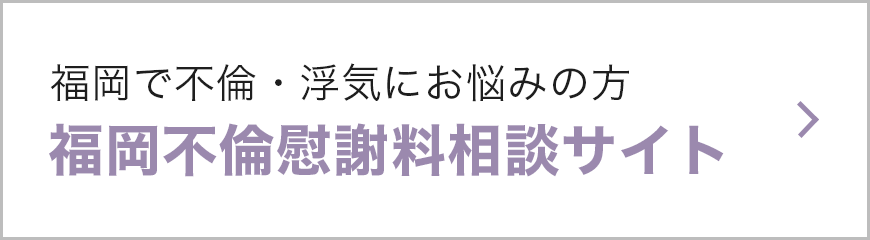
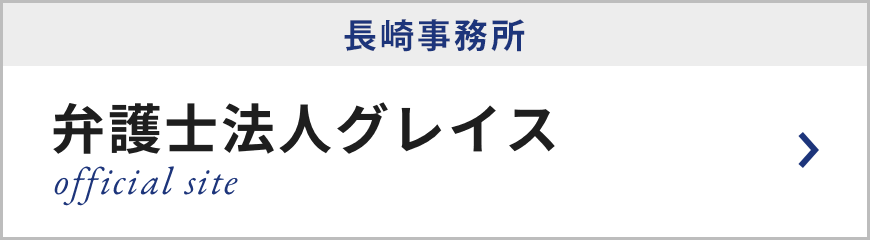

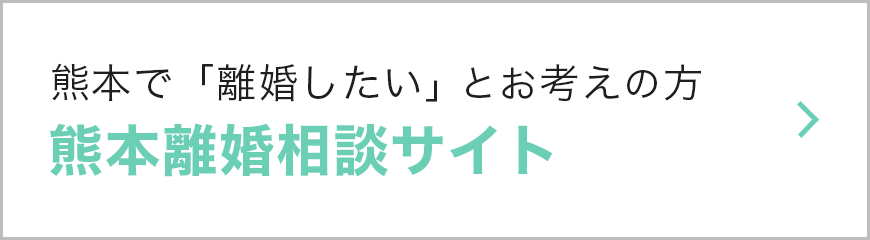
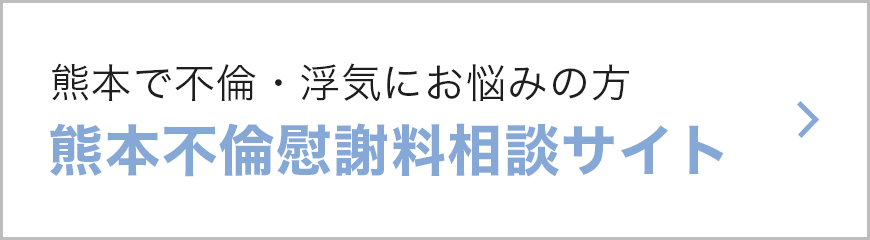





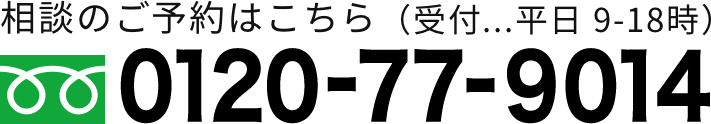
 メールでのお問い合わせはこちら
メールでのお問い合わせはこちら
