企業法務コラム
休業手当
更新日:2020/05/24
[ニュースレター77号掲載]
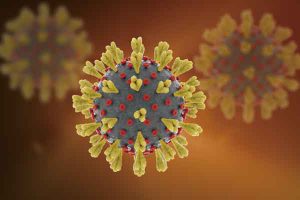
この原稿を執筆している現在、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が全国に発令されております。これに伴い、業種・業態を問わず、従業員を休業させる必要性に直面している方々が非常に多くなっております。そこで、今回はこの機会に休業手当について概観いたします。
休業手当とは、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合において、使用者が休業期間中、当該労働者にその平均賃金の6割以上の手当を支払わなければならないと労働基準法26条が定めており、同手当のことを指します。
そして、労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、感染が疑われる場合、あるいは発熱等で自主的に労働者が休む場合等につき、休業手当を支払うべきか否かという問題がクローズアップします。
厚生労働省によれば、労働者が新型コロナウイルスに感染し、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合には、休業手当を支給する必要がないとされています。
他方で、新型コロナウイルスの感染が疑われる場合において、使用者が自主的判断で休業させる場合には、休業手当を支払わなければなりません。すなわち、労働基準法26条に定める「使用者の責に帰すべき事由」がかなり広く解されており、使用者の政策的・自主的判断であった場合も「使用者の責めに帰すべき事由」に該当することになります。
もっとも、労働者が発熱や倦怠感等により自主的に休業することを申し出たような場合にまで休業手当を支給する必要はなく、その場合には通常の病欠と同様、欠勤扱いとするか、それぞれの就業規則に定められている休暇制度等で対応することになります。
更に、「休業手当」は法律上平均賃金の6割以上を支払うこととされていますが、これは少なくとも6割を払えば法律上の罰則(刑事責任)が使用者に課されないというにとどまります。すなわち、あくまで法律上は「6割以上」としているにすぎないため、個々の就業規則において「休業手当は6割とする」という定めがない場合には、直ちに「6割払えばよい」ということにはならないという点が重要です。
労働基準法は「労働刑法」の1つと言われており、刑事的処分を画する基準となっている諸規定が非常に多くなっております。
言い換えれば、就業規則や雇用契約の内容がそれを下回る内容であってはならないという基準にすぎません。これを機会に、就業規則上、休業手当についての定めがどのようになっているかを検証し、ご不明な点があれば当事務所までご相談いただきたく存じます。

【著者情報】
播摩 洋平弁護士
企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)
九州大学大学院法学研究科修士課程 修了
米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業
三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務
プロフィールはこちら>>監修者
弁護士法人グレイス企業法務部
- 本店所在地
- 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
- 連絡先
- [代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129 - WEBサイト
- https://www.kotegawa-law.com/



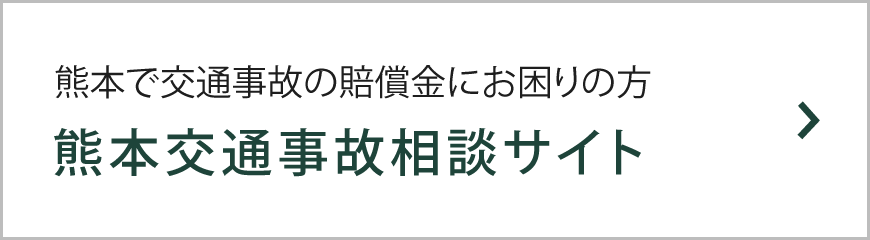


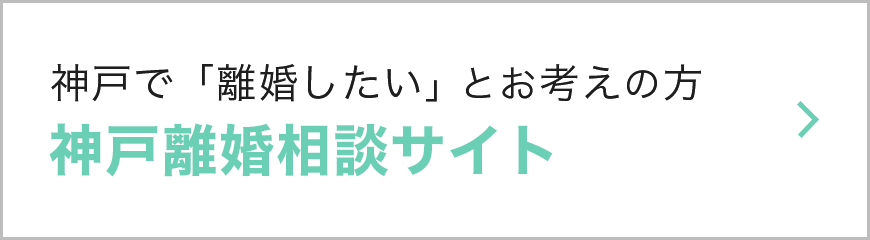
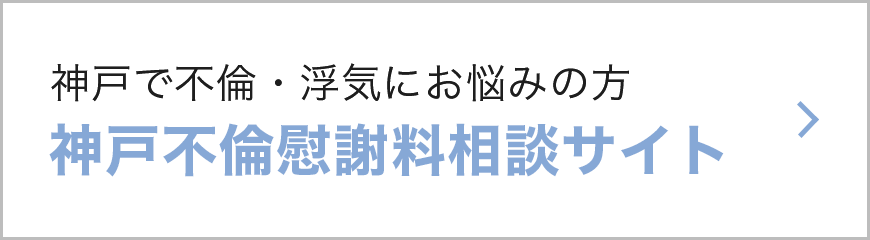



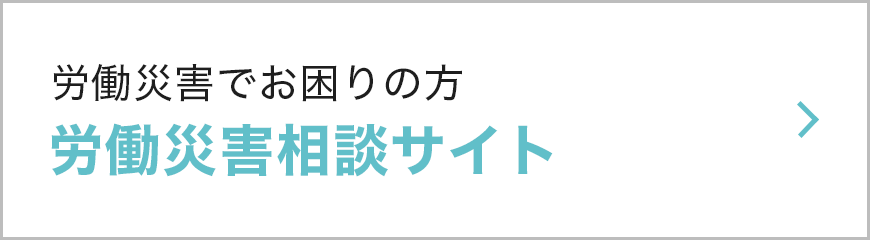
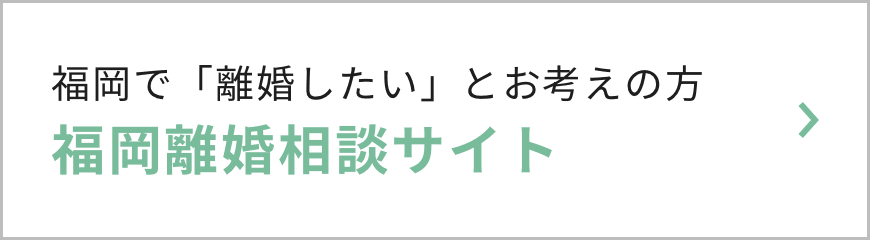
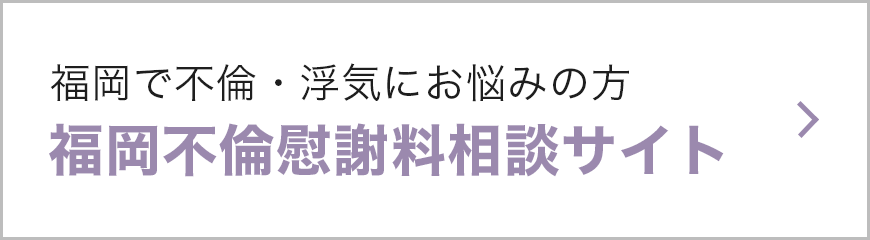
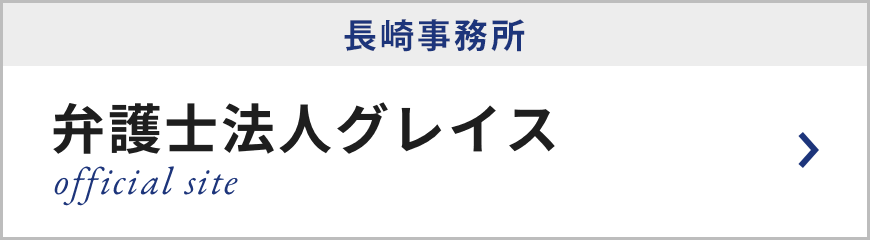

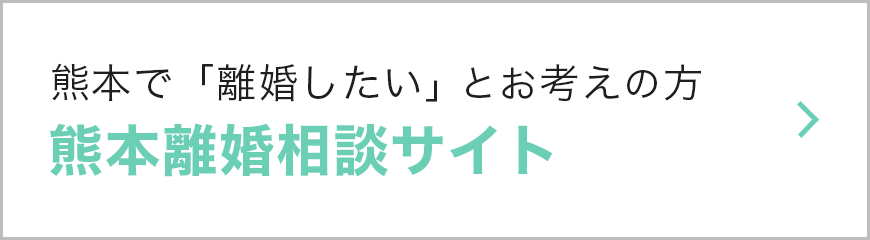
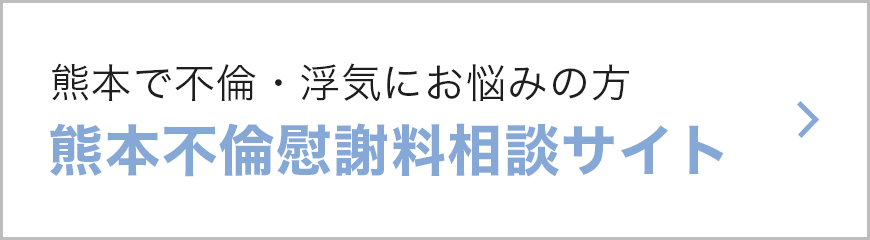





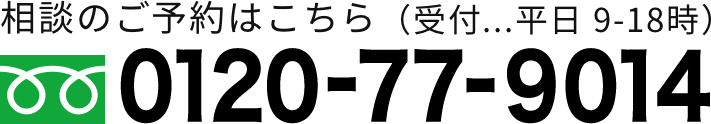
 メールでのお問い合わせはこちら
メールでのお問い合わせはこちら
