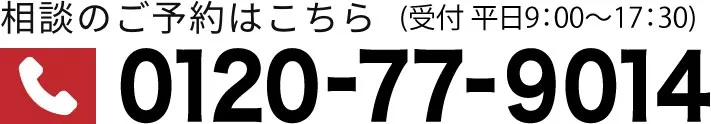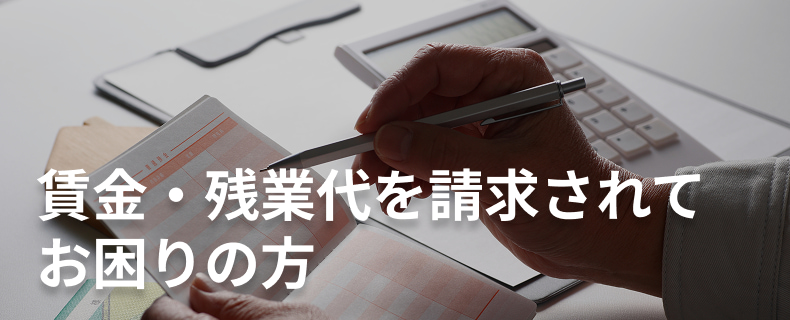企業法務コラム
「出勤停止とは?問題行動を起こした従業員に対する適切な懲戒処分の進め方」
更新日:2025/11/26
この記事をご覧になった方は、「出勤停止処分」についてどのようにご認識されているでしょうか?
実は、企業経営者の中には、出勤停止処分が懲戒処分であると知らない方も多くいらっしゃいます。逆に懲戒処分を検討する上で、いきなり懲戒解雇処分のみを検討されてしまう方も多くいらっしゃいます。
この記事では、不正行為や問題行動をした従業員に対し、懲戒処分としての出勤停止処分を下す際に必要な事項や、適切な進め方などについて解説していきます。
目次
出勤停止とは?
出勤停止とは、会社が従業員に対して、一定期間の出勤を禁じ、その間の給与を支払わないこととする懲戒処分です。解雇と異なって労働契約自体は継続しますが、従業員は労務提供ができず、会社もその受け入れを拒否する形になります。懲戒処分の中では比較的重い部類に入り、従業員に与える影響も大きいため、出勤停止処分を下す場合には、慎重な検討・対応が求められます。
出勤停止が認められるケースとは
出勤停止処分は、従業員の不正行為や問題行動に対して行われるものです。証拠から、その行為の具体的内容、悪質性、会社に与える影響がどこまで認められるかなどを総合的に考慮して、出勤停止処分が妥当かどうかが判断されます。
以下に、出勤停止処分が認められうる代表的なケースを3つご紹介します。
業務命令への重大な違反や無視
例えば、ある営業担当者が、上司からの顧客リスト共有指示を再三にわたって拒否し、さらにはその理由についても虚偽の説明を繰り返すため、何度も訓戒・譴責処分(始末書の徴求も含む。)を下している場合が挙げられます。
出勤停止処分よりも軽い業界書分では改善が見られず、業務遂行に著しい支障をきたし続ける場合には、組織の指揮命令系統を大きく乱しますから、出勤停止処分の対象となり得ます。
職場におけるハラスメント行為
また、職場で同僚に対して、度重なる性的嫌がらせ発言を行ったケースでも、出勤停止処分が認められ得ることとなります。被害者からの具体的な訴えや目撃証言があり、会社が事実関係を調査した結果、ハラスメント行為が認定された場合、出勤停止処分は当然検討されるべきです。
ハラスメントは職場環境を著しく悪化させ、会社の責任問題にも発展しかねない重大な違反行為です。このため、ハラスメント被害者との物理的距離を空けると共に、その後の異動などを検討する期間の接触を防ぐために、出勤停止処分が有効に機能します。
重大な内部情報・機密情報の漏洩に繋がる行為
例えば、経理部の従業員が、会社の極めて重要な機密情報である顧客データを、会社の許可なくUSBメモリにコピーして外部に持ち出そうとしたケースも出勤停止処分が検討されるべき事案です。
仮に持ち出し前に発覚したとしても、これは社内の情報セキュリティに対する違反行為であり、もし情報が外部に漏洩していれば会社に計り知れない損害を与えていた可能性があります。このような行為を取られた場合にも、当該従業員から内部情報へのアクセス権限を剥奪することや部署異動を検討・実施するために、出勤停止処分が有効となります。
出勤停止による給与と有給
会社として、出勤停止処分を行う際に最も気になるのが、従業員の給与と有給休暇の扱いでしょう。
給与
出勤停止期間中は、原則として給与は支払われません。これは「ノーワーク・ノーペイの原則」という、従業員が労働を提供しない以上、会社も賃金を支払う義務はない、という考え方に基づきます。
ただし、会社の就業規則に特別の定めがある場合は、それに従うことになりますので、ご注意ください。
有給
また、出勤停止期間は、そもそも従業員に労働義務がない期間とされます。このため、労働義務のある日に利用できる有給休暇を取得することもできません。有給休暇は、本来働くべき日に労働を免除するための制度であり、労働義務のない出勤停止期間には適用されないと理解すれば間違いはないでしょう。
適切な出勤停止期間
出勤停止の期間は、従業員による問題行動の内容、性質、重大性、継続性、従業員の反省の有無、過去の処分歴などを総合的に考慮して決定する必要があります。
一般的には、数日から1週間程度が目安となることが多いですが、特に重大な規律違反の場合には1か月程度の長期に及ぶこともあるでしょう。ただし、あまりに長期間にわたる出勤停止は実質的に解雇とみなされかねず、処分が無効と判断されるリスクが高まります。処分の「相当性」、つまり、その期間の出勤停止処分が妥当かどうか、という観点から、バランスの取れた期間設定をすることが必要不可欠です。
適切な出勤停止処分について悩まれた場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。
出勤停止処分を行う際の手続と注意点
このように、出勤停止処分は、懲戒解雇処分より軽いとはいえ、従業員に一定期間無給でいることを命じる処分ですから、従業員側から出勤停止処分が無効であるなどと争われるリスクが相当程度あります。この際に、裁判所から出勤停止処分が無効であると指摘されないように、以下の手続には留意しましょう。
出勤停止処分の手続
まずは、出勤停止処分の手続をご説明します。
証拠確保・事実確認
最初に、問題行動に関する客観的な証拠を収集し、事実関係を正確に把握することが重要です。関係者からの聞き取り調査(複数人からの証言や書面での記録)、メールやチャット履歴、業務日報、防犯カメラ映像など、各種証拠を早期に収集しましょう。
この際には、裁判になることも視野に入れて、客観的な証拠を重視して集めましょう。目撃者等の供述など、曖昧な情報や憶測だけに基づいて処分を進めることは控えた方が無難です。
就業規則の確認
次に、自社の就業規則に、当該問題行動が懲戒事由として明確に定められており、かつ、出勤停止処分がその懲戒事由に対する懲戒の種類として規定されているかを必ず確認してください。
従業員に対する懲戒権は、あくまでも就業規則に記載があり、かつ、これが従業員に周知されていて初めて発生する権利です。このため、就業規則に記載がない懲戒処分は、原則として無効とされます。また、同様に就業規則が従業員に周知されてことも必要となります。
弁明の機会の付与
ここまで確認した上で出勤停止処分を下す場合には、処分対象の従業員に対し、自身の行為について説明し、弁明する機会を必ず与えましょう。事前に弁明を聞く日を定めて従業員に告知し、弁明準備のための期間を一定程度付与することも重要です。
従業員の言い分を聞くことで、会社側の誤解や事実誤認を防ぐことができますし、仮に処分に至ったとしても、懲戒手続の公正性が担保されていることを示せますから、後の紛争で出勤停止処分が無効となるリスクを軽減できます。また、弁明の際に客観的証拠を示し、従業員に出勤停止処分となることを納得させることができると、なお良いです。
弁明は、書面または口頭で行わせ、その内容を録音等の記録に残しておくべきです。
処分決定と通知
収集した証拠と弁明内容を検討し、必要であれば懲戒委員会などを開催した上で、最終的に出勤停止処分を下すことを決定することとなります。
社内での決済を終えて処分を下す際には、従業員に対し、処分の理由、内容、期間などを具体的に明記した書面で通知しましょう。口頭での通知は後々のトラブルの原因となるため避け、必ず書面で交付することが重要です。
通知書には、問題行動の具体的内容、就業規則のどの条項に違反したのか、なぜ出勤停止処分に至ったのかを明確に記載しましょう。ここで記載していない懲戒理由を後から追加することは基本的に許されていませんので、慎重に作成する必要があります。
出勤停止処分の注意点
次に、出勤停止処分を下す際の注意点も、改めてご案内します。
就業規則に明記がなければNG
繰り返しになりますが、就業規則に懲戒事由と出勤停止処分に関する規定がなければ、出勤停止処分が法的に無効と扱われてしまいます。懲戒処分は、会社が一方的に課すものですので、従業員に予見可能性を与えるために、あらかじめルールが明確に定められ、周知されている必要があります。
就業規則の記載にご不安がある場合には、実際に従業員が非違行為をする前に、就業規則自体の見直しを弁護士等にご依頼されるべきです。
処分の「相当性」が必要
また、懲戒処分は、対象となる問題行動の内容、性質、程度に対して、「相当なもの」でなければなりません。
例えば、軽微な遅刻や報告忘れに対して、長期の出勤停止処分を下すなど、明らかにバランスを欠く処分は、「権利の濫用」として無効と判断されるリスクがあります。どの程度の問題行動であれば出勤停止処分を下せるかという点については、弁護士の助言を得て判断するべきでしょう。
「弁明の機会の付与」を省略すると無効に
最後に、従業員に弁明の機会を一切与えずに処分を行った場合、その処分には手続上の問題があるとして、後に無効と判断される可能性が高いことにも注意しなければなりません。弁明の機会の付与は、適正なプロセスを保障するための基本原則であり、重大な懲戒処分を下す以上は、省略することが許されません。
必ず、当該従業員側の意見を聞く機会を設けましょう。
出勤停止処分を弁護士に相談すべき理由
さて、以上のとおり、出勤停止処分を下す際の流れ等についてご説明しました。繰り返しご説明しましたとおり、出勤停止処分を下す場合には、法的な観点からの検討が必要不可欠です。これらの検討をせずに安易に下した出勤停止処分は、のちに裁判によって無効となってしまうおそれがあります。このような自体を防ぐために、ぜひ弁護士にご相談ください。
当事務所は、多くの企業顧問を抱えて日々のご相談に対するアドバイスをしています。出勤停止処分についてお悩みになった場合には、ぜひ、当事務所にご相談ください。
監修者
弁護士法人グレイス企業法務部
- 本店所在地
- 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
- 連絡先
- [代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129 - WEBサイト
- https://www.kotegawa-law.com/
「労働問題・労働法コラム」の関連記事はこちら
お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら
電話で問い合わせる
0120-77-9014
受付時間:平日9:00-17:30
メールで問い合わせる
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!
メールでのお問い合わせは24時間受付中!