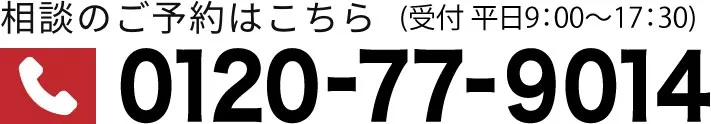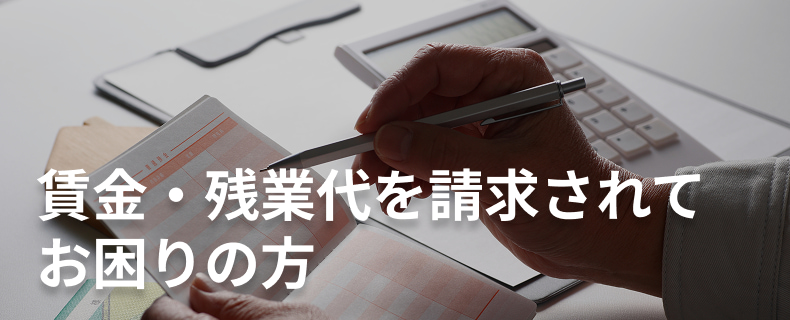企業法務コラム
出勤停止中の従業員の給与の扱いについて弁護士が解説
更新日:2026/01/20
出勤停止中の従業員が居る場合、給与を支払う義務はあるのでしょうか?また、出勤停止中の従業員が有給をとることはできるのでしょうか?
問題社員に出勤停止という処分を下したのち、どのように対応するべきか悩ましいところではないでしょうか。このページでは、出勤停止中の従業員の給与の扱いについて、弁護士の視点から解説します。
目次
出勤停止中に給与を支払う必要はあるのか?
それでは、まず出勤停止中に従業員の給与を支払う必要があるのかどうかという点についてご説明します。
ノーワーク・ノーペイの原則
結論的には、出勤停止中の従業員には、給与を支払う必要はありません。
出勤停止は、従業員の責めに帰すべき事由(就業規則違反など)に対する懲戒処分であり、一定期間の就労を禁止するものです。この期間中、従業員は労務の提供を行わないため、原則として給与を支払う必要はありません。これは、労働者が働かなければ、その対価である賃金も発生しないという「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づきます。
出勤停止中の有給
また、出勤停止中の従業員に有給を付与する必要もありません。
出勤停止期間中は、従業員に労働義務が免除されています。年次有給休暇は、本来労働義務のある日にのみ取得できるものです。したがって、出勤停止中の従業員から有給休暇の取得申請があったとしても、会社は応じる義務はありません。懲戒処分としての実効性を確保する観点からも、有給休暇の取得を認める必要はないとされています。
出勤停止中の賞与
賞与の支給は、就業規則や賃金規程に定められた基準によります。出勤停止期間中に賞与の算定期間が含まれていたり、賞与の支給日に出勤停止中であったりする場合、賞与の支給をどうするかは各種規程次第です。
賞与が労働の対価としての性格を持つ場合、出勤停止により労務提供がなかった期間を評価対象から外したり、査定を減額したりすることは可能です。もちろん、非違行為による勤務態度評価・業績悪化評価をして、賞与を減額することもあり得る選択肢でしょう。いずれにしても、就業規則等に、賞与の支給要件などについてどのように規定されているかが重要となります。
ただし、賞与支給の条件として「支給日に在籍していること」を定めている場合でも、出勤停止処分を理由に賞与を不支給とすることについては、裁判で無効と扱われている例もありますから、注意が必要です。
このように、賞与の取扱いについては、就業規則等に賞与に関する明確な定めを設けておき、事前に対策を取っておくことが重要です。
自宅待機との違い
なお、出勤停止と混同されがちなのが「自宅待機」です。両者の最も大きな違いは、その性質と給与の扱いにあります。
出勤停止
従業員の就業規則違反行為に対する「懲戒処分」であり、従業員側に労務提供できない原因がありますので、給与は原則として支払う必要がありません。
自宅待機
会社の業務上の都合(セクハラ・パワハラの調査期間、事業縮小、工場閉鎖など)による「業務命令」であり、労働者に落ち度がない場合は、原則として給与を支払う必要があります。
このため、懲戒処分としての出勤停止処分を下していないにもかかわらず、給与支払をしない、といった対応を取ることのないように、注意しなければなりません。
出勤停止とは?
ちなみに、そもそも出勤停止は、従業員が就業規則違反などの非違行為を行った際に、会社が懲戒処分として一定期間の就労を禁止するものです。懲戒処分の中では、減給より重く、懲戒解雇よりは軽い処分と位置づけられることが多く、従業員にとっては無給期間を生じる制裁となりますから、経済的にも重いものとして機能します。
懲戒解雇処分相当の非違行為を行ったものの、改悛の情が強く認められるとか、会社が被った損害を弁償したとか、特別な事情がある場合に、出勤停止処分を下すことが多いです。また、何度も戒告・譴責を繰り返し、減給処分を下したにもかかわらずなお改善が認められない場合に出勤停止処分を下すこともあります。
出勤停止の注意点
このような重い処分である出勤停止処分を有効に行うためには、以下の注意点を守る必要があります。これらを怠ると、処分が無効と判断されるリスクがありますので、注意しなければなりません。出勤停止処分を下す場合には、できるだけ弁護士に事前に相談するべきといえます。
証拠の収集
そもそも懲戒処分は一般に、客観的で合理的な理由に基づいて行われる必要があります。安易に処分を行うのではなく、非違行為があったことを証明できる証拠(書面、メールなど)を十分に収集・整理しておくことが不可欠です。ここでは、できるだけ、客観的な証拠を集めておくことが重要です。他の従業員の証言も重要ですが、その証拠としての力(信用力など)が争われることもよくあります。
そうでなければ、のちに裁判・労働審判といった場面で懲戒処分が無効であると争われた場合、証拠をもって処分の正当性を争うことができなくなってしまいます。
処分理由は合理的か
また、従業員に与える不利益の大きさと、非違行為の重さが釣り合っているか(社会通念上相当か)が重要です。軽微な違反行為に対して長期間の出勤停止を命じると、懲戒権の濫用と判断され、処分が無効になる可能性があります。
出勤停止処分は、通常は懲戒解雇や諭旨解雇の次に厳しい手段であるとされますから、相当程度重い非違行為がなければ下せないということも理解しておく必要があります。
弁明の機会の付与
懲戒処分、特に重めの出勤停止処分を下す場合には、処分対象となる従業員に、事実関係について説明し、自身の非を認めるか、あるいは反論するかするための弁明の機会を与えることが、適正な手続として求められます。弁明の機会を与えずに処分を強行すると、手続上の不備を指摘され、処分が無効となるリスクが高まります。
弁明の機会を与える場合には、処分対象となる従業員の言い分を妨げずに全て言わせることに注意しましょう。また、圧迫的な場面で弁明の機会を付与することも避けるべきです。形式的に弁明の機会を与えたとしても、従業員の言い分が充分に聞かれない状況で実施してしまうと、やはり後に手続が無効であると主張されるおそれがあります。
就業規則の確認
就業規則に、どのような行為が懲戒処分の対象となるのか、どのような懲戒処分があるのかを具体的に定めておく必要があります。就業規則に記載のない懲戒処分を科すことはできませんし、明確に懲戒事由が定められていなければ懲戒処分を科す前提も認められません。
懲戒処分について定めていない就業規則はあまりありませんが、その内容が不十分であることはよくあります。就業規則の内容に不安がある場合には、早急に弁護士にご相談ください。
出勤停止期間
法律上、出勤停止期間に明確な上限はありませんが、一般的には3日〜10日、長くても30日(1か月)程度に設定する企業が多いです。非違行為の性質・態様を考慮し、合理的な範囲に留める必要があります。
長すぎる期間は、裁判で争われた場合、処分が重きに失すると判断されて無効とされる可能性があります。仮に出勤停止処分が無効となった場合には、後から出勤停止処分期間中の給与支払を求められることとなります。
適切な処分をするには
出勤停止処分をのちに無効とされることなく、適切な処分として下すためには、以下の点に注意が必要です。
顧問弁護士に相談する
まずは、出勤停止処分を下す前に、必ず弁護士に相談するようにしましょう。普段からあなたの企業の状況を知っている顧問弁護士がいれば、より安心でしょう。
出勤停止処分は、その判断や手続が不適切だと、後々労働者とのトラブルに発展する可能性があります。また、出勤停止処分の有効性は、他の従業員にこれまで下された懲戒処分とのバランスをも踏まえて判断されます。処分を検討する際は、懲戒処分に関する専門的な知識を持つ弁護士、特に、あなたの企業内のことを熟知した顧問弁護士に事前に相談し、法的なリスクを回避することが賢明でしょう。
就業規則の改訂を行う
また、就業規則の整備を行い、かつ、従業員への周知を徹底して行うことも肝要です。
特に、内容に問題がなかったとしても、従業員に周知されていない就業規則は効力が認められない場合がある点に、留意が必要です。最新の法令や会社の現状に合わせて、懲戒事由や懲戒処分の種類、手続を具体的に記載した就業規則を作成・改訂し、従業員に周知徹底しておくことが重要です。
就業規則の内容や周知方法については、やはり弁護士に相談してその内容を決めるべきといえます。仮に裁判になったとして、どのようにその効力が判断されるかは、裁判経験のある弁護士でなければ想定しがたいので、労働問題・裁判経験の豊富な弁護士にご相談なさることをお勧めします。
5. まとめ
以上のとおり、出勤停止中の従業員の給与の扱いについてご説明しました。出勤停止は、従業員への懲戒処分として有効な手段ですが、実際に処分を下すためには、厳格な要件と手続が求められます。
ノーワーク・ノーペイの原則に基づき給与は支払わなくてよく、有給も付与しなくてよいのが原則ですが、賞与の扱い、自宅待機との違いなど、細かな点に注意が必要です。処分の有効性を確保するためには、事実の裏付け、処分の合理性、適正手続の遵守が不可欠ですから、専門家である弁護士への相談や就業規則の整備を常日頃から行うことが、労使トラブルを未然に防ぐ上で重要となります。
当事務所では、多くの企業顧問を抱えて労働問題・労働紛争も多く手掛けています。出勤停止処分はもとより、懲戒処分を下す際にお悩みの場合には、ぜひ当事務所に一度ご相談ください。あなたからのご相談に、丁寧に対応させていただきます。
監修者
弁護士法人グレイス企業法務部
- 本店所在地
- 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
- 連絡先
- [代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129 - WEBサイト
- https://www.kotegawa-law.com/
「労働問題・労働法コラム」の関連記事はこちら
お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら
電話で問い合わせる
0120-77-9014
受付時間:平日9:00-17:30
メールで問い合わせる
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!
メールでのお問い合わせは24時間受付中!