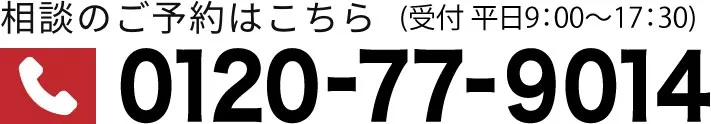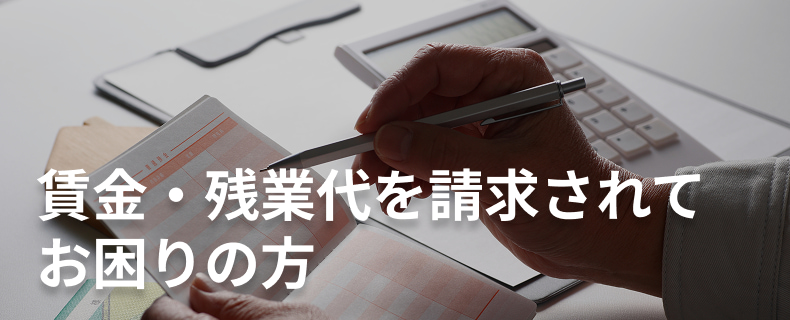企業法務コラム
即日解雇は違法?会社が守るべき『解雇予告』のルールと実務対応
更新日:2025/11/26
即日解雇は、法律上の要件を満たさない限り、原則として違法な不当解雇と扱われることとなります。会社が従業員を解雇する際には、労働基準法で定められた「解雇予告」のルールを守る必要があります。
以下では、会社が守るべき解雇予告のルールと実務対応について解説します。
解雇予告とは
解雇予告とは、会社が従業員を解雇する際、「解雇日の少なくとも30日前までに予告しなければならない」という法律上の義務です。このルールは、労働者の生活安定を図るためのものです。
解雇予告の法的根拠(労働基準法20条)
上記のとおり、会社は、従業員を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその旨を予告しなければなりません。これは、労働基準法20条に定められています。この30日の期間は、労働者が次の仕事を探すための猶予期間を確保するという意味合いを持っています。
解雇の30日前予告義務とは?
会社がこの義務を怠り、予告期間を設けないで解雇(即日解雇)を行う場合は、30日に満たない日数分の「解雇予告手当」を支払う必要があります。例えば、解雇日の10日前に予告する場合は、残りの20日分について解雇予告手当を支払うことになります。
解雇予告が不要となる例外のケース
会社が解雇予告や解雇予告手当の支払いをせずに即日解雇できるケースは、ごく限られています。以下、例外となるケースをご紹介します。
就業規則に定める懲戒解雇の場合
労働者の重大な規律違反など、労働者の責めに帰すべき事由による懲戒解雇の場合です。例えば、著しいパワハラ・セクハラ、業務上の横領、会社の名誉を著しく損なう行為、正当な理由のない無断欠勤など、社会通念上、解雇がやむを得ないと判断されるほどの非行・非違行為がこれに該当します。
ただし、懲戒解雇が許される場合も限定的ですから、安易に懲戒解雇を選択することなく、事前に弁護士にご相談されることをお勧めします。
天災事変などやむを得ない事由
次に、事業の継続が不可能になった場合など、会社側の不可抗力による解雇の場合です。具体的には、地震や火災などの天災事変、あるいは事業場の壊滅的な被害などがこれに該当します。
この場合、事業主の故意や過失がないことが前提であり、単なる経営不振は含まれません。また、労働基準監督署の除外認定を受けることが必要となります。
労基署の認定(解雇予告除外認定申請)について
上記2つのいずれの場合にせよ、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」(労働基準法20条1項但書)に該当するときは、会社は労働基準監督署長に対して「解雇予告除外認定申請」を行い、認定を受けることで、解雇予告手当の支払を要せずに即日解雇をすることができます(労働基準法20条3項)。
ただし、解雇予告除外認定申請は、原則として解雇予告通知の前に行うべきものとされている点に注意が必要です。この申請を労働基準監督署に行った場合、労基署の調査が行われますので、申請が認められるまでに1~2週間程度の時間を要します。このため、即日解雇を行う場合には、時間的余裕を確保した上で計画を練る必要があります。
このような認定を受けずに即日解雇を行った場合、解雇予告手当の支払いが免除されることはありません。弁護士に相談することで、申請書類の作成や、認定を受けるための論理的な構成をサポートしてもらえますから、事前に弁護士にご相談されることをお勧めします。
解雇予告手当とは
さて、次に、解雇予告手当についてご説明します。
手当が必要なケースと不要なケース
解雇予告手当は、会社が労働者を即日解雇(又は解雇までに30日以下の日数しかないような解雇予告)する場合に原則として支払うべきものです。逆に言えば、30日以上前に解雇予告を行った場合は、手当を支払う必要はありません。
計算方法の具体例
解雇予告手当の金額は、平均賃金の30日分と定められています。
平均賃金 = 直近3か月間の賃金総額 ÷ その期間の暦日数
例えば、過去3か月の賃金総額が90万円、暦日数が90日だった場合、平均賃金は1万円となります。この場合、解雇予告手当は 1万円 × 30日分 = 30万円となります。
ただし、予告日数が30日に満たない場合は、不足日数分の平均賃金を支払えばよいとされています。例えば、解雇日の10日前に解雇予告をした場合は、20日分解雇予告日数が足りていないので、(30日 – 10日)×
平均賃金が解雇予告手当となります。
即日解雇する場合に会社が取るべき手続
次に、即日解雇する場合に会社が取るべき手続についてもご紹介します。解雇予告手当の支払はさることながら、解雇通知書を適切に作成することにも留意が必要です。
解雇予告手当を支払う流れ
即日解雇を行う場合は、解雇の当日に解雇予告手当を支払うことが原則となります。この支払いが遅れると、労働者が次の仕事を見つけるまでの期間の手当を何らしないこととなりますから、労働基準法違反となる可能性が高いです。
ちなみに、支払方法としては、通常の給与同様に、現金手渡や銀行振込などが考えられますが、のちに解雇予告手当の金額が争われた場合に備え、いつ、いくら支払ったかを明確に記録に残しておくことが重要です。
解雇通知書の作成
また、口頭での解雇は、確実にトラブルの元となります。解雇の理由、日付、解雇予告手当の支払額・支払方法について明記した解雇通知書を必ず作成し、労働者に交付すべきです。これにより、解雇の事実と内容を明確にし、後の紛争リスクを低減できます。
解雇通知書を作成する場合には、解雇の理由を漏れなく記載することにもご留意ください。のちに解雇の有効性が争われることも視野に入れて、万全の体制を整えてから解雇をしましょう。事前に弁護士にご相談いただければ、リスクを最小化することが期待できます。
よくあるトラブル事例とその対応策
ここで、即日解雇をした場合によくあるトラブル事例とその対応策についてもご説明しておきます。
「突然の解雇は無効」と訴えられたケース
解雇の理由が客観的に合理性を欠き、社会通念上相当と認められない場合、「不当解雇」として解雇が無効となる可能性があります。この場合、解雇後の期間も、会社側が不当な解雇をしたせいで労働者が働けなくなったものと扱われ、この期間の賃金を支払うよう命じられることもあります。解雇が無効とされるようなケースでは、半年から1年くらいの賃金を支払わなければならないとされるような事例も少なくありません。
対応策としては、解雇理由を客観的かつ具体的に証拠をもって説明できるようにしておくことが不可欠です。仮に解雇予告手当を支払ったとしても、そもそもの解雇自体が無効となってしまっては意味がありません。リスク管理のためにも、実際の解雇前に一度弁護士にご相談ください。
労基署から是正勧告を受けた場合の対処法
また、即日解雇をされた労働者が労働基準監督署に相談に行くこともよくあります。この場合には、解雇予告手当の未払いなど、労働基準法違反が疑われるときには、労働基準監督署が自ら調査を行い、会社に対して是正勧告を行うことがあります。勧告を受けた場合は、速やかに是正措置を講じなければなりません。
対応策としては、弁護士と連携し、法的な観点から適正な対応をとることが重要です。いずれにしても、事前に法的観点から解雇の有効性・解雇手続に不備がないように注意をしておくことが必要なのです。解雇をする場合には、事前に無用な争いを避ける準備をするという意識を持ちましょう。
解雇問題を弁護士に相談するメリット
このような解雇問題については、とにかく専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。弁護士に相談することで得られるメリットは、以下のとおりです。
「不当解雇」リスクを未然に防げる
まず、弁護士は、解雇の有効性について法的な観点から厳しく解雇リスクをチェックした上で会社に助言します。弁護士は労働紛争や裁判を経験していますから、解雇の有効性を争われた場合にどのような結果になるか、予測を立てることができます。先を見通すことができる弁護士ならではの助言があるのです。
このように、解雇理由の妥当性や手続の適法性を事前に確認することで、将来的な不当解雇トラブルを未然に防ぐことができます。
解雇通知書の法的有効性を担保できる
また、解雇通知書は、その内容が法的に有効である必要があります。弁護士は、解雇通知書に記載すべき事項や、トラブルを防ぐための文言を適切にアドバイスし、作成をサポートしますから、法的有効性を担保することができるでしょう。
特に解雇通知書は、解雇の有効性を争われた場合に会社側の主張を補強する重要な証拠となりますから、おざなりにすることなく、適切に作成しなければなりません。
万が一の労使紛争でも「初動が整っている」ことで有利に
弁護士のサポートを受けて適正な手続で解雇を進めていれば、万が一、労働者から訴えられた場合でも、会社側の正当性を主張するための証拠や論理が整っているため、紛争を有利に進めることが可能です。
特に、労働者から不当解雇であるとの主張がなされた場合の初動で、会社経営者が不用意な回答をしてしまい、これがのちのちに尾を引く事例は枚挙にいとまがありません。初動から弁護士に相談・依頼して、会社に有利な結論を引き寄せましょう。
まとめ
以上のとおり、会社が守るべき解雇予告のルールと実務対応についてご説明しました。
即日解雇は、解雇予告手当を支払えば常に合法になるというわけではありません。労働基準法に定められた解雇予告の義務と、解雇予告手当の支払いはセットで理解する必要があります。安易な即日解雇は、不当解雇と判断され、後々の法的トラブルに発展するリスクをはらんでいます。弁護士に相談し、法的に適正な手続きを踏むことが、会社と労働者双方にとっての安全策となります。
当事務所には、多くの企業顧問を抱えて、労務相談・労働事件の対応をしてきた実績があります。もし労働者への解雇についてお悩みの場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。あなたの会社のリスクヘッジのために、適切な助言を提供させていただきます。
監修者
弁護士法人グレイス企業法務部
- 本店所在地
- 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
- 連絡先
- [代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129 - WEBサイト
- https://www.kotegawa-law.com/
「労働問題・労働法コラム」の関連記事はこちら
お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら
電話で問い合わせる
0120-77-9014
受付時間:平日9:00-17:30
メールで問い合わせる
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!
メールでのお問い合わせは24時間受付中!