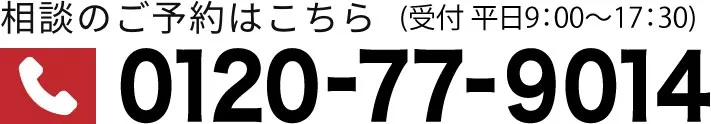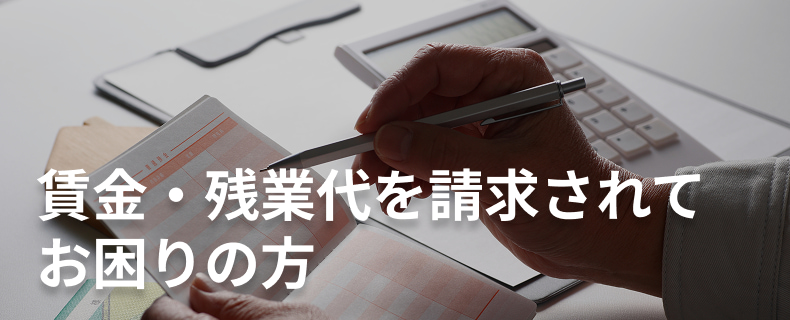企業法務コラム
安全配慮義務に違反するとどうなる?違反のリスクと顧問弁護士ができる対策を解説
更新日:2025/10/29
会社は、従業員が安全な労働環境で労働に従事できるよう、その安全に配慮する義務(安全配慮義務)を負います。
安全配慮義務に違反し、労災を起こしたり、ハラスメントを放置したりして従業員に損害を与えてしまった場合、会社は多額の損害賠償責任を負うだけでなく、社会的信用を失い、事業継続が困難になるほどの深刻なダメージを受けるリスクがあります。このようなリスク・デメリットを減らすために、ぜひ、顧問弁護士を付けることをご検討ください。
このページでは、安全配慮義務違反のリスクと、顧問弁護士ができる対応・対策についてご説明します。
目次
安全配慮義務とは?
そもそも安全配慮義務とは、企業が雇用する従業員の生命、身体、健康を危険から守るために、必要な配慮を行う法的な義務です。これは労働契約法第5条に明記されており、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と定められています。
この義務は、単に法律に定められているだけでなく、過去の多くの判例の積み重ねによって形成されてきたものであり、その範囲は非常に広範かつ多岐にわたります。会社と従業員との関係では、具体的には、以下の3つの側面から義務が課せられているといえます。
労災事故の防止
最も直接的な義務として挙げられるのが、労災事故の防止です。これは、作業環境の整備、危険な機械や設備の安全対策、危険物の適切な管理など、物理的な側面で従業員の安全を確保することです。例えば、製造業における機械の安全カバーの設置、建設現場における足場の安全確保、飲食店における衛生管理などがこれに該当します。
単に物理的な安全対策を講じるだけでなく、従業員に危険を認識させ、適切な行動を促すための安全教育の実施も重要な義務です。特に、経験の浅い新人や、新たな業務に就く従業員に対しては、より丁寧な指導と監督が求められます。この義務を怠り、事故が発生した場合は、企業は使用者責任(民法第715条)や債務不履行責任(民法第415条)に基づく損害賠償責任を問われることになってしまいます。
ちなみに、これらの労災事故が起きた場合に備え、労災上乗せ保険に加入している会社も多いです。
健康被害の防止
また、現代の労働環境においては、過重労働やストレスによる心身の健康被害が大きな問題となっています。安全配慮義務は、会社に対し、こうした健康被害を未然に防ぐための配慮も求めています。
具体的な対策としては、労働時間や残業時間の適切な管理が挙げられます。労働基準法が定める労働時間を遵守することはもちろん、過労死の労災認定基準となるいわゆる「過労死ライン」(月に80時間を超える時間外労働)を意識した勤怠管理が不可欠です。また、定期的な健康診断や、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の実施も義務付けられておりますから、従業員の心身の健康状態を把握し、必要に応じて医師の面談指導を受けさせるなどの措置を講じなければなりません。
業務上の心理的負荷が原因でうつ病などの精神疾患を発症した場合も、企業は安全配慮義務違反を問われる可能性がありますから、平時から、産業医への相談ができる環境、業務量や業務内容の見直し、メンタルヘルスケアの提供などが求められます。
ハラスメントへの対応
更に、職場におけるハラスメントは、従業員の心身に深刻なダメージを与え、健全な職場環境を著しく阻害します。このため、企業は、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントといった各種ハラスメントを防止し、発生した場合には適切に対処する義務を負います。昨今は、この観点からの安全配慮義務も挙げられることが多いです。
この義務を果たすためには、以下の措置を講じることが必要です。
ハラスメント防止のための社内規程の整備
ハラスメント行為の定義や、禁止行為、罰則などを明確に定める必要があります。
相談窓口の設置
被害者や目撃者が安心して相談できる窓口(できれば外部の窓口が良いです。)を設置するべきです。相談者や内容の秘密厳守を徹底し、相談者に不利益な取扱いをしないことを明示する必要があります。
迅速かつ適切な対応
社内又は上記相談窓口に相談があった場合は、速やかに事実関係を調査し、被害者と加害者双方への適切な措置を講じなければなりません。被害者の安全確保やケア、加害者への懲戒処分、両者の隔離措置、再発防止策の実施などが含まれます。
これらの義務を怠った結果、ハラスメントが原因で従業員が精神疾患を発症したり、離職に追い込まれたりした場合、企業は安全配慮義務違反として損害賠償責任を負うことになってしまいます。
安全配慮義務違反とされる典型例
安全配慮義務違反と判断されるのは、企業が上記のような配慮を怠った結果、従業員に損害が発生した場合です。以下、特に問題となりやすい典型的な例を挙げます。
十分な安全教育を行わず新人に作業をさせた
新入社員や、配置転換されたばかりの従業員は、業務に関する知識や経験が乏しく、危険を十分に認識できないことがあります。この状況下で、企業が十分な安全教育や研修を行わずに危険な作業をさせた結果、事故が発生した場合、安全配慮義務違反が重く問われます。これは法律的な意味合いのみならず、会社のレピュテーションを下げる意味でも、重くのしかかります。
例えば、
- 製造現場で、機械の操作方法や緊急停止ボタンの位置を教えずに作業をさせた結果、指を挟む事故が発生した。
- 営業職の新人に、安全運転講習を受けさせないまま、長距離運転を命じた結果、居眠り運転による事故が発生した。
- 高所作業現場で、安全帯の使用方法を十分に指導せず、落下事故が発生した。
といったケースが想定されます。
これらのケースでは、単に事故が起こったことだけでなく、企業が予見できた事故の危険に対する事前の回避措置を怠った点が問題視されます。
長時間労働・過重労働の放置
また、従業員の長時間労働や過重なノルマを放置し、その結果、うつ病や心臓疾患、脳血管疾患を発症させるようなケースは、近年特に増加傾向にあります。長時間労働は、心的にも身体的にも、従業員を破滅的な立場に追いやってしまうリスクがありますので、注意が必要です。
具体例としては、
- 営業職に対し、達成困難なノルマを課し、連日深夜に及ぶ残業を黙認した結果、過労死やうつ病を発症した。
- 裁量労働制を適用しているにもかかわらず、実際には長時間労働を強要し、従業員の健康管理を怠った。
- 多忙な部署に人員を補充せず、一人当たりの業務量を過度に増加させた結果、従業員が精神的に追い詰められた。
といった例が挙げられます。
これらの場合、企業は労働時間管理等の不備だけでなく、業務量や精神的負荷の軽減、適切な休憩時間の確保といった配慮を怠ったとして、重い責任を追及されます。
パワハラ・セクハラを放置
従業員間でハラスメントが発生していることを知りながら、見て見ぬふりをしたり、適切な対応を取らなかったりした場合、企業は安全配慮義務違反となります。
典型的なケースとしては、
- 上司による部下への暴言や暴力が常態化していることを知りながら、注意指導を行わず放置した。
- 複数の従業員からのセクハラ相談に対し、プライバシーを理由に調査を怠り、加害者への処分を行わなかった。
- 被害者が退職を希望しているにもかかわらず、その原因となったハラスメント行為を放置し、改善しようとしなかった。
が挙げられます。
ハラスメント事案では、企業が「被害を認識した時点」から「適切な対応を完了するまで」の一連のプロセスが、安全配慮義務の履行として厳しく問われます。形式的な相談窓口があるだけで、実効性のある対応が取られていなければ、安全配慮義務を果たしたことにはなりません。
安全配慮義務違反が会社に与える深刻なリスク
安全配慮義務違反が認められた場合、企業が直面するリスクは多岐にわたり、その影響は経営の根幹を揺るがすほどの深刻なものとなります。
多額の損害賠償責任
最も直接的なリスクは、被害を被った従業員やその遺族から多額の損害賠償を請求されることでしょう。賠償額は、被害の程度、企業の過失の度合い、そして被害者の年齢や収入など、様々な要素を考慮して算定されます。
従業員に被害が出た場合の損害賠償費目としては、以下のものが挙げられます。
治療費
労災保険の給付対象とならない医療費や、精神科の治療費など。
休業損害
労災認定の有無にかかわらず、休業期間中の賃金相当額。
逸失利益
事故や疾病が原因で将来得られるはずだった収入の喪失分。特に若年層の場合、就業可能年限に応じた将来の収入減少額が算定されるため、賠償額が高額になります。
慰謝料
精神的・肉体的な苦痛に対する賠償。死亡事故や重い後遺障害が残った場合、数千万円単位の慰謝料が認められることもあります。
弁護士費用
被害者が訴訟を提起した場合の弁護士費用も、一部が賠償額に上乗せされることがあります。
例えば過去の過労死事案では、一億円を超える賠償命令が出されることも珍しくなく、中小企業にとっては、これだけで企業継続を脅かすほどの経済的負担となります。
訴訟・労働審判への発展
また、このような損害賠償請求を受けた場合、被害者が会社との任意の交渉で合意に至らない場合、訴訟や労働審判へと発展する可能性が高まります。
労働審判
労働者と使用者間の紛争を、裁判官と労働関係の専門家からなる審判員が迅速に解決を図る制度です。原則3回以内の期日で結論を出し、調停による解決が期待されますが、調停が成立しない場合は審判が下されます。
訴訟
訴訟は公開の法廷で行われ、判決が下されるまでに、年単位での長期間を要することもあります。この間、企業は多大な時間、労力、そして弁護士費用を費やさなければなりません。
どちらの手続も、企業にとっては大きな負担です。特に訴訟では、裁判が一般に公開されるため、報道リスクが生じます。この結果企業の内部事情やトラブルの内容が世間に知られることになりますと、後述する社会的信用の低下に繋がります。
従業員や取引先からの信頼低下
上でも述べてきたとおり、安全配慮義務違反は、企業のブランドイメージや社会的信用を著しく損ないます。
従業員からの信頼低下
従業員は「会社が自分たちの安全や健康を軽視している」と感じ、会社への帰属意識やモチベーションが低下します。結果として、優秀な人材の離職に繋がり、企業の人的基盤が揺らぎます。
採用活動への悪影響
企業名がメディアで報道されたり、「ブラック企業」としてインターネット上で情報が拡散されたりすると、新たな人材の採用が困難になります。求人を出しても応募が集まらなかったり、優秀な学生が選考を辞退したりする事態も起こりえます。
取引先・顧客からの信頼低下
企業の不祥事は、取引先や顧客との関係にも悪影響を及ぼします。上場企業など、コンプライアンスを重視する企業ほど、安全配慮義務違反を犯した企業との取引を見直す可能性があります。企業の社会的責任が問われる現代において、このリスクは無視できません。
これらのリスクは相互に作用し合い、会社を孤立させていき、企業の存続を危うくするほどの負のスパイラルを形成する要因になります。目に見えず、数値にも表れないものの、このリスクが最も大きなものといえるかもしれません。
違反を防ぐために経営者ができること
安全配慮義務違反のリスクを回避するためには、経営者が主体的に、かつ予防的な対策を講じることが不可欠です。
労務管理の見直し(残業・休職者対応)
最も基本となるのは、適正な労務管理体制を構築することです。
勤怠管理の厳格化
タイムカードやICカード、クラウド型の勤怠管理システムを導入するなどして、従業員の労働時間を正確に把握しましょう。特に、サービス残業をなくし、申告された時間外労働が実態と乖離していないか定期的に確認しなければ、長時間労働の実態は見抜けません。
残業時間の削減
恒常的な残業が発生している部署には、業務の効率化や人員の再配置を検討する必要があります。また、残業が月80時間を超える可能性のある従業員(いわゆる過労死ライン)に対しては、産業医による面談を義務付け、業務負荷の軽減策を講じます。
休職者対応
休職中の従業員に対しては、定期的に連絡を取り、復職に向けたサポートを行いましょう。復職時には、試し出社や短時間勤務から始めるなど、無理のない復帰プログラムを策定するべきです。この復帰過程が上手く機能しないと、続々と離職が相次ぎます。
ハラスメント対策と社内体制整備
また、ハラスメントは、発生する前に芽を摘むことが重要です。
社内研修の実施
全従業員を対象に、ハラスメントの定義や具体例、被害者・加害者への影響、会社の対応方針などを周知するための研修を定期的に実施しましょう。特に管理職に対しては、部下への適切な指導方法や、ハラスメントの兆候を早期に発見するためのマネジメントスキルを教育しなければなりません。これらの研修講師としては、弁護士が最適です。
相談窓口の周知
社内の相談窓口の担当者だけでなく、提携している外部の弁護士事務所やカウンセリング機関など、複数の窓口を設置し、従業員が相談しやすい環境を整えると良いです。
再発防止の徹底
ハラスメント事案が発生した場合は、速やかに事実関係を調査し、加害者への懲戒処分、配置転換などの措置を講じましょう。また、再発防止策を社内外に周知することで、企業のハラスメントに対する断固たる姿勢を示すことができます。レピュテーションリスクを減らすためには、このような自発的な発信活動も重要です。
安全教育・マニュアルの徹底
更に、従業員の物理的な安全を確保するためには、従業員一人ひとりの安全意識を高めることが不可欠です。
安全マニュアルの作成と更新
業務内容に応じた安全マニュアルを作成し、従業員に配布します。マニュアルは、設備の変更や作業手順の改善に応じて、定期的に更新する必要があります。
危険予知トレーニングの導入
実際の作業現場で起こりうる危険を想定し、それを回避するためのトレーニングを実践しましょう。これにより、従業員自身が危険を察知し、自律的に安全行動をとれるようになります。
ヒヤリハットの共有
重大な事故に至らなかった「ヒヤリハット」の事例を社内で共有し、潜在的な危険箇所の洗い出しと対策に活かします。航空事故の分野においても、1件の大きな事故の前には、数百数千のヒヤリハットがあったと言われます。「ヒヤリハット」のうちに危機回避を進めましょう。
顧問弁護士との連携
これらすべての対策を自社内部だけで完璧に行うのは困難です。特に、法改正や最新の判例動向を把握して自社のルールに反映させていくには、専門家の知見が不可欠です。顧問弁護士と日常的に連携し、予防的な観点からアドバイスを求めることが、最も有効なリスクマネジメントとなります。
顧問弁護士ができる対策
このように、顧問弁護士は、安全配慮義務違反のリスクを回避するために、企業の「かかりつけ医」のような存在として機能します。トラブルが起こる前の予防策から、万が一トラブルが発生した際の初動対応、そして法的な解決まで、多岐にわたるサポートを提供できるのが、顧問弁護士なのです。
日常的な労務相談でトラブルを未然に防止
例えば、労務管理には、法律上のグレーゾーンや解釈に迷う場面が多々あります。以下のような場合には、顧問弁護士の対策が機能するでしょう。
就業規則の適用
従業員の休職期間や、懲戒処分の要件など、就業規則の具体的な適用について迷った際、顧問弁護士に相談することで、法的に適切な対応方針を迅速に確認できます。
問題社員への対応
業務命令に従わない社員、ハラスメントの疑いがある社員など、対応が難しい社員に対して、法的リスクを最小限に抑えながら、どのように指導や処分を進めるべきかアドバイスを得られます。
残業代未払いリスクのチェック
勤怠管理の状況や、特定の従業員の労働時間について、サービス残業が発生していないか、未払い残業代の請求リスクがないかを定期的にチェックしてもらえます。
顧問弁護士は、こうした日常的な相談を通じて、小さなリスクの芽を見つけ出し、それが大きな法的トラブルに発展するのを防ぐ役割を果たします。
就業規則・社内規程の整備
また、労働関連法規は頻繁に改正され、最新の判例によって新たな解釈が生まれます。これらを社内に反映していくためには、平時から顧問弁護士との協力が不可欠です。
法改正への対応
育児・介護休業法、労働安全衛生法、ハラスメント関連法など、頻繁に行われる法改正に迅速に対応し、就業規則や各種規程を最新の状態に保ちます。
企業の実情に合わせた規程の作成
雛形をそのまま使うのではなく、会社の業種や規模、風土に合わせたオーダーメイドの就業規則を作成します。これにより、トラブル発生時の法的根拠が明確になり、円滑な対応が可能になります。あなたの会社の状況を知っているからこそできる対策です。
リスクヘッジ
懲戒処分や解雇に関する規定、ハラスメントの相談・調査フローなど、トラブルが発生しやすい項目について、法的に有効な内容になっているかを確認し、訴訟リスクを低減します。
従業員トラブル発生時の初動対応
万が一、労災事故やハラスメント、内部告発などのトラブルが発生した場合、初動対応を誤ると、その後の訴訟で不利になるだけでなく、企業の信用失墜にも繋がります。このような危機対応も、顧問弁護士に任せればスムーズに進みます。
事実関係の調査
顧問弁護士は、ある程度公平中立な立場で、関係者へのヒアリングや証拠の収集を支援できます。
被害者・加害者への対応アドバイス
被害者への謝罪や補償の交渉、加害者への懲戒処分など、その後の対応について法的観点から適切な助言を行います。
対外的広報
メディア対応や関係者への説明について、法的リスクを考慮した上で、どのようなメッセージを発信すべきか助言します。
損害賠償・訴訟リスクへの備え
事態が悪化して従業員から損害賠償請求や訴訟を起こされた場合、顧問弁護士は企業の代理人として対応します。
交渉代理
被害者側との示談交渉を代行し、企業の損害を最小限に抑えるための交渉を行います。
法廷活動
訴訟に発展した場合、企業の主張を裏付ける証拠を収集し、裁判官に対して説得力のある主張を展開します。
和解提案
長期化しがちな訴訟において、早期解決を図るための和解条件を提示するなど、事態収拾に向けた戦略的なアドバイスを提供します。
これらの対応は、やはり普段から付き合いの深い顧問弁護士に任せるべきでしょう。
まとめ
以上のとおり、安全配慮義務に違反するリスクと顧問弁護士ができる対応について解説しました。安全配慮義務の違反は、企業に多額の経済的損失、社会的信用の失墜、そして優秀な人材の流出という致命的なリスクをもたらします。これらのリスクは、一度顕在化すると、企業の存続そのものを脅かしかねません。
しかし、これらのリスクは、決して避けられないものではありません。経営者がこの義務の重要性を深く認識し、日々の業務における物理的・精神的な安全対策を徹底することで、ほとんどのトラブルは予防可能です。特に、労働法の専門家である顧問弁護士と日常的に連携し、就業規則の整備から従業員トラブル発生時の初動対応まで、予防的な視点で企業のリスクマネジメントを行うことが、現代の企業経営においては不可欠といえるでしょう。安全配慮義務の履行は、コストではなく、従業員が安心して働ける環境を整えることで企業の生産性を高め、長期的な成長を支えるための重要な投資であると捉えるべきです。
当事務所では、多くの顧問企業を抱える法律事務所として、労務問題にお悩みの方への助言を多く扱っています。ぜひ、お悩みの場合には、また、顧問弁護士をお探しの場合には、当事務所までご相談ください。
監修者
弁護士法人グレイス企業法務部
- 本店所在地
- 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
- 連絡先
- [代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129 - WEBサイト
- https://www.kotegawa-law.com/
「労働問題・労働法コラム」の関連記事はこちら
お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら
電話で問い合わせる
0120-77-9014
受付時間:平日9:00-17:30
メールで問い合わせる
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!
メールでのお問い合わせは24時間受付中!