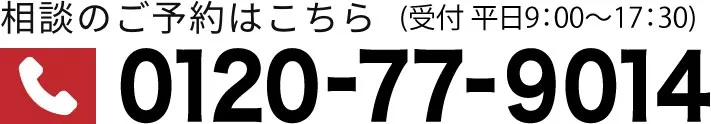企業法務コラム
パワハラに該当する言葉一覧|従業員のパワハラを防ぐ方法を弁護士が解説
更新日:2025/11/26
職場のハラスメントの中でも「パワーハラスメント(パワハラ)」は特に問題視されています。企業には、従業員が安心して働ける環境を整備する義務があり、パワハラ防止対策は喫緊の課題です。ここでは、パワハラに当たりうる具体的な文言と、企業が取るべき対策について解説します。
目次
パワハラになり得る言葉
パワハラは、単なる厳しい指導や注意とは異なり、従業員の尊厳を傷つけ、就業環境を悪化させる行為を指します。以下に、パワハラに該当し得る具体的な言葉の例を挙げます。
身体的な攻撃を示唆する言葉
例:「殴るぞ」「ぶっ飛ばすぞ」「殺すぞ」
相手に身体的な危害を加えることを示唆する言葉は、パワハラに該当する可能性が高いです。また、脅迫行為にあたって犯罪に当たる可能性すらあります。
精神的な攻撃(侮辱や暴言)
例:「こんなこともできないのか」「頭おかしいんじゃないの?」「給料泥棒」
相手の人格を否定したり、誹謗中傷したりする言葉は、精神的な苦痛を与えますから、パワハラに該当する可能性が高いです。
人間関係からの切り離し
例:「話しかけるな」「お前とは仕事しない」「あの人はもういないと思ってください」
意図的に特定の従業員を孤立させ、職場で孤立させる行為もパワハラに該当します。特に、自主退職に追い込むための手法であれば、パワハラとしての性質が高まるでしょう。
過大な要求
例:「終わるまで絶対に帰らせない」「土日も出てこい」「有休なんて使わせない」
業務上明らかに不要なことや、遂行不可能なことを強制したり、仕事の妨害をしたりする言葉も、パワハラに当たりうる文言です。
過小な要求
例:「もう掃除だけやってればいいから」「電話も取るな」「お前にできる仕事なんてないだろ」
業務を極端に少なくしたり、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事をさせたりする言葉もパワハラに当たり得ます。上記の人間関係からの切り離し同様に、自主退職に追い込むためにこのような言葉を投げかけると、やはりパワハラとしての性質が高まります。
個の侵害
例:「結婚は?」「子ども作らないの?」「もっと痩せたら?」「なんで実家に帰るの?」
プライベートな事柄に過度に立ち入ったり、特定のプライベートな情報に言及したりする言葉となります。このような言葉は、パワハラのみならず、マタハラ(マタニティ・ハラスメント)、セクハラにも当たる可能性があります。
パワハラに認定される基準(パワハラの3要件)
上記の言動・言葉がパワハラに当たるかどうかは、法律上のパワハラに当たるかどうかによって定まります。いわゆるパワハラ防止法(正式名称:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)によれば、事業主は、「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」とされています(30条の2第1項)。
これを踏まえて、厚生労働省は、パワハラの定義を以下の3要素からなるものとしています。
優越的な関係に基づいていること
まず、職場での何からの優越的な関係に基づくものであることが必要となります。例えば上司から部下への言動が最も分かりやすい典型例となります。
他方で昨今は、同僚又は部下による言動でも、その同僚や部下の方が業務上の知識・経験を多く有している場合や、集団による言動である場合など、職場での上下関係に限られないで「優越的な関係」の有無を判断することも認められています。
業務上必要かつ相当な範囲を超えていること
次に、社会通念に照らして、当該言動が明らかに事業主の業務上必要性がないものであったり、当該言動の態様が相当でない(妥当でない)ものであったりすることが必要です。
上記の言葉をご覧いただくと分かるとおり、業務上必要のない言葉や不適切・不適当な言葉を投げかけたりすると、パワハラに当たる可能性が出てきます。
労働者の就業環境が害されていること
最後に、当該言動によって労働者が身体的・精神的苦痛を与えられ、これによって就業環境が害されたことが必要となります。この判断にあたっては、パワハラ的な言動を受けた個人ではなく、平均的・一般的な労働者が同様の状況で当該言動を受けた場合に、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるか否かという視点からの検討がなされます。
一般の労働者が受けたら、通常の就業をすることに支障を来たすかどうか、ということが重要となるわけです。
パワハラ被害の訴えを受けたときの対応
このようにパワハラに該当するかどうかは法的な視点からの検討を要するものです。しかしながら、実際に職場でパワハラ被害の訴えがあった場合には、迅速な一次対応が要求されます。
以下、パワハラ被害の訴えを受けたときの対応方法についてご案内します。
速やかに事実確認を行う
まず訴えがあった場合は、加害者とされる人物、被害者、および目撃者などから詳細な聞き取りを行い、事実関係を把握することが不可欠です。パワハラは言動によるものが多いので、客観的証拠を欠く場合が多いですが、仮にメール・業務用チャットツールなどに証拠がある場合には、当事者が削除する前にその写真などを収集しましょう。
一時的な隔離措置をとる
また、事実確認の間、被害者と加害者とされる人物が直接接触しないよう、配置転換や一時的な在宅勤務指示など、適切な隔離措置を検討する必要があります。これにより、被害者のさらなる精神的負担を軽減し、証拠保全にも繋がります。やはり、事実確認中に加害者とされる人物が他者と口裏合わせしたり、被害者に対して圧力を掛けたりすることは避けなければなりません。
一時的な隔離措置を取る際には、必ず、就業規則などに根拠にできる規定があるかどうかも確認しましょう。この際に、顧問弁護士がいれば、早急に相談するべきです。
弁護士に相談する
これらの一次対応と併行して、または一次対応が終わったら直ちに、弁護士に相談しましょう。確認した事実関係と収集した証拠を踏まえ、パワハラに該当するかどうか、法的視点から助言を得るべきです。
場合によっては加害者側に懲戒処分を下すことも視野に入るでしょうから、早い段階で弁護士に相談し、法的な観点からのアドバイスを受けることで、適切な対応が可能となります。
パワハラと認定された場合、適切な処分を行う
事実確認の結果、弁護士の意見を踏まえてパワハラだと認定する場合には、就業規則に基づき、加害者に対して厳正な処分(例えば、懲戒処分や配置転換など)を行う必要があります。社内外からパワハラを放置する会社であるとの評価を受けることのないよう、適時に対応をとるべきです。
また、被害者へのケアや再発防止策も講じる必要があります。特にパワハラの場合には、使用者である会社自体の責任も追及されます。
未然にパワハラを防ぐには
一度パワハラが起きてしまうと、上記のような対応に追われることとなってしまいます。そこで、未然にパワハラを防ぐための方策についても、ご紹介します。
パワハラ防止措置の徹底
まずは、パワハラ防止措置を徹底することが肝要です。以下のようなパワハラ防止措置を事前にとることをご検討ください。
社内ルールの整備と明文化
社内の就業規則等のルールにおいて、パワハラの定義、具体的な行為例、相談窓口、ハラスメントに対する処分規定などを明確にした社内ルールを策定し、全従業員に周知徹底することが必要です。
パワハラに限らず、ハラスメント全般を取り扱う規定を整備すると、より社員の意識改革に繋がるでしょう。これらの社内ルール策定時には、ぜひ弁護士の助力を受けてみてください。
定期的な研修・教育の実施
また、管理職向け、一般従業員向けに、それぞれパワハラに関する研修を定期的に実施し、ハラスメントについての理解を深めることも有効です。その時々によって、SNSを利用したパワハラや、社内ツールを利用したパワハラなど、時代に応じた研修を定期的に実施することも重要といえるでしょう。昨今では、例えばSOGIハラスメント(性的指向・性自認に関するハラスメント)が一般に浸透しつつあるなど、新たな視点からの教育は必要不可欠です。
特に管理職には、適切な指導方法やアンガーマネジメントなども含めた教育が有効です。先ほどのように、業務上必要のない・妥当ではない言動がないか、研修を再度の確認の場としましょう。
ちなみに、研修講師に弁護士を招くと、訴訟になった場合の行く末も聞くことができますので、加害行為をしやすい方々への抑止力も高まります。
相談しやすい体制の整備
その上で、社内だけでなく、社外の専門機関(弁護士事務所など)にも相談窓口を設置するなど、従業員が安心して相談できる体制を整える必要があります。
そこでは、匿名での相談も可能にする・女性からの相談は女性が担当するなど、相談における心理的ハードルを下げる工夫も重要です。こうすることで相談しやすい体制を整備することができれば、「パワハラをしたらすぐに相談される。」と加害者側に思わせ、抑止力を働かせることも期待できます。
顧問弁護士との連携
これらの事前対応策については、平時から顧問弁護士と連携することで、パワハラ防止策の策定段階から専門的なアドバイスを受けることができます。また、実際に問題が発生した際にも、迅速かつ的確な対応が可能となり、企業の法的リスクを軽減できます。
もしあなたの会社に顧問弁護士が居ない場合には、実際にパワハラ問題が起きる前に、ぜひ顧問弁護士を付けることをご検討ください。平時から相談することができる体制を構築し、あなたの会社の状況をつぶさに理解している弁護士がいれば、有事の際にも、速やかに適切な対応を取ることができるでしょう。
まとめ
以上のとおり、パワハラに当たるような言葉をご紹介した上で、パワハラへの対応・事前予防策についてご案内しました。
パワハラは、働く人々の尊厳を傷つけ、企業の生産性やイメージにも悪影響を及ぼす深刻な問題です。昨今はハラスメント全般に対して世間の目も厳しくなっていますから、「まだあんなことが行われている会社があるんだね。」と後ろ指を指されてしまいかねません。企業は、パワハラの定義を正しく理解し、予防策を講じるとともに、万が一発生した場合には迅速かつ適切に対応することが求められます。従業員一人ひとりが安心して働ける健全な職場環境を築くために、継続的な取り組みが不可欠です。
当事務所では、企業顧問を多く抱えているため、企業法務・労務分野への相談対応、予防法務の観点からの指導・助言をすることに慣れています。ぜひパワハラ問題が起きる前に、当事務所を顧問弁護士に選んでいただくこともご検討ください。当事務所では、多くの弁護士が、あなたの会社からのご依頼をお待ちしております。
監修者
弁護士法人グレイス企業法務部
- 本店所在地
- 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
- 連絡先
- [代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129 - WEBサイト
- https://www.kotegawa-law.com/
「労働問題・労働法コラム」の関連記事はこちら
お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら
電話で問い合わせる
0120-77-9014
受付時間:平日9:00-17:30
メールで問い合わせる
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!
メールでのお問い合わせは24時間受付中!